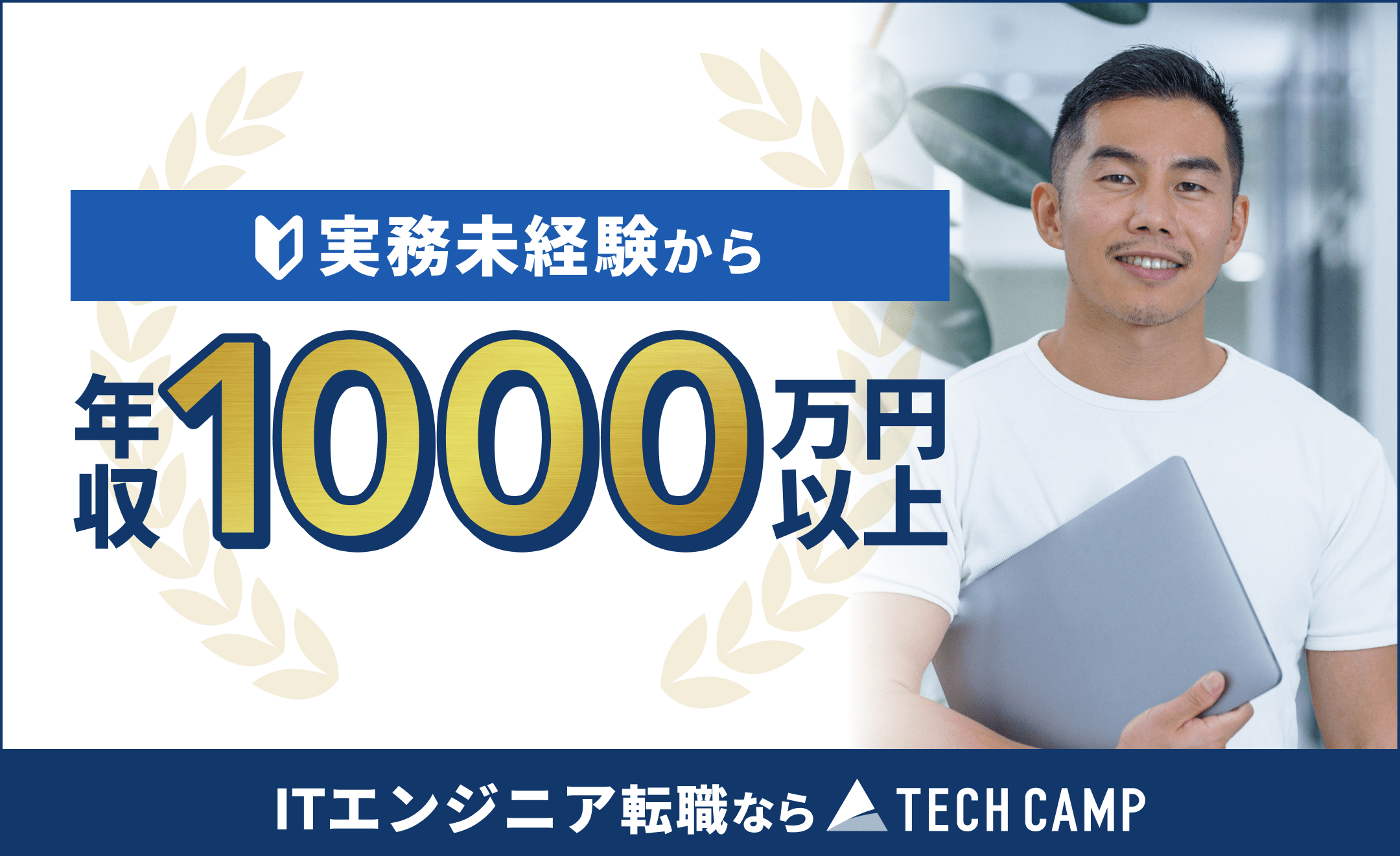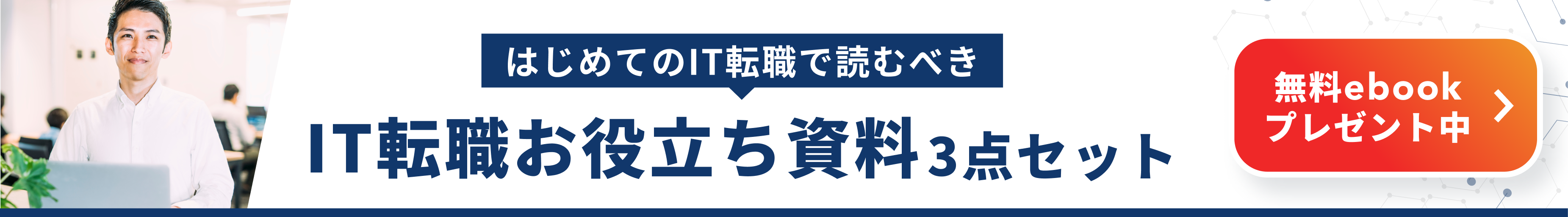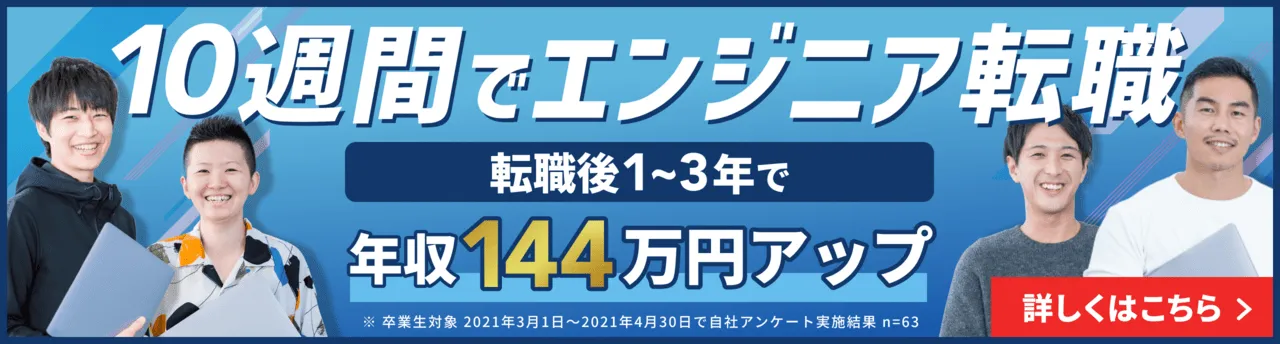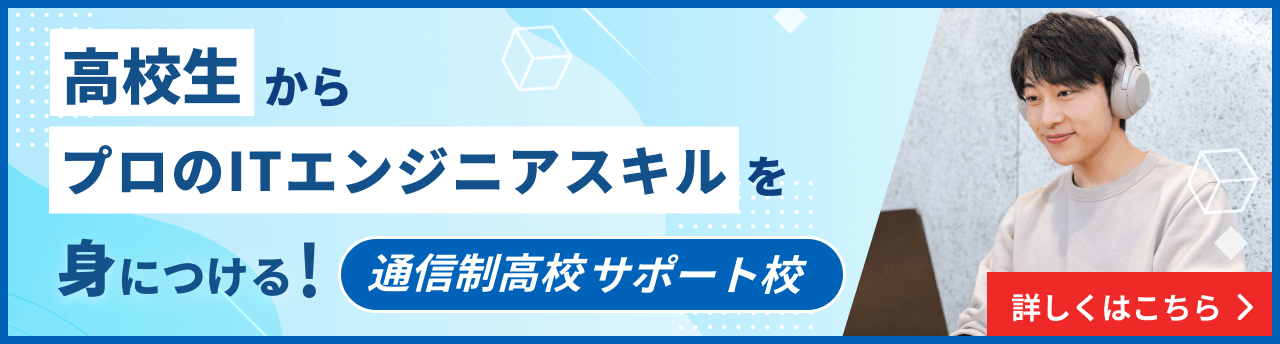「いざ仕事に取り組もうと思っても、なかなか集中できない」
「なぜ自分はあの人みたいに集中できないのだろう」
「仕事に集中できない原因を理解して改善に繋げたい」
さまざまな理由で仕事に集中できない悩みを持つ方は多いでしょう。そこでこの記事では「仕事に集中できない原因」や「集中できないことによる悪影響」などを解説します。
仕事に集中できる状態を作るには、まずは原因を探ることが先決。本記事が仕事に集中できない自分を変えるきっかけになれば幸いです。
この記事もオススメ

この記事の目次

そもそも人間は「集中できない」動物である


「なかなか仕事に集中できない」
「集中力が持続しない」
こんな悩みを持つあなたにぜひ知っておいてほしいことがあります。それは「そもそも人間は集中し続けることはできない動物」だということです。
以下でその理由について実際の調査を元に解説します。
- 東大生の6割近くが大切にしている「集中力」
- 集中力が持続するのは1時間程度
- 集中力の周期は15分
東大生の6割近くが大切にしている「集中力」
ぺんてる株式会社が2018年に東京六大学の卒業生・在校生300名に対して行った「東京六大学卒業生・在校生調査」を見てみましょう。
この調査では、対象者に高校時代の受験勉強についてアンケートを実施しました。すると全体の4割以上の人が、受験勉強で大切なのは「集中力」だと回答。
大学別の結果では、東京大学の卒業生・在学生の6割近くが「集中力」大切だと回答しました。
集中力が持続するのは1時間程度
その一方で、集中力は長く続かないというデータも出ています。同調査では「集中力を維持して勉強できる時間」に関するアンケートも実施。
すると全体の43.8%が、集中できるのは1時間程度と回答しました。
2番目に多かったのは30分程度、そして次に多かったのは1.5時間程度。つまり大半の人が、1時間程度で集中力が切れ、長くても1時間半程度しか続かないのです。
この記事もオススメ



集中力の周期は15分
東京大学の池谷裕二教授は、集中力には周期があり、それは「15分」だと述べました。
池谷教授が行った実験によると、15分×3回で学習したグループの方が、60分続けて学習したグループよりも、脳のパワーが回復。


つまり、「休憩していては仕事が進まない」と言って無理に作業を続けるよりも、潔く休憩した方が仕事がスムーズに進む可能性が高いのです。
参考元:集中力の維持と長期的な学習効果につながる方法(東京大学・池谷裕二教授の見解)
【無料】ChatGPTの使い方をマンツーマンで教えます
・ChatGPTの基本的な使い方がわかる
・AIの仕組みがわかる
・AIをどうやって活用すれば良いかがわかる お申し込みは1日5組限定です。
今すぐお申し込みください。 ChatGPTレッスンを確認する▼
https://tech-camp.in/lps/expert/chatgpt_lesson
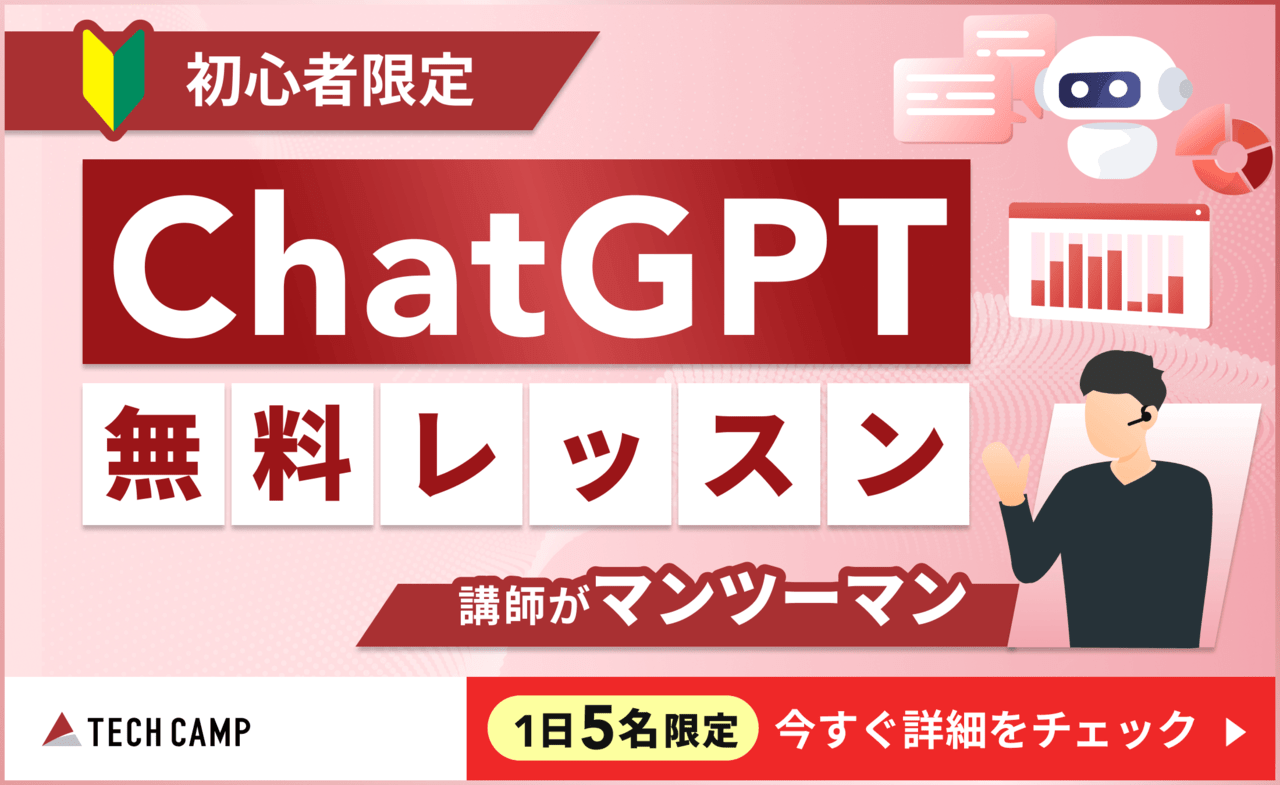
仕事に集中できない人の4つの特徴


仕事に集中できる方法を知る前に、まずは「仕事に集中できない人の特徴」を見てみましょう。
そのような特徴を改善させることも、仕事に集中できる人になるためには必要です。
- 複数の作業を同時に取り組もうとする
- 計画を立てるのが苦手
- 何事にも飽きやすい性格をしている
- 体調管理ができていない
複数の作業を同時に取り組もうとする
複数の作業を同時に取り組む、つまり「マルチタスク」の状態は、脳が混乱状態に陥りやすくなります。
上記記事にもある通り、マルチタスクは脳のワーキングメモリを圧迫してしまいます。その結果、生産性や判断力の低下をもたらしてしまうのです。
あなたにも「仕事を一気に終わらせよう」として、さまざまな資料を一気に広げたり、ブラウザのタブをいくつも開いた経験はありませんか。
そのような行為は、結局一つ一つの物事に集中できない要因になります。そして「いつまでも仕事が終わらない状態」に陥りやすくなるのです。
この記事もオススメ
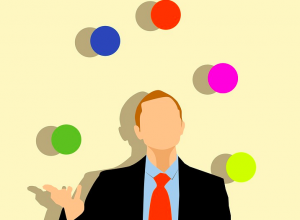
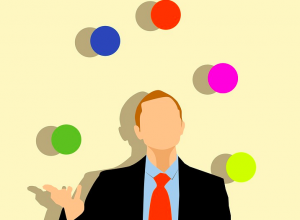
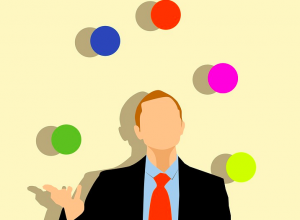
計画を立てるのが苦手
仕事に集中できない人は、頭の中が整理されていない状態です。つまり、物事の優先順位がつけられていないのです。
例えば、あらかじめ締め切りが決まった業務があれば、その締め切りから逆算して「今日やること」「今週中に終わらせておくべきこと」と、物事を順序よく進めなければなりません。
一方でそのような計画を立てていないと、上司から急に別件で「これ明日までにやっておいて」と言われたときに、軽く引き受けてしまいます。
その結果、目の前にやらなければならないことがたくさんある状態になり、脳がパニック状態に陥りやすくなり、なかなか集中できなくなってしまいます。
この記事もオススメ



何事にも飽きやすい性格をしている
何事にも飽きやすい性格は、「集中力」に直結します。実は「集中力」の50%近くは、遺伝的なものに関わるといわれています。
しかし、ここで「じゃあ自分が飽きっぽくて集中できないのは仕方ないのかも」と諦めないでください。なぜならあとの50%は、あなたの取り組み次第で変えられるからです。


例えばあるWeb記事を読んでいても、わからないワードがあればすぐに調べてしまい、それから次々にブラウザのタブを開いて本題から脱線してしまう…なんてことはありませんか。
自分の中で、このような好奇心旺盛な部分や飽きやすい部分を意識している人はなおさら、集中力を高める努力をする必要があります。
「仕事に飽きた・辞めたい」と感じている方は「仕事に飽きた・辞めたい・めんどくさい時の対処法5つ!転職した方が良いケースも紹介」もご覧ください。
体調管理ができていない
集中力は、脳のコンディションに大きく影響します。つまり、脳を含めた体全体の管理ができていない人は、仕事に集中することも難しくなるのです。
例えば「集中しすぎていてご飯を食べるのも忘れていた」というフレーズをよく耳にします。


また、そうやって食事を取らずに作業を続けた結果、反動で体調を崩したり「頑張ったからご褒美」とダラダラと長時間過ごしてしまったりしては、元も子もありません。
大切なのは、集中したいときに一気に集中できる体の状態を整えることなのです。そのためには、基本的な生活習慣を整え、適宜休憩を取ることも重要です。

「仕事に集中できない」状態に陥る9つの原因


あなたが仕事に集中できないのは、以下のような理由からかもしれません。もし当てはまるのであれば、これらを解決する必要があるでしょう。
- 向上心がない
- 職場が騒がしい
- 人間関係が悪い
- 仕事と関係のないツールを使ってしまう
- 十分な休みが取れていない
- 仕事の納期やノルマに余裕を持ちすぎている
- 能力と仕事が見合っていない
- やりたい仕事ができていない
- プライベートでの理由
向上心がない
向上心がある人は、努力を惜しみません。「目の前の物事に最善を尽くすためにはどうすればよいのか」を考え、実行していけます。
一方でそのような向上心がないと、目の前のことに集中できません。
「なぜ自分がこんなことをやらなければならないのだろう」
「これをやっても意味ないよね」
そんな考えにとらわれ、集中力を保てないのです。
この記事もオススメ



職場が騒がしい
仕事に集中できるかどうかは、周囲の環境にも左右されます。例えば集中できないほど職場が騒がしいのは問題でしょう。
- 周囲の人が雑談ばかりしている
- 上司が自分のデスクから移動せず、頻繁に大声で部下を呼ぶ
こんな環境では、集中できないのも当然といえます。
この記事もオススメ



人間関係が悪い
仕事の集中力に影響が及ぼすほど、職場の人間関係が悪いことも考えられます。例えば以下のようなケースです。
- ミスに対して異常に怒る上司がいる
- 仲の悪い先輩同士の板挟みになっている
- 同僚からの陰口など、いじめのような扱いを受けている
このような状況下では、どうしても目の前の業務に集中できません。集中力は、体だけでなく精神も安定して初めて発揮されるからです。
この記事もオススメ



仕事と関係のないツールを使ってしまう


仕事と関係のないツールを使ってしまい、時間を無駄に消費してしまうことも集中できない原因の1つ。仕事と関係のないツールの代表例は、やはりスマートフォン(スマホ)です。
スマホはもはや私たちの生活に不可欠で便利なツールですが、それゆえの弊害もあります。その一つが、得られる情報量の多さです。
「休憩中にスマホをパッと見ただけで、SNSの通知を見つけてしまい、そのままタイムラインを流し読みしていたら30分以上経っていた…」こんな経験は誰もがあるはず。
スマホにはさまざまな通知が来ます。例え今まで集中したとしても、気になる通知があればそちらに目が行ってしまうのは仕方のないこと。
それがわかっていれば「集中したいときはスマホは見ない」「机の引き出しにしまっておく」と決めることも大切です。
この記事もオススメ



十分な休みが取れていない
ここまで述べてきた通り、集中力は脳のパフォーマンス次第。つまり脳を含めた体全体に疲労やストレスが溜まっていれば、うまく力は発揮されないのです。
あなたは最近、残業が続いて疲れていませんか。休日返上で仕事に取り組んでいませんか。
もしそのような状況が続き、睡眠不足、体のだるさ・重さなど、体力的・精神的な疲労を実感しているのであれば、集中できないのは仕方のないこと。
可能な限り休みをとり、体力を回復させることが大切です。
睡眠不足は特に注意
睡眠不足は集中力の敵です。とくに睡眠時間が6時間未満の人は要注意。
慢性的な睡眠不足は思考力や判断力の低下を引き起こす原因となります。


つまり、せっかく集中しても周囲の物や音にすぐに反応してしまい、集中時間が続きにくいのです。
仕事の納期やノルマに余裕を持ちすぎている
仕事の納期に余裕があると「早めに手をつけている自分」に満足して、業務がおろそかになる傾向があります。
「早めにやっている自分にご褒美」「これくらい休んでもいいだろう」と、ついつい業務の合間の休憩時間が長くなってしまった経験はありませんか。
そして「余裕だと思ったのに」と、最終的に焦る事態に陥ります。


これは心理学者エドウィン・ロックとゲイリー・レイサムによって提唱された「目標設定理論」でも明らかにされています。
仕事上でモチベーションを上げるためには、今の自分のスキルを正しく理解し「達成できるかできないかくらいの目標」を設定することが重要なのです。
「仕事のモチベーションを上げる13の言葉!すぐにやる気が出る方法を一挙紹介」では、仕事のモチベーションを上げる言葉・本・映画を紹介しています。
目標設定理論をはじめとしたモチベーションに関する理論についても紹介していますので、あわせて参考にしてください。
能力と仕事が見合っていない
今あなたが携わっている仕事は、あなたの能力に見合ったものでしょうか。これは前述したノルマの部分にも関係します。
今の自分にとって「全力で取り組んでもできるかどうかわからない業務」でなければ、モチベーションが上がらず、集中できない要因になるのです。
「こんなものは誰でもできる」
「自分がやらなくてもいい」
そう思える業務であれば、その仕事は後輩に任せ、新たな業務に携われるよう上司に直訴することもおすすめです。
投げやりになってしまったり、集中力を切らしてだらだら仕事をしたりするよりは、スキルアップに繋がる業務を自ら見つけましょう。
やりたい仕事ができていない
そもそも、現在の仕事にやりがいを感じない場合、身が入らないのは自然なこと。
目標を達成することで正当な評価やインセンティブがもらえたり、スキルアップにつながったりするなどのメリットがあれば話は別。
しかし何のメリットもないと、やりたくないことをやらされるのは苦痛に感じるでしょう。
このような場合、先述の「能力と仕事が見合っていない」と同じく、別の仕事に携われるよう上司に相談するのが効果的な対策です。
相談の際は「将来を見据え、こういう作業がしたい」「より業務を効率化するために、この作業がやらない方が良い」など、正当な理由を付け加えましょう。
それでも仕事内容を変更できないならば、転職も視野に入れるべきかもしれません。
この記事もオススメ



プライベートでの理由


あなたが仕事に集中できないのは、プライベート上の出来事が関係しているのかもしれません。
例えば以下のようなことです。
- 身近な人の不幸
- 配偶者(恋人)との喧嘩
- 子供にきつく当たってしまった
- 子供が学校でトラブルを抱えている
- 親の介護による疲労
- 友人との金銭トラブル
プライベートの問題は仕事とは切り離して考えるべきですが、心配事が大きければ大きいほど、頭の中を占める割合も大きくなるもの。
休日はこのような課題の解決に励むなど、根本の原因を取り除かないと、仕事の集中ができないことも考えられます。
恋愛や友人関係などに気を取られている
「プライベートでの理由」にもつながりますが、恋愛や友人関係など、クリアに解決できない悩みが集中力の妨げになっている可能性もあります。
特に、「現在恋愛中で仕事に集中できない」という人は、ホルモンの影響を受けているのかもしれません。
例えば恋愛中に分泌されるドーパミンは、欲望を抑えられなくする働きを持ちます。
そのため「仕事中なのに恋人からの連絡が気になり、ついスマホの画面を眺めてしまう」といった事態に陥りやすくなります。
仕事に集中できないことで起こる悪影響


仕事に集中できないと、以下のような4つの悪影響を引き起こします。
- 仕事がはかどらない
- ミスを引き起こしてしまう
- 周りから煙たがられてしまう
- 自分の成長につながらない
仕事がはかどらない
集中できないと仕事がはかどらないのは当然です。ダラダラと過ごす時間が増え、業務が進みません。また、マルチタスクで「仕事をしている気になっている状態」も問題。
いくつも資料を広げ一気に業務を進めているように見えても、実は一つ一つの業務に集中できておらず、効率が悪くなっているのです。
ミスを引き起こしてしまう
集中力が落ちた状態で仕事を続けると、ミスが発生する要因になります。なぜなら、脳のパフォーマンスが落ち、思考力や判断力が低下するからです。
あなたには、デスクからしばらく離れた後に業務に戻り、それまで行っていた業務のミスに気づいた経験はありませんか。


ですから、もしある程度業務を続けて集中力が途切れるのを実感したら、その作業を一旦切り上げるのも一つの手です。
そしてしばらく休憩した後に作業に戻れば、休憩前に気づけなかったミスに気づくことができるでしょう。
この記事もオススメ



周りから煙たがられてしまう
集中せずにぼーっとしていると、仕事をしていない人だと思われる可能性があります。
また、実際にそれで作業が遅くなると「仕事ができない人」のレッテルを貼られることも。
最悪「同じだけ給料をもらっているのにあいつはサボってばかりだ」「全然役に立たない」と周囲から不満があがり、煙たがられてしまうことも考えられます。
自分の成長につながらない
人は限りある時間で集中して働き、自分を追い込むことで成長します。一方、集中できずにダラダラ仕事をしていても、自己成長は見込めません。
では、なぜあなたは仕事に集中できず、成長できないのでしょうか。その要因の一つに、仕事の難易度が関係しています。


一方で、業務の難易度があまりにも高すぎても「到底頑張っても達成できなさそうなもの=放置するもの」と判断する原因になります。
重要なのは、今のあなたの能力で達成可能かどうかを容易にははかれない「ギリギリの難易度」を設定することです。
そのような業務であれば、人は限られた時間で今の自分の能力を最大限発揮できるように集中します。そうやって仕事に取り組んだ結果、自己成長へとつながるのです。
この記事もオススメ



仕事に集中するためのコツを知ろう
仕事に集中できない人にありがちな特徴や仕事に集中できない原因、集中できないことによる悪影響などを解説しました。
そもそも、人間という動物は集中力を長時間維持することはできません。しかし、集中できない内的要因や外的要因を知ることで、集中力を回復させることは可能。
仕事に集中するためには、具体的には以下のような方法が効果的です。
- デスク周りの整理整頓
- 1日のタスクの書き出し
- 短時間集中することを意識する
- コンスタントに休憩を取る
- リラックスして集中できる音楽を聴く
- 仕事の割り振りを考える
上記の通りで、「やることを決める」「時間を限定する」「体調を整える」といったことが重要なポイントといえるでしょう。
集中できない状況から脱却するための詳しい方法については「「仕事に集中できない人」から脱却する効果的な方法6選。おすすめの本も紹介」をご覧ください。
はじめての転職、何から始めればいいか分からないなら
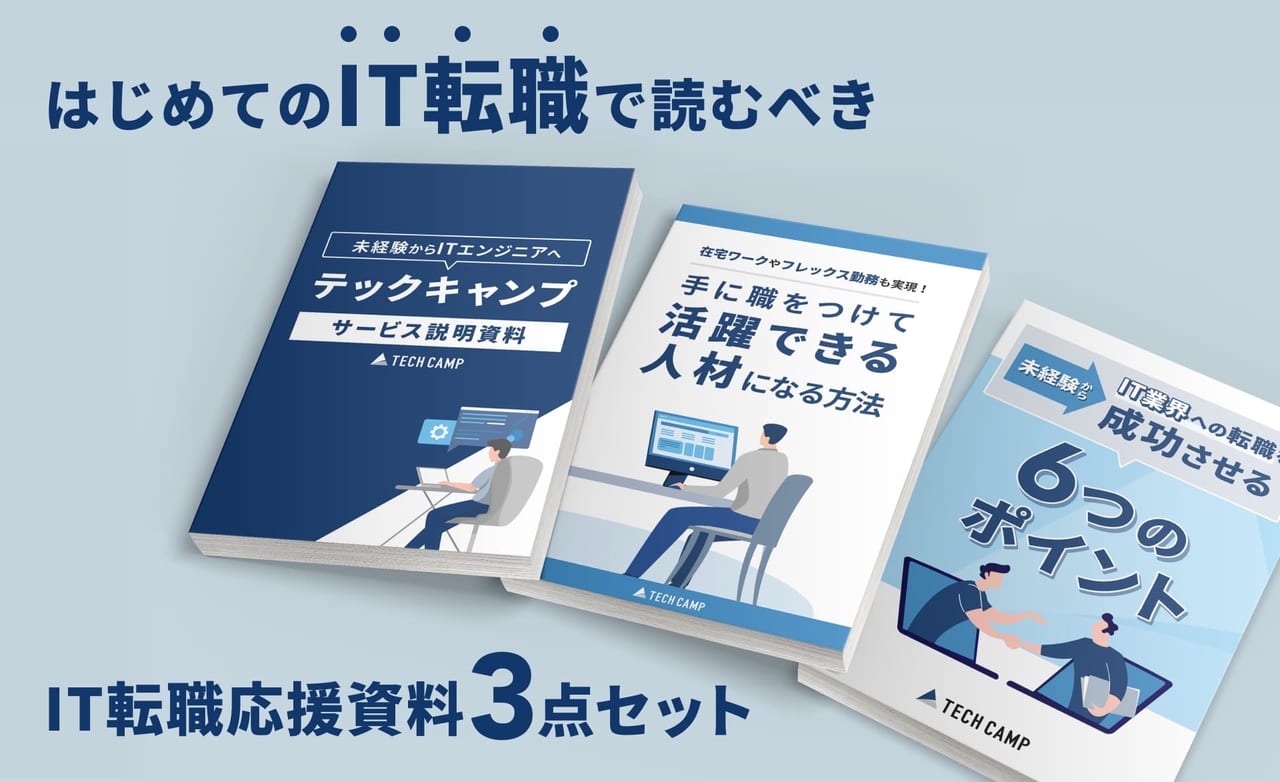
「そろそろ転職したいけれど、失敗はしたくない……」そんな方へ、テックキャンプでは読むだけでIT転職が有利になる限定資料を無料プレゼント中!
例えばこのような疑問はありませんか。
・未経験OKの求人へ応募するのは危ない?
・IT業界転職における“35歳限界説”は本当?
・手に職をつけて収入を安定させられる職種は?
資料では、転職でよくある疑問について丁寧に解説します。IT業界だけでなく、転職を考えている全ての方におすすめです。
「自分がIT業界に向いているかどうか」など、IT転職に興味がある方は無料カウンセリングにもお気軽にお申し込みください。