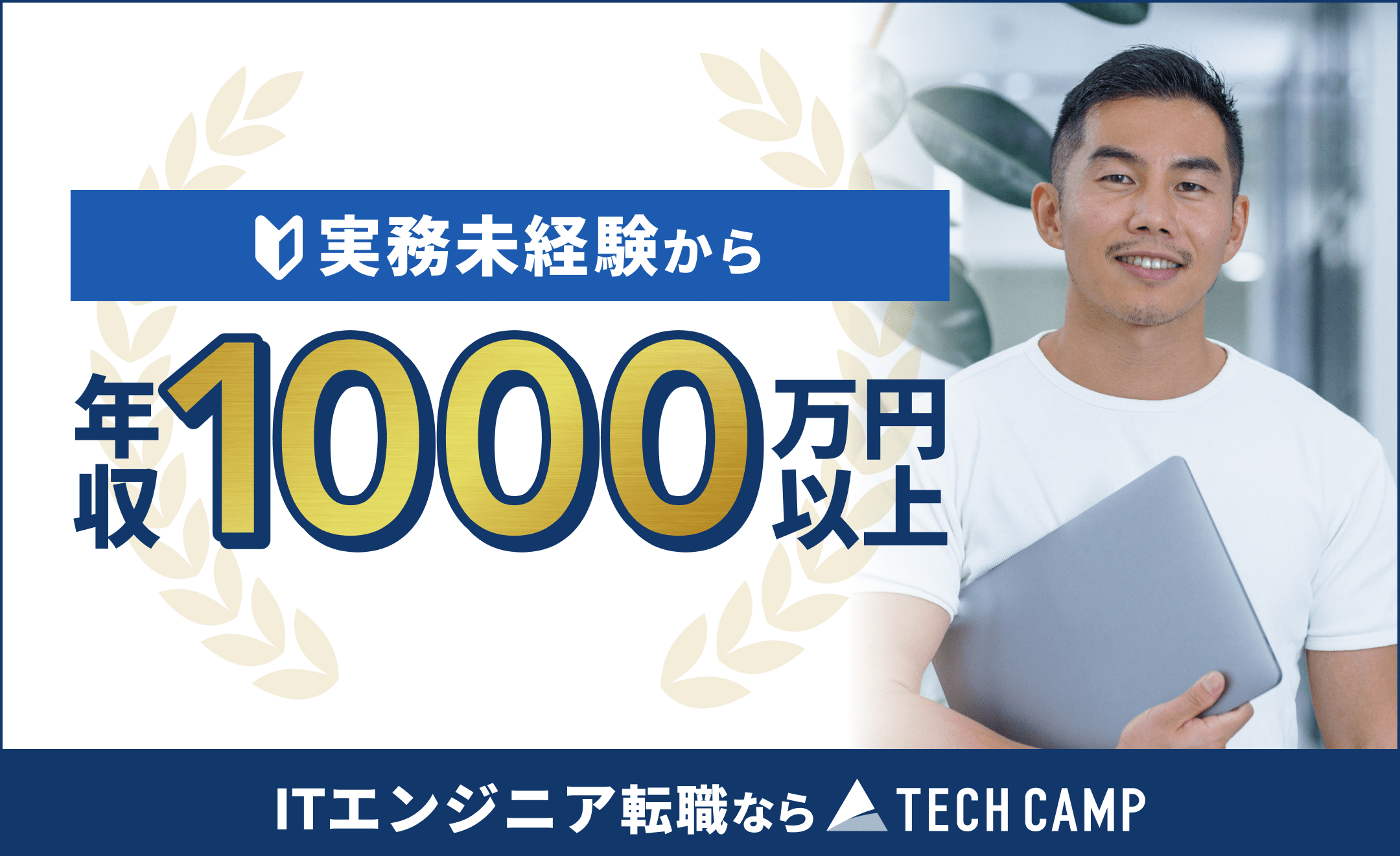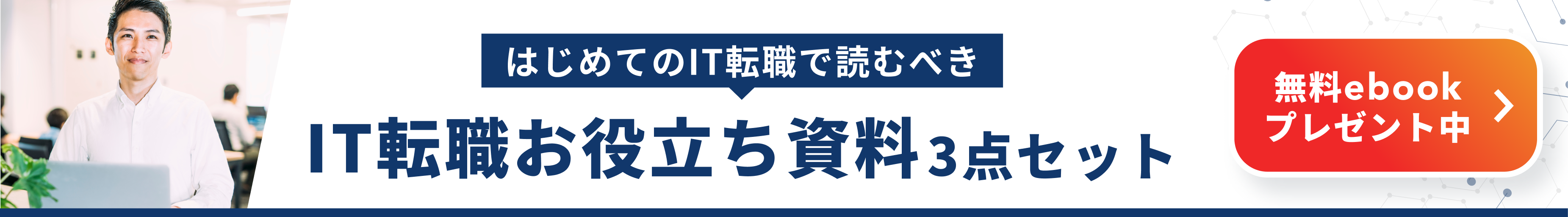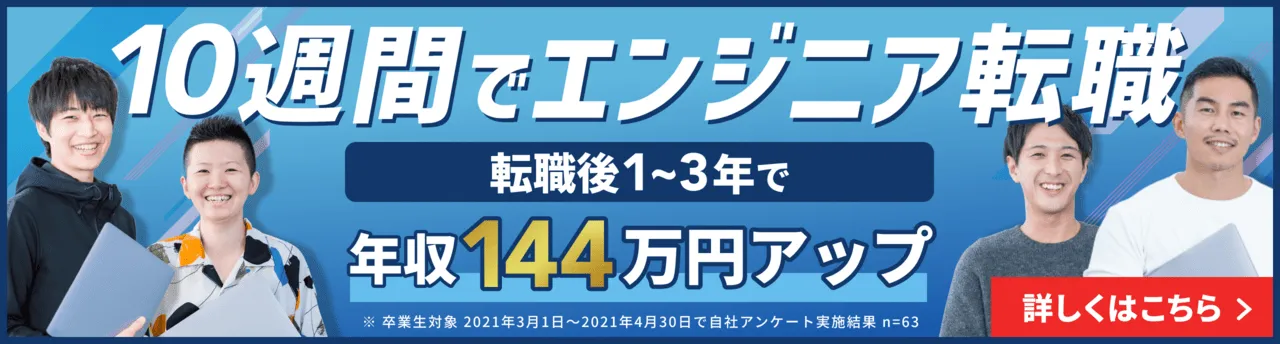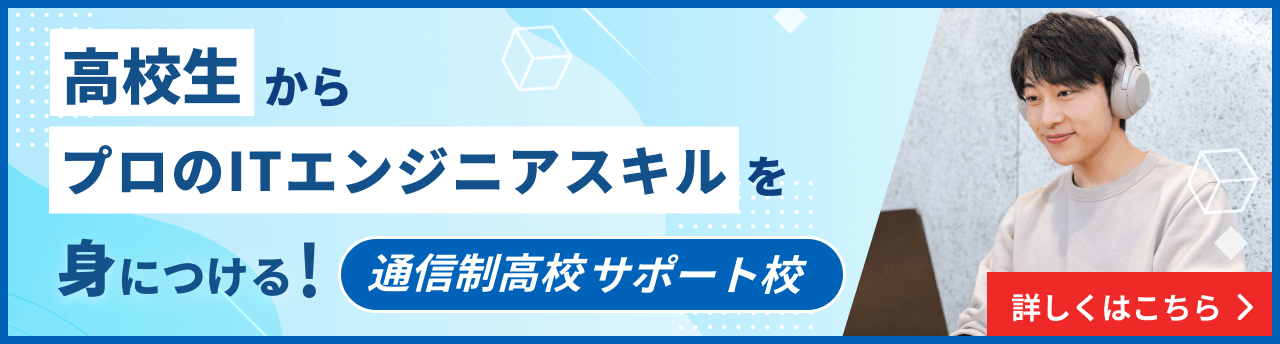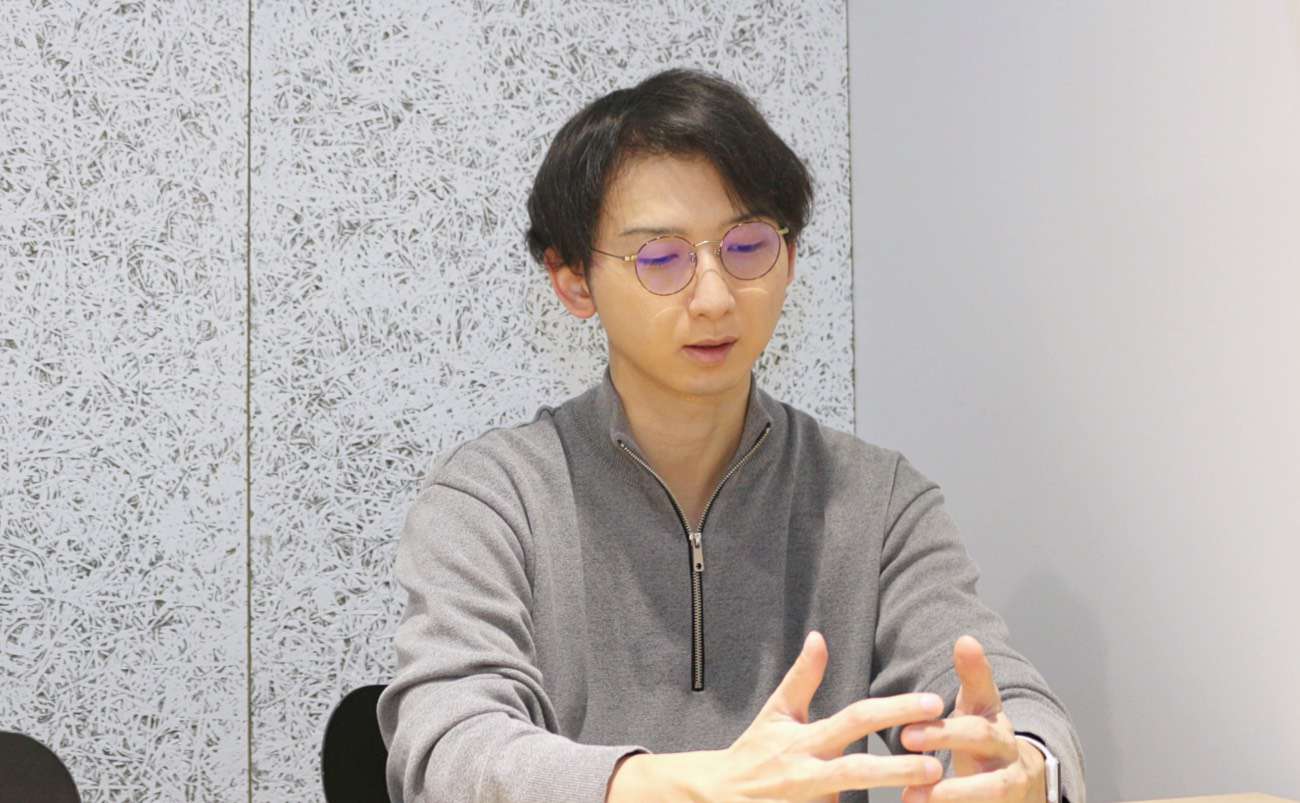「マネジメントという言葉をなんとなく使っている」
「マネジメントが本当は何かよく知らないので理解したい」
「明日から実践できるマネジメントのコツが知りたい」
マネジメントスキルは現代のビジネスパーソンに求められる能力の1つ。
本記事では、マネジメントがぼんやりとしかわからない人向けに、意味・目的・種類などについて、わかりやすく解説します。
また、マネジメントを成功させるためのポイントや、具体的な事例なども紹介。
マネジメントの意味を知って今後の仕事に活用できるよう、ぜひ参考にして下さい。
この記事の目次

マネジメントとは?意味を簡単に紹介

マネジメントは直訳すると、「管理」「経営」といった意味。日本語で言い換えると「経営管理」を意味しています。
マネジメントとは、計画-組織-統制の一連の活動。企業に導入されれば経営管理。しかし、マネジメントは役所、学校、政党のような組織体にも不可欠である。マネジメントには、マネジメント機能が必要であるが、マネジメント機能は計画-実行-審査(plan-do-see)の循環であると開設している。計画を立て、実行し、その結果を比較・分析・審査することによって、つぎの計画をより合理的にたてるよう配慮するといった考えや態度、やり方である。
マネジメントという言葉は、組織においての「経営管理」を意味しているのです。
この記事もオススメ

ドラッカーが説く「マネジメント」の定義が一般的
マネジメントの言葉の定義に関しては、経営学者として有名なピーター・ドラッカーの著書「マネジメント」で表された定義が、一般的に認識されています。
日本では、その内容がわかりやすくまとめられている「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの”マネジメント”を読んだら」が大ヒットしました。
ドラッカーが定義するマネジメントについて
ドラッカーは、マネジメントについて「組織に成果を上げさせるための道具、機能、機関」と定義しています。


マネジメントはビジネスでの重要性が高まっている


マネジメントがうまくいくかいかないかで、組織のパフォーマンスが大きく変わるため、ビジネス面での重要性が高まっています。
変化の激しい時代である昨今、その流れに対応して環境を変えていかなければ、簡単に遅れを取ってしまうでしょう。
その中で成長し続けるには、現場の人材育成や生産性向上のノウハウ、業務効率化などを日々アップデートして成果を上げていかなくてはなりません。
これらを成功に導くには、組織の成果を上げるマネジメントが重要なのです。
【無料】ChatGPTの使い方をマンツーマンで教えます
・ChatGPTの基本的な使い方がわかる
・AIの仕組みがわかる
・AIをどうやって活用すれば良いかがわかる お申し込みは1日5組限定です。
今すぐお申し込みください。 ChatGPTレッスンを確認する▼
https://tech-camp.in/lps/expert/chatgpt_lesson
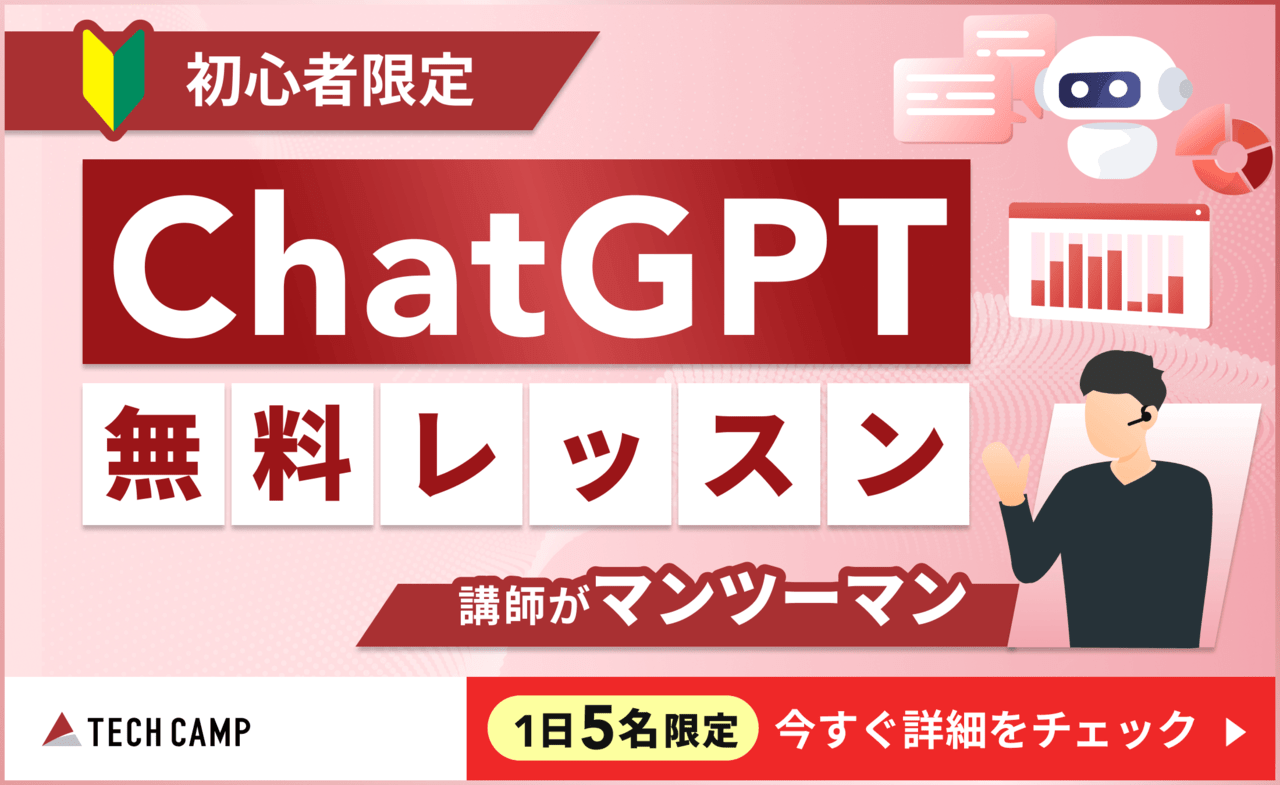
マネジメントとリーダーシップの違い


マネジメントとリーダーシップはよく混同されがちです。
リーダーシップは、平たく言えば「牽引する能力」のこと。目標を定めた方向に、集団を引っ張っていき、導く能力のことを指します。
一方、マネジメントは、定めた目標を達成するための手段を考え、模索して、集団を管理するという役割を指すのです。
また、リーダーシップでは「人柄」や「誠実さ」といった、人を惹き付ける能力が重要なのに対し、マネジメントは「現実主義」「論理的な思考」などの考え方ができるかが大事。
そのため両者の意味合いは、似て非なるものなのです。
この記事もオススメ




マネジメントを行う目的と役割


ビジネス面で重要性が高まっているマネジメント。では、マネジメントを実際に行う目的と役割はどのようなものなのでしょうか。
本章では「マネジメントを行う目的と役割」を解説します。
マネジメントの目的
マネジメントの目的は、「設定した目標に沿って組織を運営する」ことです。
つまり、組織の経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報」を効率的に運用することで、設定した目標に向かい、組織を発展させ続けることがマネジメントの目的と言えます。
マネジメントの役割
マネジメントの役割は以下の3つに大きく分けられます。
- 自らの組織に特有の目的を果たす
- 仕事を通じて働く人を生かす
- 自らが社会に与える影響を処理するとともに、社会の問題について貢献する
わかりやすく言い換えると、以下の通り。
- 組織自体が設定している目的の達成
- 組織に所属している個人個人の自己成長
- 組織がもたらした利益による社会貢献
また、マネジメントは会社の経営層だけが行うわけではありません。社内のプロジェクトチーム内であっても、マネジメントをする必要があるのです。
マネジメントの種類
マネジメントにはさまざまな種類があり、対象によって内容が変わってくるのです。
そこで本章では「組織の階層による分類」と「業務領域による分類」の2つに大別して、マネジメントの種類を紹介します。
組織の階層による分類


組織の階層による分類は「経営者層」「管理者層」「監督者層」の3つにわけて考えられます。以下で1つずつ、どのような内容なのかを解説。
経営者層
経営者層が行うマネジメントを「トップマネジメント」と呼びます。
トップマネジメントは、組織全体の方針や目的の決定をした上で戦略を検討。
そして、マネジメントをする役割を担うメンバーに振り分けて取り仕切らせるといった、大きな組織を動かす骨組みとなるのです。
管理者層
中間管理職などの層が担うマネジメントを「ミドル・マネジメント」と呼びます。
トップマネジメントで決めた会社全体の方針や目的を、どのように現場に落とし込むかを考えて実行していかなければいけません。
実際に自分の仕事をしながら、マネジメントを行う視点も持っていないといけない難しい役回りでもあります。
監督者層
現場に最も近い監督者層が担うマネジメントを「ロワー・マネジメント」と呼びます。
ミドル・マネジメントで決まった具体的な目標を考慮し、現場にいる人材と予算をどのように使って目標を達成するかを考えなくてはいけません。


この記事もオススメ



業務領域による分類


業務領域による分類は「組織運営」「人材管理」「メンタルヘルス」の3つにわけて考えられます。以下で1つずつ、どのような内容なのかを解説。
組織運営
組織運営の領域には、「プロジェクトマネジメント」「チームマネジメント」「ナレッジ・マネジメント」などの種類があります。
組織で設定している、プロジェクト全体の運営計画や管理を行ったり、チームメンバーとのコミュニケーションを図ったりするのも組織運営の一部です。
また、個々人が持つ知識やスキルをうまく扱うのも組織運営に含まれます。
この記事もオススメ



人材管理
人材管理の領域には、「タレントマネジメント」「ダイバーシティマネジメント」「モチベーションマネジメント」などがあります。
人材のスキルを明確化したり、グローバルな人材が働きやすいよう文化や制度を調節するのが、人材管理の役割です。


この記事もオススメ



メンタルヘルス
メンタルヘルス領域には「メンタルヘルス・マネジメント」「ストレスマネジメント」「アンガーマネジメント」などがあります。
メンバーの行動や心理、社員の不調などに対応して、現場の活力を保たせる役割。
また、個人のストレスや怒りをコントロールして、全体のパフォーマンスを向上させるのもメンタルヘルスの領域です。
この記事もオススメ



マネジメント業務の具体例


マネジメントの具体的な仕事内容は一体どういったものなのでしょうか。
本章では、マネジメント業務の具体例を6つ紹介します。
- 組織にあった目標設定
- 管理する組織の業務管理
- それぞれの能力を生かせる環境づくり
- 正しい評価とフィードバック
- チームメンバーの育成
- コンプライアンスの遵守の徹底
組織にあった目標設定
会社としての目標に沿って、自分が管理する組織にフィットする目標を落とし込む作業は、マネジメントの仕事です。
マネジメントでは、チームや部下の目標設定をすることがよくあります。この目標設定が担っているのは、チームにいるメンバーや、部下にとってのゴールを定める役割。
すなわち「今、どういった目標に対して進んでいるのか」「どうすればうまく進むことができるのか」などを明確にするのが、マネジメントの業務の1つなのです。
この記事もオススメ



管理する組織の業務管理
業務の進捗管理や課題解決を行うのもマネジメントの仕事です。
マネジメントがうまくできていないと、「業務が今どのくらい進んでいるのか」や「課題に行き詰まっていないか」などが不透明になります。
作業の効率を上げるためには、そういった業務の管理が必要です。誰が何をどのように行うかの定義をしてあげないといけません。


この記事もオススメ



それぞれの能力を生かせる環境づくり
組織の中で目的ごとにチームをわけ、人員を選定する場合、それぞれの能力を生かせる環境づくりをしなければいけません。
適材適所にメンバーを配置するのもマネジメントをするうえで重要な仕事。そのためには個人個人の得手不得手を把握しておかなければならないでしょう。
また、編成後に自らすすんでコミュニケーションを取るのも大切な仕事です。
この記事もオススメ



正しい評価とフィードバック


メンバーや部下の業務に対する正しい評価とフィードバックもマネジメントの仕事。
そして、正しい評価やフィードバックに必要な評価制度の整備・改善も重要です。
「目標設定」と「評価・フィードバック」はセットで行います。
この記事もオススメ



チームメンバーの育成
正しい評価やフィードバックなどを含め、チームメンバーを育成するのもマネジメントの仕事として非常に重要です。
メンバーのモチベーションを上げたり、適切なサポートしたり、上手な支援行動をすることで人材は育ちます。
その結果、チームメンバーの育成に成功すれば、個人のみでなく、組織全体のパフォーマンスが向上するのです。
この記事もオススメ



コンプライアンスの遵守の徹底
マネジメントをする上では、法令や規則を破らないように、コンプライアンスの遵守を徹底しなければいけません。
そのため、労働関連法規や業務に関する法律の理解を深めましょう。
会社の機密情報や個人情報の適切な管理は、マネジメントにおいて重要な役割なのです。
マネジメント業務に向いている人の特徴


マネジメント業務に向いている人の特徴を挙げると、以下の通り。
- 円滑なコミュニケーションが取れる:マネジメントにおいては、チームメンバー・上司・クライアントなどとの効果的なコミュニケーションが不可欠
- リーダーシップを発揮できる:組織やチームのベクトルを合わせ、同じ目標に向かって導けるリーダーとしての能力も問われる
- 問題解決能力がある:日々の業務で起こるさまざまな問題や課題に対して、的確に分析し解決策を見出す能力も重要
- 適切なスケジュール管理ができる:タスクやプロジェクトを効果的に管理し、適切なスケジュールやリソースを割り当てることもマネジメントにおいて重要
- チームビルディングに秀でている:マネジメント業務ではチームメンバー間の信頼関係を構築し、協力関係を促進する役割もある
企業や携わる分野などによってマネージャーに与えられる業務範囲は異なるものの、これらの特徴があるとマネジメント業務を効率的に遂行できるはずです。
この記事もオススメ



マネジメントを成功させる4つのポイント


マネジメントは、時代の移り変わりに伴い、日々新しいものへとアップデートしていかなければなりません。そこで本章では、マネジメントを成功させるポイントを4つ紹介します。
- 可視化された評価制度
- 情報共有を徹底する
- 現場の声に振り回されない
- さまざまな働き方への対応
この記事もオススメ



可視化された評価制度
評価制度を可視化することで、活発な組織づくりにつながります。
例えば、社内で意見などを積極的に言う人は目立ちますが、そのような人ばかりが成果を挙げているわけではありません。
目立たなくても会社に貢献している人はたくさんいます。しかし、成果がわかりづらいため評価が難しいのです。
こうした不透明な部分をなくすために、正しい評価制度が重要になってきます。
例えば「Unipos株式会社」では、成果が目に見えづらいエンジニアに焦点を当てて「発見大賞」という他薦のMVP制度を作りました。
他にも、従業員同士で互いにポイントを送り合えるシステムを導入し、一定数のポイントが貯まるとAmazonのギフト券がもらえる仕組みも構築。
その結果、Uniposはエンジニアの離職者が大幅に減少、会社自体も活気づき、東証マザーズ上場も果たしました。


情報共有を徹底する
業務における情報共有の徹底はとても重要です。また、マンパワーに頼らない環境を作るためのナレッジの共有も大切。
「M.T.Burn株式会社」では、それぞれの営業マンの役割をずらして情報共有をさせることで、その人が共有しなければ皆のミッションが成り立たない状況をあえて作り出しました。
そうすることで、他の人がしていることを知りたくもなり、また、知らなくてはいけないといったサイクルが完成。
積極的に情報を共有していく環境ができあがり、新しいものを生み出せるチーム作りにも役立っています。
ほかにも「株式会社リクルートライフスタイル」ではプロジェクト関係者しか関連情報にアクセスできない情報をオープン化して、誰でも閲覧が可能に。
その結果、行き詰まっている人がいても、他のメンバーがすぐにアドバイスを送れるような環境ができあがり、業務の生産性が向上しました。
情報共有の考え方ひとつで、さまざまなメリットが生まれるのです。
現場の声に振り回されない


現場の声は短期的なビジョンである場合が多いので、全てを鵜呑みにして振り回されることのないように気を付けましょう。
マネージャーは会社の目標に沿った多角的な視点で、長期的なスパンを考えた改善策を提案しなければいけません。
現場の声は汲み取りつつも、振り回されないことがマネジメント成功の秘訣です。
さまざまな働き方への対応
現在は、海外のビジネスパートナーも増加しているので、グローバル化に対応するマネジメントが必須です。
また、少子高齢化の影響で、これからさらに労働人口が減っていきます。
そのため、出産や介護などで働くことができなかった層や、元気な高齢者に対しても、柔軟な働き方ができる環境を用意することが必要。
その他にも、働き方改革の推進によってリモートワークで働く方が増えれば、今までとは違ったマネジメントのアプローチが必要となるでしょう。
さまざまな働き方に合わせて、マネジメントも多面的に広げていく必要があるのです。
この記事もオススメ



マネジメント能力を高める方法


マネジメントスキルを高める方法としては、以下の通り。
- 現場でマネジメント職を経験する
- マネジメント本で勉強する
- マネジメント系の資格を取る
- プライベートでマネジメントをやってみる
チームリーダーやプロジェクトマネジャーといった、マネジメント職を経験できる現場ならば、確実にスキルが身に付きます。
あるいはドラッカーの「マネジメント」などの本で勉強する、「プロジェクトマネージャ試験」などの国家試験に挑戦するのもあり。
身近で鍛えるならば、サークル活動のまとめ役や、友人・家族・恋人との旅行計画をスケジューリングしてみるのもよいでしょう。
この記事もオススメ



マネジメントはビジネスの成功に欠かせない
マネジメントは組織全体のパフォーマンスを上げる重要な業務。
マネジメントを通してチームメンバーの負担が減少し、その結果モチベーションの維持・向上などにつながり、新しい価値を生み出す土台が構築されます。
ビジネスが上手くいく背景には、画期的なビジネスモデルはもちろんのこと、マネジメントの成功があってこそ。
また、マネジメント能力を鍛えることで、限られた人的資源を上手く活用できます。人手が不足している日本において、そのような人材はとても重宝されます。
その結果、自身のキャリアアップにもつながりやすくなるので、マネジメント能力は磨いておくべきでしょう。
この記事もオススメ



はじめての転職、何から始めればいいか分からないなら
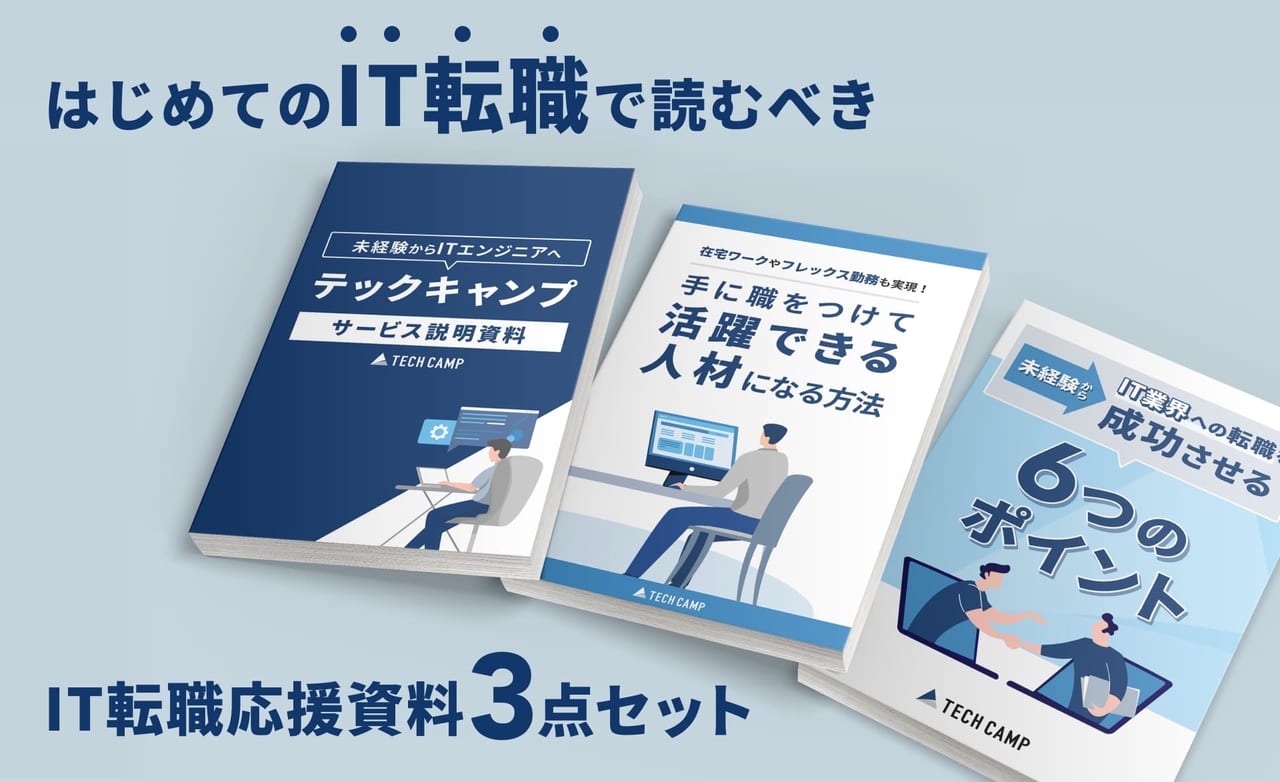
「そろそろ転職したいけれど、失敗はしたくない……」そんな方へ、テックキャンプでは読むだけでIT転職が有利になる限定資料を無料プレゼント中!
例えばこのような疑問はありませんか。
・未経験OKの求人へ応募するのは危ない?
・IT業界転職における“35歳限界説”は本当?
・手に職をつけて収入を安定させられる職種は?
資料では、転職でよくある疑問について丁寧に解説します。IT業界だけでなく、転職を考えている全ての方におすすめです。
「自分がIT業界に向いているかどうか」など、IT転職に興味がある方は無料カウンセリングにもお気軽にお申し込みください。