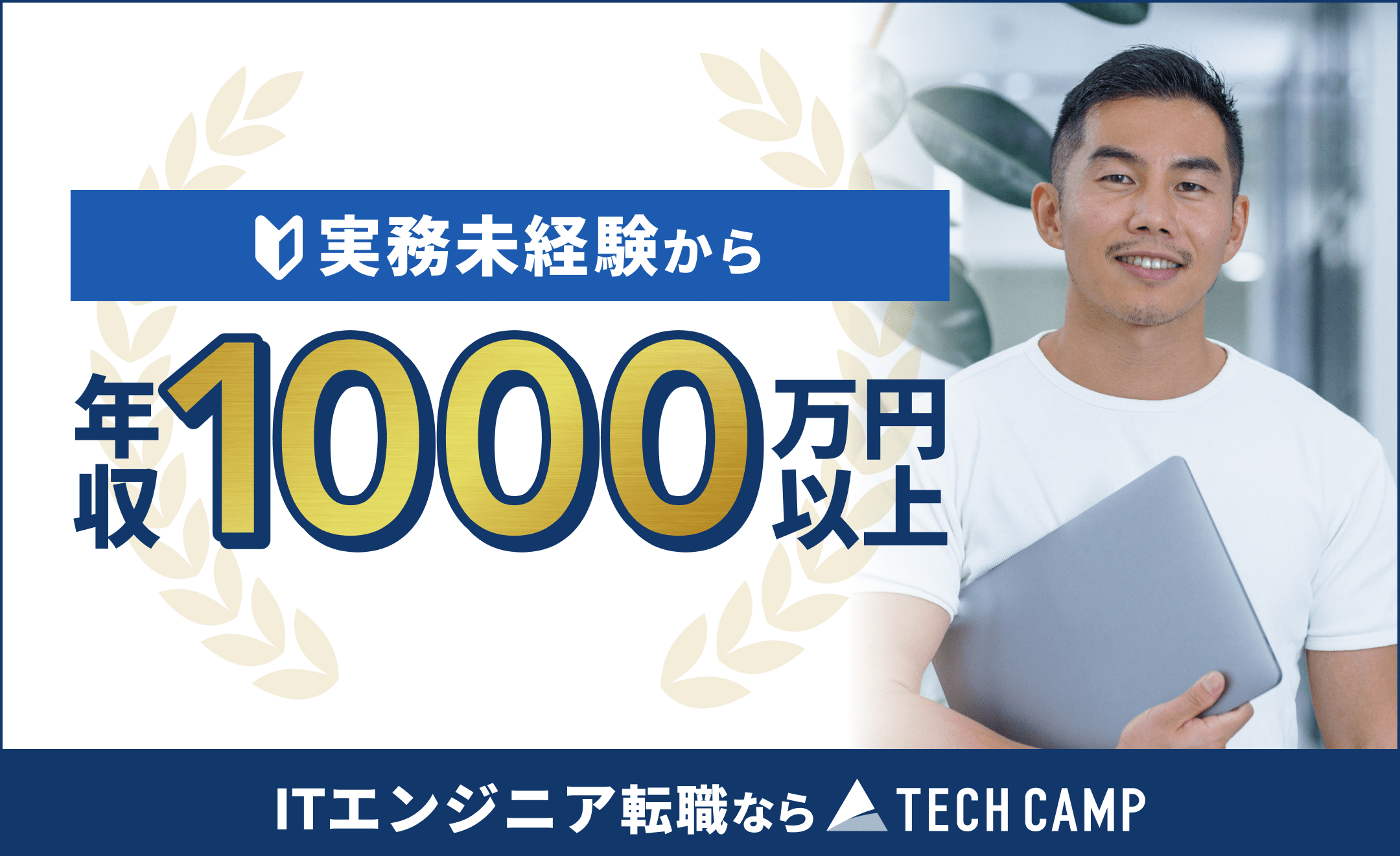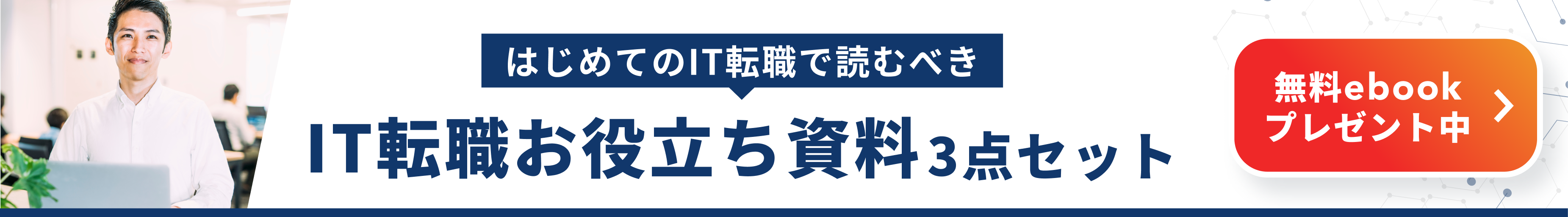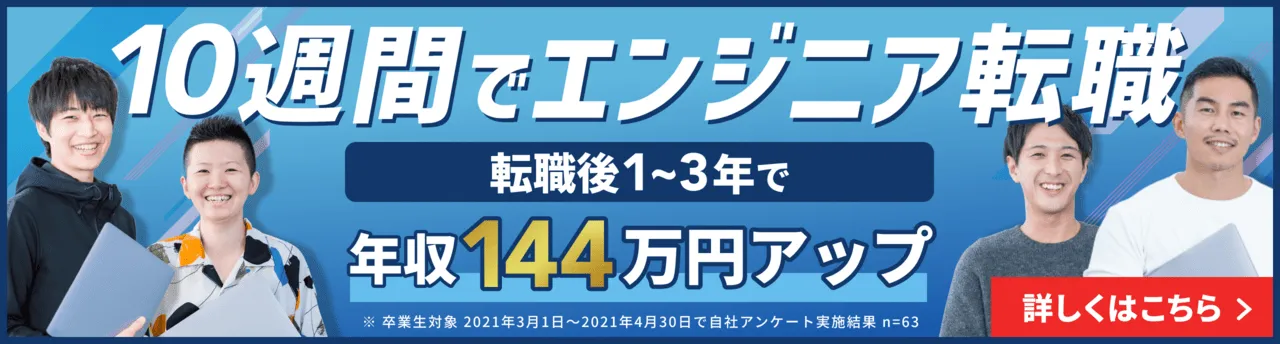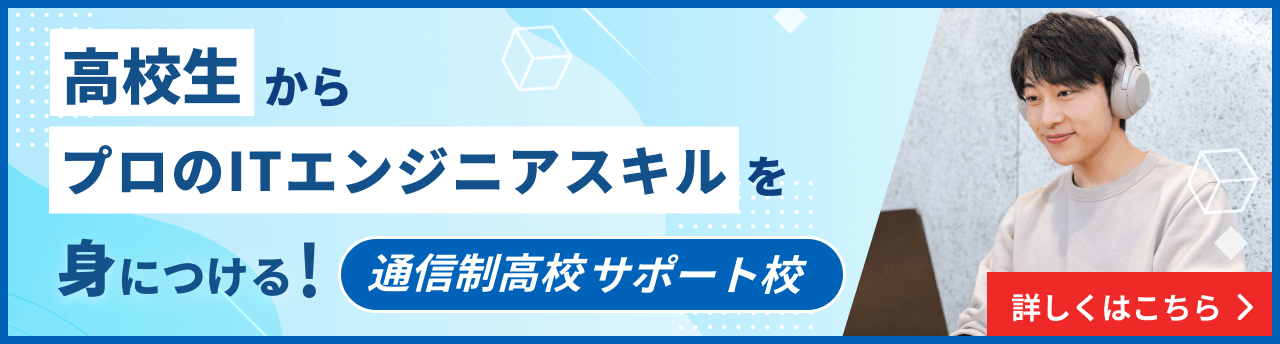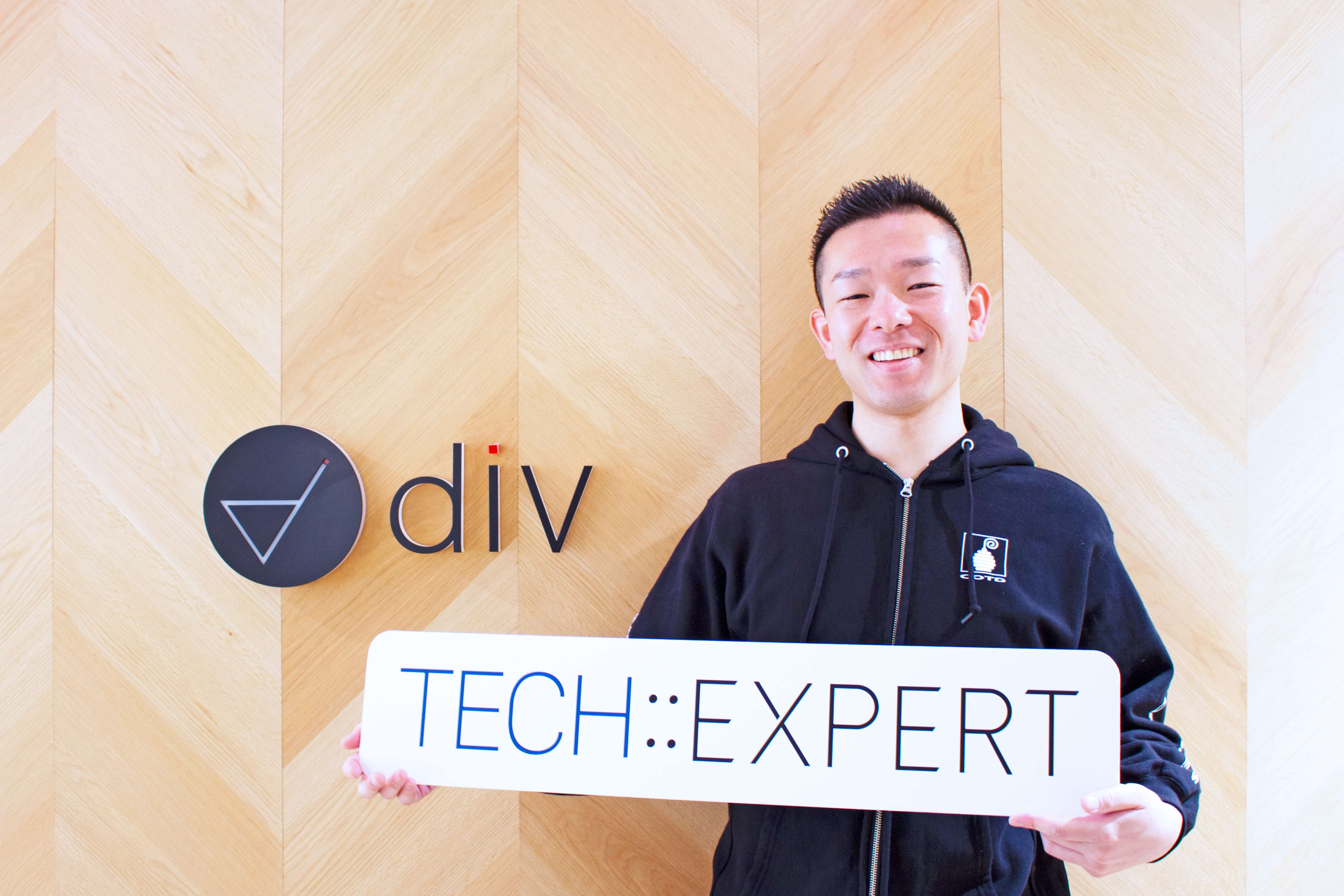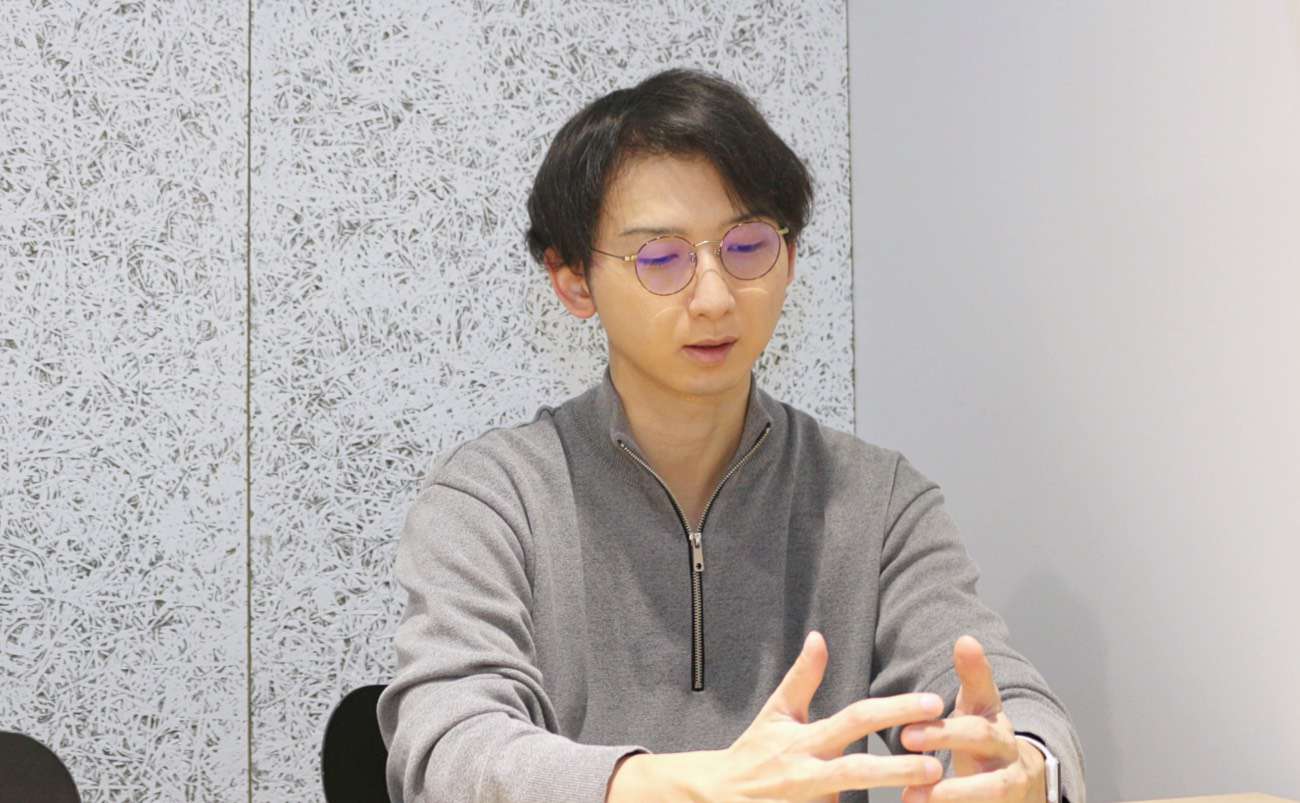- 既存のシステムだけでは成長に限界がある
- 消費者や社会のニーズの変化に対応する
- あらゆる分野で起きるデジタル化に対応する(コロナ対策など)
「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を最近よく聞く」
「しかしDXの意味について聞かれるとよくわからない」
「DXに取り組むべき理由や事例などが知りたい」
あらゆる分野でのデジタル化が進み「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を聞く機会も増えました。テレビやネットで見る機会も多いはずです。
時代の流れに遅れないためにも、この記事ではDX(デジタルトランスフォーメーション)の意味や具体例を紹介します。また既存のビジネスモデルをデジタル化したい企業担当者に向けて、DXを推進する基本的な流れも簡単に解説。
DXの基本を押さえたい人や「自分の勤める会社でデジタル化を進めたいけど、どうすればいいのだろう」という人はぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義


DXとは「デジタルトランスフォーメーション(Desital Transformation)」という意味の言葉です。
英語圏ではTransを省略して「X」と表記することが多いため、頭文字をとってDXと呼ばれます。
直訳すると「デジタル変化」で、ITの浸透によって人間の生活があらゆる面で良い方向に変化することを意味します。
スウェーデンのウメオ大学教授エリック・ストルターマン氏が2004年に提唱しました。以下では、DXの概要について解説していきましょう。
- ビジネスにおけるDX(経済産業省の定義)
- ビジネスリーダーの87%が過去3年以内にDXを検討/施行/実践
ビジネスにおけるDX(経済産業省の定義)
2018年に経済産業省がDXを以下のように定義(DX推進ガイドライン)しています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのも のや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」
言い換えると、顧客や社会のニーズに合わせて自社の事業や既存のシステムをデジタル化。競合企業に対して優位に立つことをDXと定義しているのです。
この記事もオススメ



DX推進指標とは
経済産業省によって定められた、DXを進める上で必要な点をまとめた要項を「DX推進指標」と呼びます。
「DX推進のための経営のあり方、仕組みに関する指標」と「DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築に関する指標」の2つに分かれており、DXを推進するにあたっての現状や、経営者やデジタル担当者が解決しなければならない課題などが35項に渡ってまとめられています。
ビジネスリーダーの87%が過去3年以内にDXを検討/施行/実践
2019年2月に富士通が行った調査によると、世界9ヶ国900人のビジネスリーダーの87%が「過去3年以内にDXを検討/施工/実施した」という結果が出ています。
つまり、多くの企業がすでにDXを推進しているということです。競合企業に対して優位に立つためにはデジタル化が必須と言い換えてもいいでしょう。
特に金融、運輸業はデジタル化が進んでおり、金融業では47%、運輸業では45%がDXを実践し成果があったという結果が出ています。
【無料】ChatGPTの使い方をマンツーマンで教えます
・ChatGPTの基本的な使い方がわかる
・AIの仕組みがわかる
・AIをどうやって活用すれば良いかがわかる お申し込みは1日5組限定です。
今すぐお申し込みください。 ChatGPTレッスンを確認する▼
https://tech-camp.in/lps/expert/chatgpt_lesson
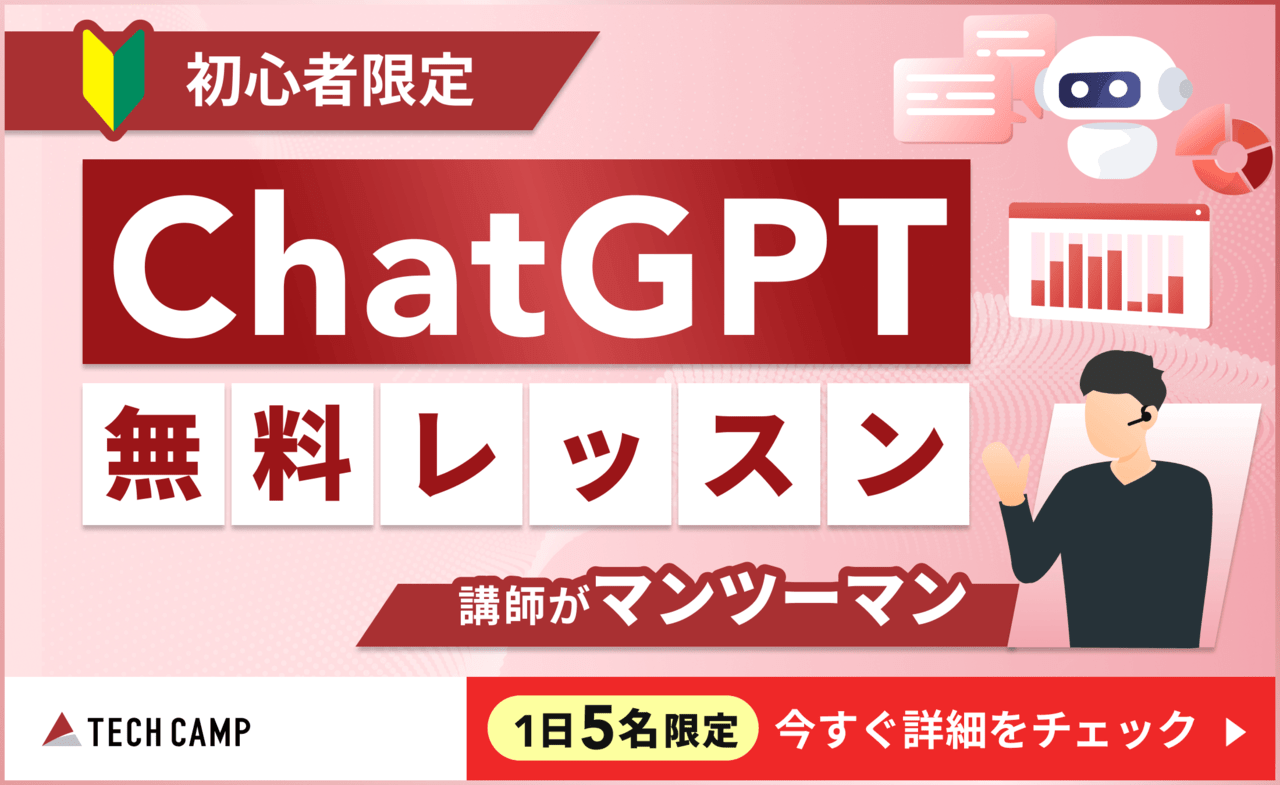
企業がDXに取り組むべき理由


現在、DXは多くの企業にとって必須で取り組むべきことと言っても過言ではありません。ではなぜ、企業にDXが必要なのでしょうか。大きく分けて3つの理由があります。
それぞれ解説します。
既存のシステムだけでは成長に限界がある
使い慣れたシステムの方が業務もしやすいのは確かですが、企業の将来的な成長を考えるとそう遠くない未来に限界を迎える可能性が高いです。
維持・拡大にコストがかかってしまうだけでなく、後述するデジタル化に対応できないというケースが多々あります。
クラウドなどは低コストで導入できる上、古いシステムを凌駕する様々な機能を備えている場合があるため、企業の成長につなげやすいでしょう。
消費者や社会のニーズの変化に対応する
消費者の消費活動や社会のニーズは常に変化しています。
例えば、最近はサブスク型のサービスのニーズが高まっており、特に「Netflix」や「U-NEXT」といったストリーミングサービスのユーザー増加は著しいです。レンタルDVDなどに取って代わるサービスとなっています。
こうしたニーズの変化に対応するためには、既存のビジネスモデルのデジタル化が欠かせません。
この記事もオススメ



あらゆる分野で起きるデジタル化に対応する(コロナ対策など)
昨今、IT業界以外のあらゆる分野でデジタル化が進んでいます。こうした時代の流れに対応できなければ、競合企業に遅れをとってしまう可能性があるのです。
特に近年は新型コロナウイルス対策にデジタル化を進める企業が増加中。ZoomやTeams、Skypeといったアプリケーションを使ったテレワークもDXの一環です。
新型コロナウイルスの拡大をきっかけに、デジタル化はほとんどの企業で必須になっていると言い換えてもいいでしょう。

DX(デジタルトランスフォーメーション)を支える技術
DXを支える技術として、主に以下のものが挙げられます。
- モバイル端末
- クラウドコンピューティング
- AI(人工知能)
- IoT(Internet of Things)
- 5G(第5世代移動通信システム)
- VR/AR(仮想現実/拡張現実)
- サイバーセキュリティ
- HMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)
- 量子コンピューティング
- 情報処理基盤
- DXの推進を考えるならば、自社の事業に上記の技術を組み込めないか検討することから始めるのがよいでしょう。
それぞれの技術について概要を紹介します。
モバイル端末


近年、モバイル(スマートフォンなど)でも高度なITシステムを使うことが可能です。
メールの送受信はもちろん、画像・動画の編集や文書の作成などもできます。デスクトップ型のパソコンだけでしかシステムを使えない時代から変化しつつあるのです。
モバイルを活用することで自宅での作業や外出先でのサービス提供が可能になり、デジタル化の推進につながります。
クラウドコンピューティング
デジタル化の基盤となるのは大量のデータです。そのデータを分析することでどのような改革をするべきか方針を決めます。
これらのデータをオンプレミス型(自社のサーバにソフトをインストールして使用する形)で収集・保存しておくのには限界があります。
そこで登場したのが「クラウドコンピューティング」という技術。クラウドを利用することで、増加するデータの保存場所として利用可能です。
メンテナンスもクラウドの運営業者に任せられるため、結果的に維持費用のカットにもつなげられるでしょう。
この記事もオススメ



AI(人工知能)
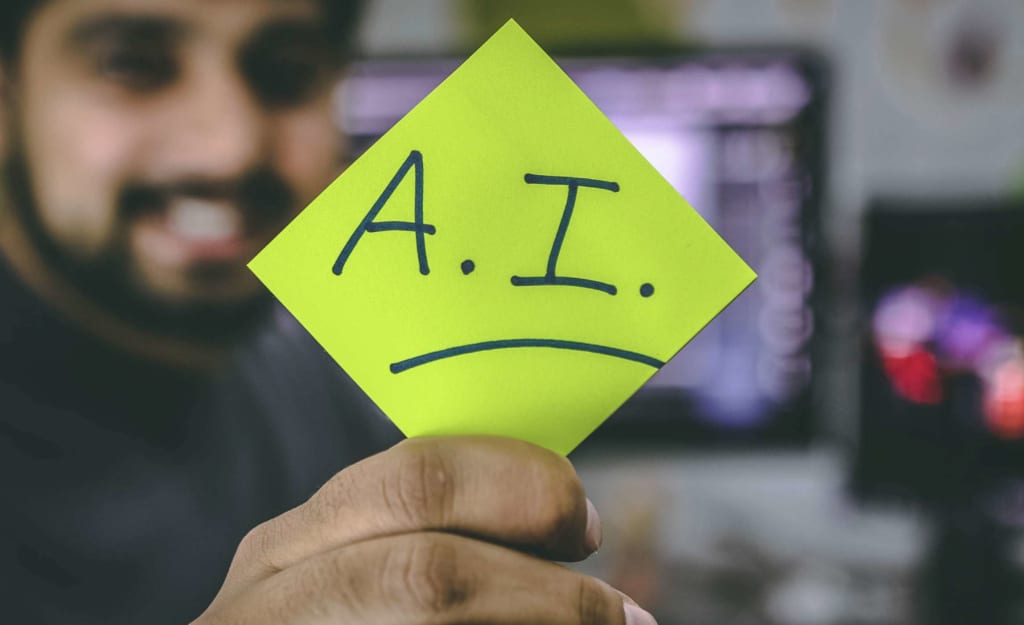
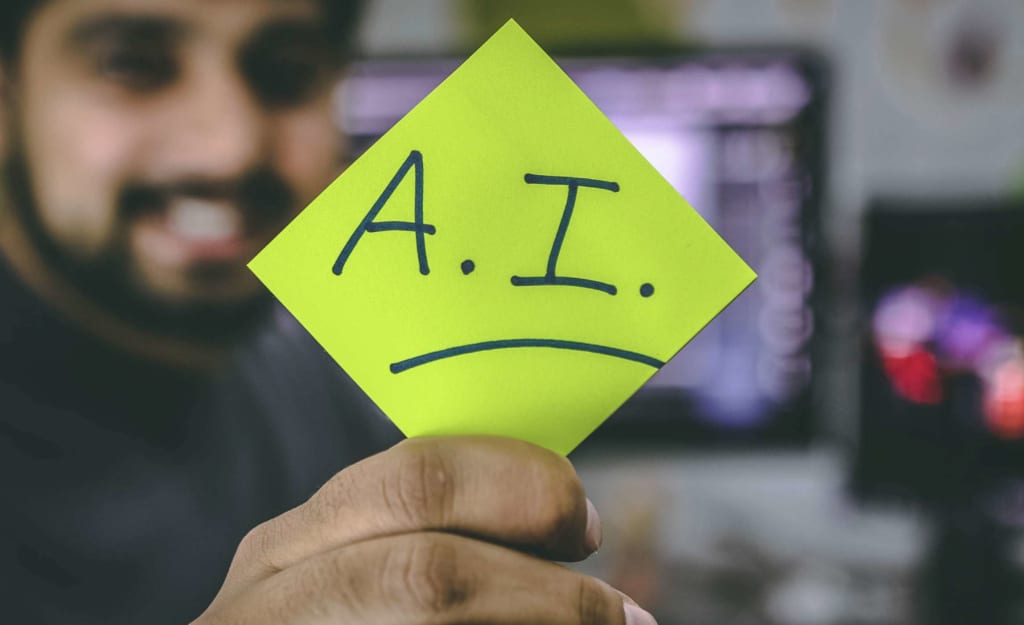
集めた大量のデータ全てを人力で分析することはまず不可能。そこで役立つのがAI(人工知能)です。
AI(人工知能)は大量のデータ(ビッグデータ)の分析を得意としており、人の力では分析に時間がかかるデータ量でも一瞬で処理が可能です。
集めたデータを活用するために、AI(人工知能)の導入も併せて行えると理想的です。
この記事もオススメ



IoT(Internet of Things)
IoTとは「モノのインターネット化(Internet of Things)」という意味の言葉です。従来の「モノ」をインターネットにつないだサービス・商品が該当します。
例えば、Googleが開発した「Google Home」は、デバイスがインターネットとつながっており、言葉で指示した作業を実行してくれます。
近年は自動運転車の開発も進んでおり、これも自動車というモノをインターネットにつないだIoTの代表的な事例です。
IoTによって既存のビジネスモデルが大幅に発展する可能性があります。
またインターネットに接続することで、さらなるデータ収集も可能。集めたデータを分析すればサービス・商品の品質向上にもつなげられるのです。
5G(第5世代移動通信システム)
クラウドやIoTはネットワークに接続してこそ活用できる技術。これらを実現するために期待されているのが第5世代移動通信システム、通称「5G」です。
高速での通信し、複数の端末を接続が可能。遅延も少ないネットワークである5Gの発展が、今後のDX推進の基盤として注目を集めています。
本記事を執筆している2024年3月時点では、5Gの整備が全国的に進んでいる印象です。ソフトバンクのサービスエリアマップを見ても、だいぶ進んでいます。
将来的には当たり前に使えるネットワークになっていることでしょう。
この記事もオススメ



VR/AR(仮想現実/拡張現実)


VRとは仮想現実を意味する言葉です。専用のゴーグルをつけることで普通では入り込めない世界を体験することが可能。
身近なところではゲームに活用されることが多く、テレビ画面でを見るのではなく自分自身がゲームの世界に入り込んだ感覚を味わえます。
またARとは拡張現実のことです。現実の世界に仮想のオブジェクトを出現させる技術を意味します。
例えば、Googleで好きな動物の名前を検索してみてください。すると動物のオブジェクト現実に出現させ、スマホを通して見ることができます。
ゲームやイベントなどで使用されることの多いVR/ARは、エンタメ業界を進歩させる技術となりうるでしょう。
サイバーセキュリティ
デジタル化にはリスクも存在します。例えば、インターネットを利用した犯罪(サイバー犯罪)に巻き込まれる可能性が高まるという点です。
企業の顧客データの流出やサービス機能の障害といった事例が散見されます。
このようなリスクを回避できるハイレベルなサイバーセキュリティの導入も欠かせません。
この記事もオススメ



HMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)
HMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)とは、キーボードやマウスといった、人間と機械の接点となるモノを意味します。
HMIの具体例として、音声や視覚など五感を利用したインターフェースがあります。
五感を使ったインターフェースによって機械を操作する方法の幅も広がっており、IoTに応用されている技術でもあります。
量子コンピューティング
従来のコンピュータは0と1の組み合わせによって計算を実行していました。
量子コンピューティングはそれと異なる計算方法をとっており「量子ビット」という重ね合わせが可能な単位を使って計算します。
これにより従来のコンピュータよりも高速での計算が可能。瞬時に正確な計算結果を弾き出せるようになりました。量子コンピューティングの普及は、IoTの発展にも役立っています。
情報処理基盤
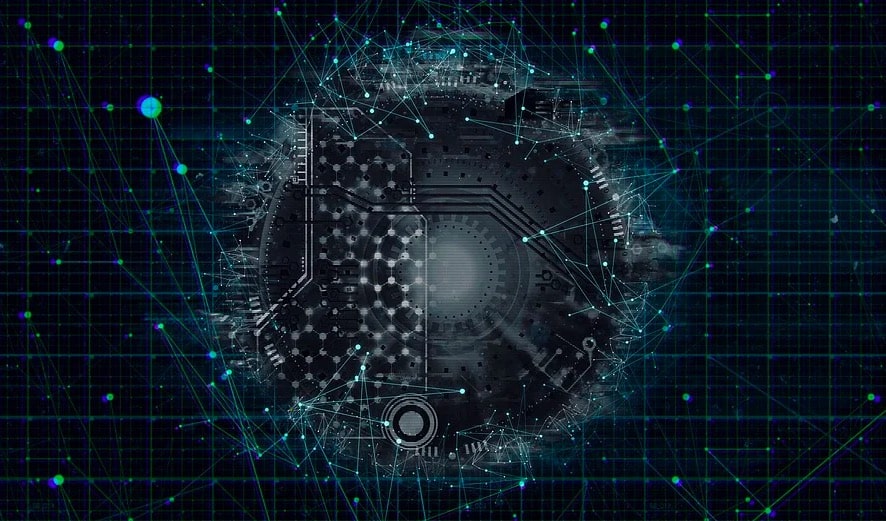
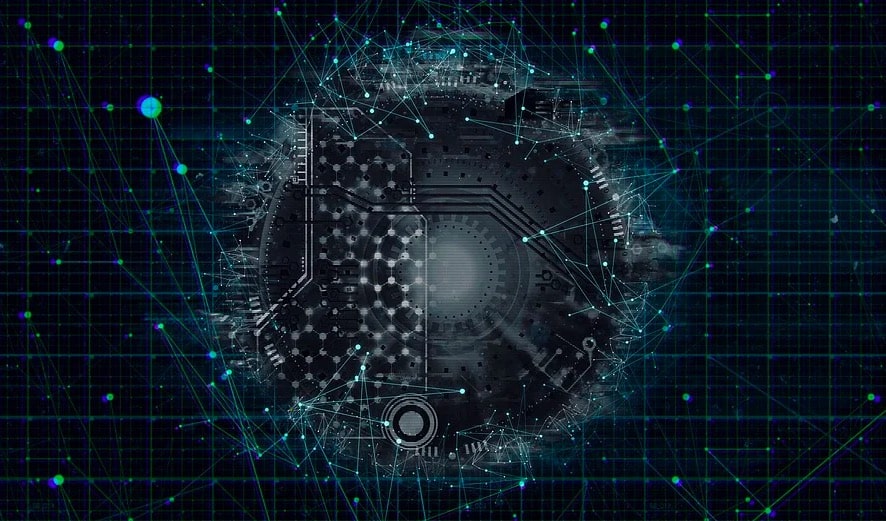
ここまでに紹介した技術を実現するためには、情報処理基盤の見直しも必要です。
データベースやネットワークといったインフラの整備を適宜行うようにしましょう。
DX(デジタルトランフォーメーション)の事例
実際にDXの事例としてどのようなものがあるのでしょうか。5社の事例を紹介します。
- 株式会社マロニエゲート
- 株式会社資生堂
- Amazon.com, Inc
- 株式会社メルカリ
- LINE株式会社
会員カードのアプリ化による顧客情報の収集(株式会社マロニエゲート)
マロニエゲートは東京都の銀座にある商業施設です。
これまで使っていた会員カードをアプリ化することで、顧客データの収集(来館する時間帯や購入額など)を可能にしました。
また。最後に来館してから時間が空いている顧客に対してアプリを使った通知を送ることで、来館を促すことも可能になりました。
これにより、ダイレクトメッセージを送るためにかかっていた費用な削減を実現しました。
IoTで個人の肌にあったケアを実現(株式会社資生堂)
化粧品などを販売する株式会社資生堂は、「Optune(オプチューン)」というIoTシステムを開発しました。
「Optune(オプチューン)」は、顧客の肌の情報をスマートフォンアプリで読み取り、最適なケア方法を提案するシステムです。
「Optune(オプチューン)」によってサブスクリプション型のサービスも実現しました。
この記事もオススメ



「行動」「知識」「モノ」をデジタル化(Amazon.com, Inc)
ECサイトAmazonは「行動」「知識」「モノ」の3つをデジタル化しました。
従来は店舗に足を運んで購入する必要がある商品を、どこにいても購入できるという「行動」をデジタル化。
また、これまで顧客の希望する商品(潜在的なニーズ)を掘り出すのは、商品情報を把握している店員の役割でした。しかし、AI(人工知能)を使って過去の購入履歴から割り出すことが可能に。「知識」や「経験」をデジタル化しました。
さらに本や映像などをデジタル化し、本屋に行く、レンタルDVDを借りるというプロセスを省略。「モノ」のデジタル化にも成功しました。
スマホで出品、購入が可能なフリマアプリを実現(株式会社メルカリ)
フリーマーケットアプリを運営する「株式会社メルカリ」は、インターネットでのオークション形式を大きく変えました。
これまではパソコンを使っての出品や購入が当たり前でしたが、全てをスマートフォンアプリで完結可能に。より気軽にオークションを利用できるようになりました。
また相手の住所・氏名がわからなくても発送できる「匿名配送」、宛名がなくても発送できる「らくらくメルカリ便」、ポイントで購入可能な「メルペイ」など、より便利に利用できるサービスをリリースしています。
AI(人工知能)による信用スコアの導入(LINE株式会社)
メッセージアプリ「LINE」を提供するLINE株式会社は、2018年に個人の信用スコアを数値化する「LINE Score」を開発しました。
個人スコアとは、クレジットカードの発行などに必要な個人の信用情報をAI(人工知能)によって数値化したものです。
過去の支払い実績や通販の購入履歴といったデータから数値を導きだします。人間の主観が入らない客観的な信用の数値化が可能です。
「LINE Score」では、LINE Payやメッセージのやりとり、LINEニュースの閲覧履歴から信用スコアを算出する方法を取っています。
算出したスコアは個人への融資サービスや決済サービスなどに利用されています。
企業におけるDX(デジタルトランフォーメーション)の推進方法


実際にDXを自社で進めていくにはどのようなプロセスを踏めばよいのでしょうか。
ここからがDX推進の方法について解説します。
- 経営層がデジタル改革に対する理解を深める
- 経営戦略を作成する
- DX(デジタルトランフォーメーション)実現に向けた体制を作る
- 現状のIT資産を分析する
- 既存事業をデジタル化により効率化・拡張する
- 既存事業をデジタル化により新規事業に転換する
経営層がデジタル改革に対する理解を深める
経営層がDXに関する知識が浅い、または理解がない場合、スムーズなデジタル化ができない可能性が高いです。
そのため「ビジネスの指針を決める経営層がデジタル化に対して理解を深める」という段階が欠かせません。
理解がないままDXを進めようとしても曖昧な指示しかできず、実際に現場で動く社員たちが混乱してしまうケースが予想されます。
この記事もオススメ



経営戦略を作成する
次の段階としてDXによって自社にどのようなメリットがあるのか、また業界の変化にどう対応するかを示すべく、経営戦略を作成します。
その戦略を作成するのは経営層である場合が多いでしょう。しかし、経営層の理解が浅いままだと戦略も曖昧なものになりがち。
社内のIT担当者は先に説明したDXへの理解を経営層に深めてもらうべく、わかりやすい資料を作成するべきです。その上で、経営戦略を練る段階に進みましょう。
DX(デジタルトランフォーメーション)実現に向けた体制を作る
作成した経営戦略に基づき、DXの実現に向けた社内体制を作ります。
社長、経営層が直接指示を出せる部門にしたり、デジタル化を専門に対応する部署を新設するなどが具体的な方法となります。
体制を整えたばかりの頃は全てのプランを完璧にこなすことは難しいでしょう。
トライ&エラーを繰り返しながら改善点を洗い出し、必要に応じて体制を作り変えていくという姿勢が重要です。
デジタル・IT化は非常に速いスピードで進んでいきます。DXに対応する部署は可能な限り素早く動ける体制にしておくのがおすすめです。
現状のIT資産を分析する
自社のシステムやネットワークなどのIT資産を分析しましょう。
活用できる部分はそのまま活かしたり、不要な部分は処分・廃棄したりします。特に重視したいのは老朽化したシステムや、ある特定の担当者しか扱えない(ブラックボックス化)システムがないかを洗い出すことです。
後述しますが、老朽化・ブラックボックス化したシステムはDXの推進を大きく妨げる場合があります。そのようなシステムがあった場合は他のもので代替できないか、使用方法をマニュアル化して社内で共有できないかを確認してください。
また、システムを社内で一元化できているかどうかも重要な部分です。
部門・部署ごとに異なるシステムを使っている場合、全社的なDX推進が難航しがち。このようなケースでも代替可能なシステムがないかを考えるべきでしょう。
既存事業をデジタル化により効率化・拡張する
実際にDXに取りかかる前段階として、既存事業をデジタル化によって効率化・拡張を試みます。
社員の労働環境や売上・費用などあらゆる面を評価し、戦略に沿った効果が現れたら次の段階に移行します。次はデジタル化による新しいビジネスモデルを作成する(DX)の段階です。
この記事もオススメ



既存事業をデジタル化により新規事業に転換する
既存事業を基に、あるいは新規のビジネスモデルをデジタル化によって進めていきます。
ここからも挑戦や失敗を繰り返しながら効果を見つつ、必要に応じた対応をとっていきます。
社内体制の変革や、新しい技術の導入など必要な物事を定期的に見直していきましょう。
DX(デジタルトランフォーメーション)の推進に伴う課題
先述の通り、富士通の調査では世界9ヶ国900人のビジネスリーダーの87%が過去3年以内にDXを検討/試行/実施しているという結果が出ています。
しかし、実際にDXを理解し推進する決定を下している企業はまだまだ少ない状況です。
DX推進には様々な課題があり、妨げになっている場合があります。ここでは、実際にどのような課題があるのか解説します。
- 経営層のデジタル化に対する理解不足
- IT人材の枯渇・教育環境の不足
- 汎用的なシステム導入の難航
- 多重下請け構造によるノウハウ不足
- システムの老朽化(不明瞭なシステム)
経営層のデジタル化に対する理解不足
DX推進を妨げる原因の一端には、経営層のDXに対する理解不足があります。
理解が浅いとDX推進による自社へのメリットが見えず、現状のシステムを刷新する意思決定が難しくなってしまうのです。
企業のIT担当者は経営層をいかに納得させるか、DXを理解してもらうかの工夫が必要です。
IT人材の枯渇・教育環境の不足


将来的に、現在のIT担当者が退職した場合の後継者がいなくなってしまうという課題があります。特に、デジタル部門を少数の人材で運用している企業はこのリスクが高いでしょう。
今は問題なく回っていても、数年後はどうなっているかわかりません。また、そもそもDXに対応可能なIT人材が市場に少ないという問題もあります。
「AI(人工知能)を導入したい」「クラウドでデータを管理したい」と経営者が考えても、それを実行できる人材の確保が難しいのです。
その原因として、IT人材を育てる環境も不足が影響しています。昨今はプログラミングスクールなどが増えてきていますが、IT人材の増加にはつながっていないのが実情です。
汎用的なシステム導入の難航
部門や部署ごとに適用したシステムを構築している企業が多く、会社全体で一斉に新規のシステムを導入できる環境ができていないケースが見受けられます(システムのサイロ化)。
他のシステムとの連携ができず、全社で使える汎用的なシステムの導入が難しいこともDXの課題です。
多重下請け構造によるノウハウ不足
自社でIT人材を確保できないと下請けのSIerに仕事を委託する形になるでしょう。これがIT業界で見られる「多重下請け構造」の原因の一つです。
多重下請け構造により、元請企業にITスキルや開発のノウハウが蓄積しないという現象が起こります。結果、自社のサービスを社内で取り扱うことができないといった状態に陥りがちです。
この記事もオススメ



システムの老朽化(不明瞭なシステム)


既存のシステムが老朽化しており、刷新が難しいこともDX推進の課題です。
またシステムが複雑化したり、社内共有ができていないことによるブラックボックス化もDXの推進を妨げる要因になっています。
上記のようなシステムを維持するにも、複雑なシステムほど維持には高いレベルの技術者が必要になり、その分のコストもかかります。
老朽化したシステムをそのままにしておくと、2025年以降、年間で最大12兆円の経済的損失が生まれるとのデータもあります(『2025年の崖』と呼ばれます)。
システムの刷新はコストカットの面においても非常に重要な部分と言えるのです。
これからDXに対応するなら「divx」がおすすめ
自社でDXを推進するのが難しい場合、専門のコンサルティング企業を利用するという方法があります。その際におすすめしたいのが「divx」です。
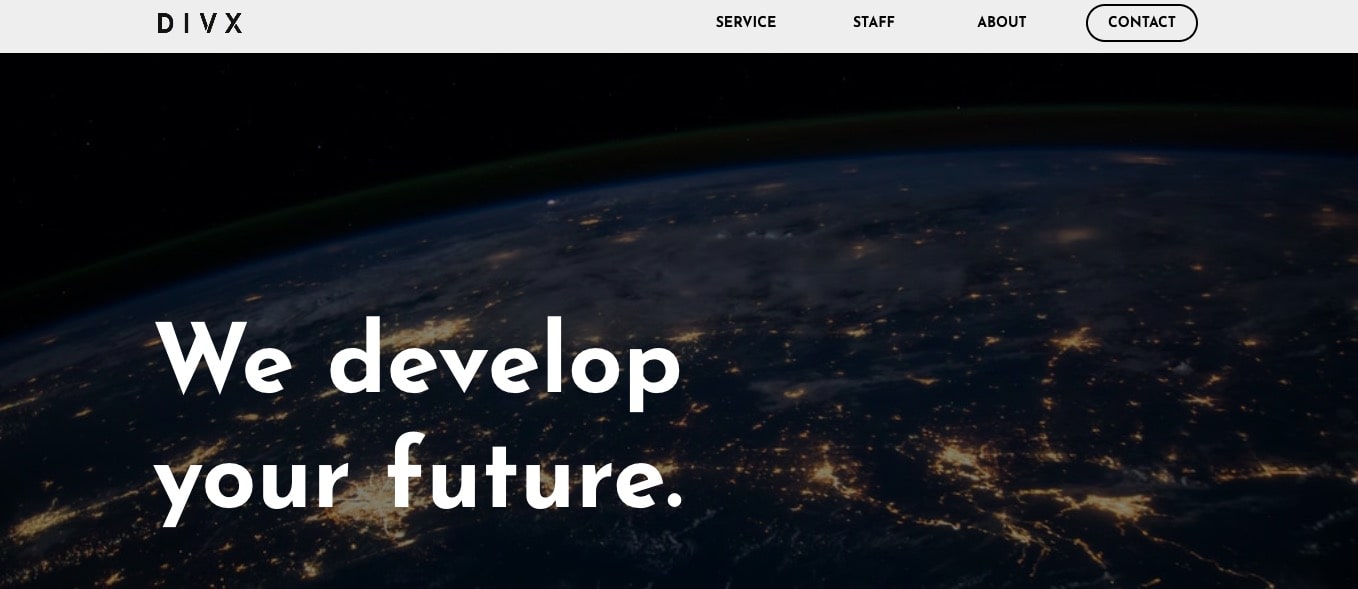
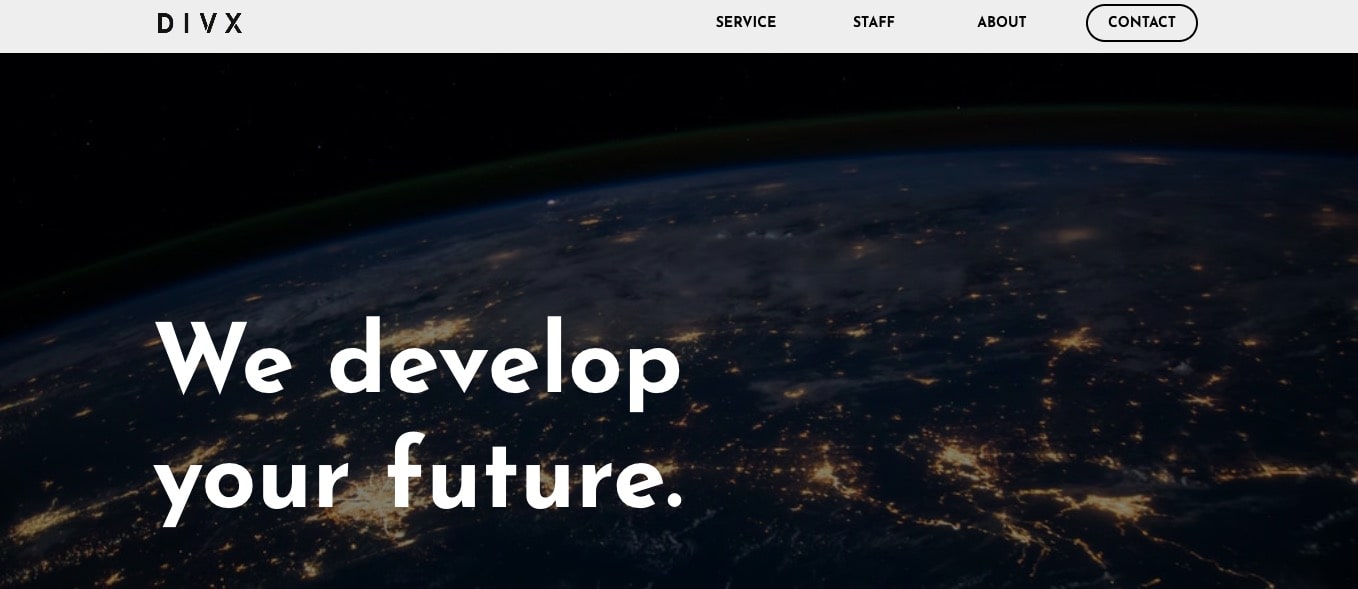
出典元:divx
divxは、各企業のニーズに沿ったIT/DXのコンサルティングからシステム開発、サービスの運用・改善までを一気通貫で対応。これからDXを進めたい企業をサポートします。
詳細は下記からご覧ください。
▶️株式会社divx(ディブエックス)|コンサルからサービス運用までDXを支援
はじめての転職、何から始めればいいか分からないなら
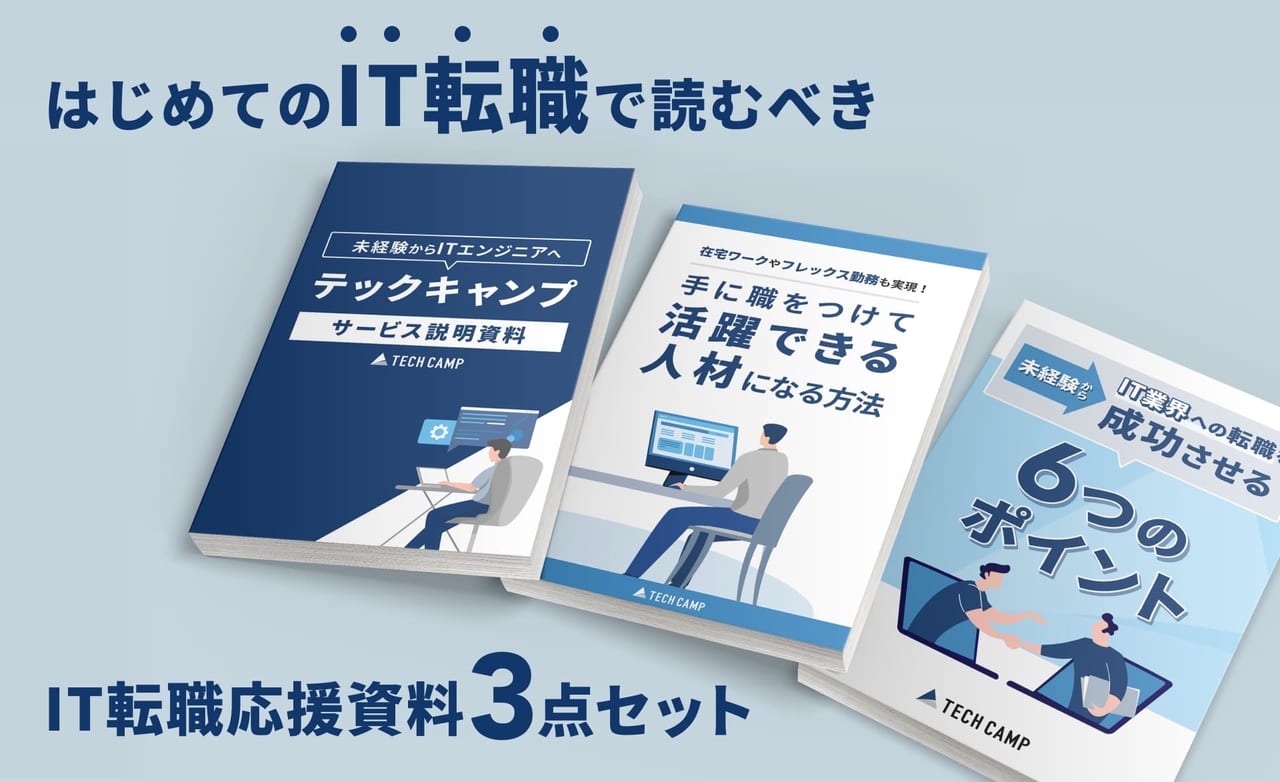
「そろそろ転職したいけれど、失敗はしたくない……」そんな方へ、テックキャンプでは読むだけでIT転職が有利になる限定資料を無料プレゼント中!
例えばこのような疑問はありませんか。
・未経験OKの求人へ応募するのは危ない?
・IT業界転職における“35歳限界説”は本当?
・手に職をつけて収入を安定させられる職種は?
資料では、転職でよくある疑問について丁寧に解説します。IT業界だけでなく、転職を考えている全ての方におすすめです。
「自分がIT業界に向いているかどうか」など、IT転職に興味がある方は無料カウンセリングにもお気軽にお申し込みください。