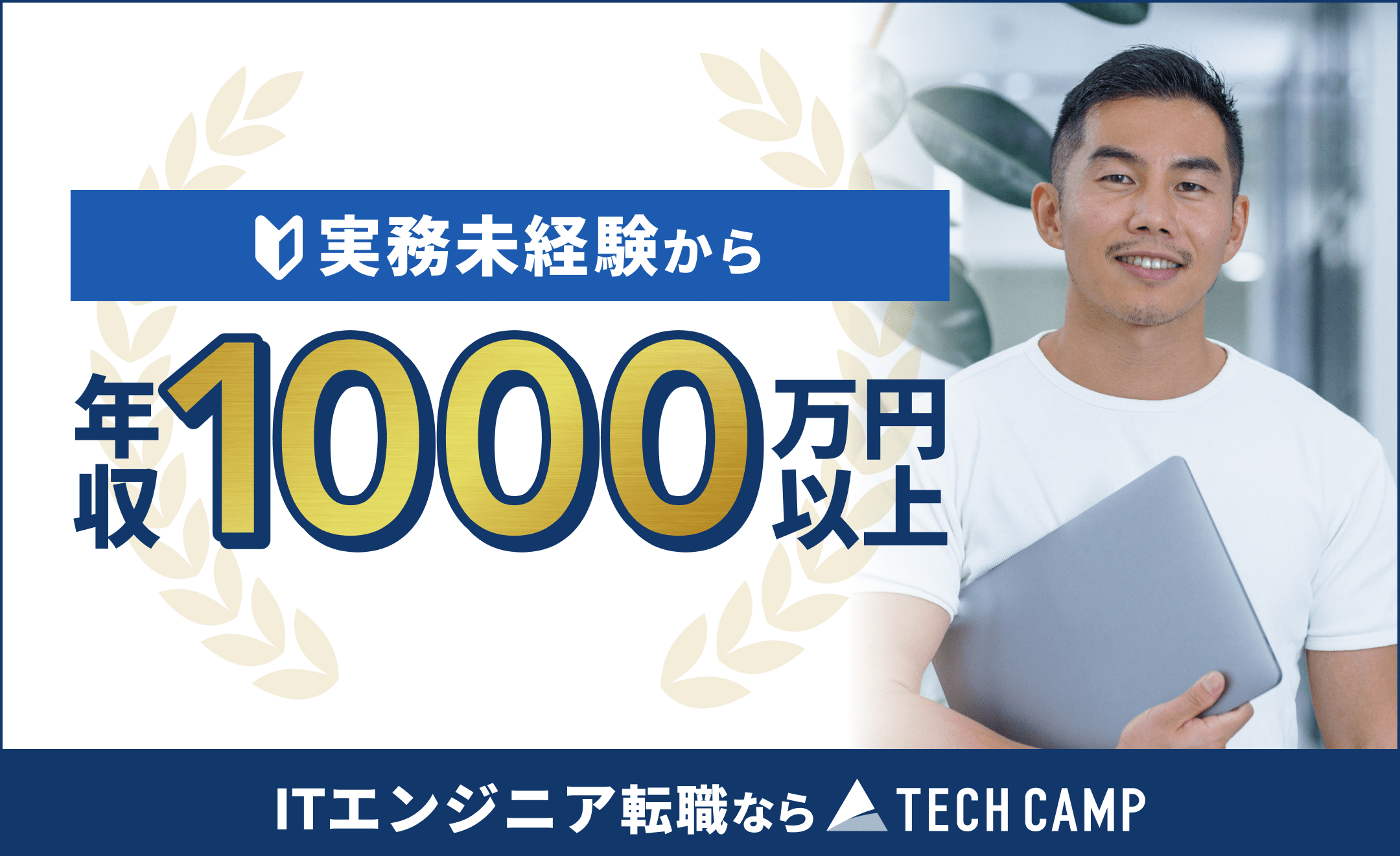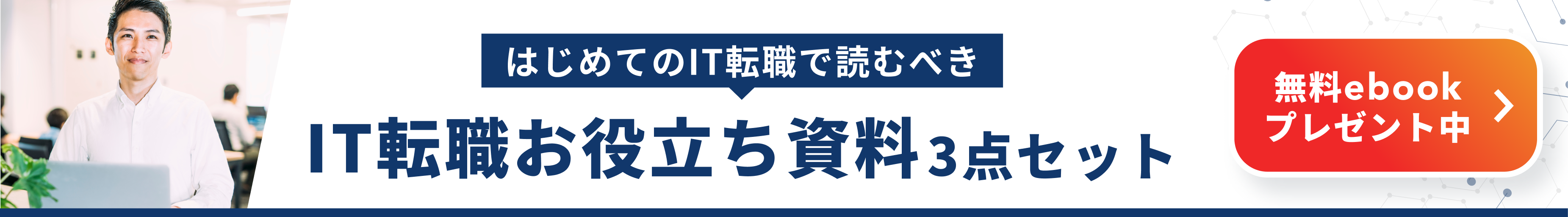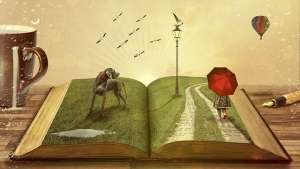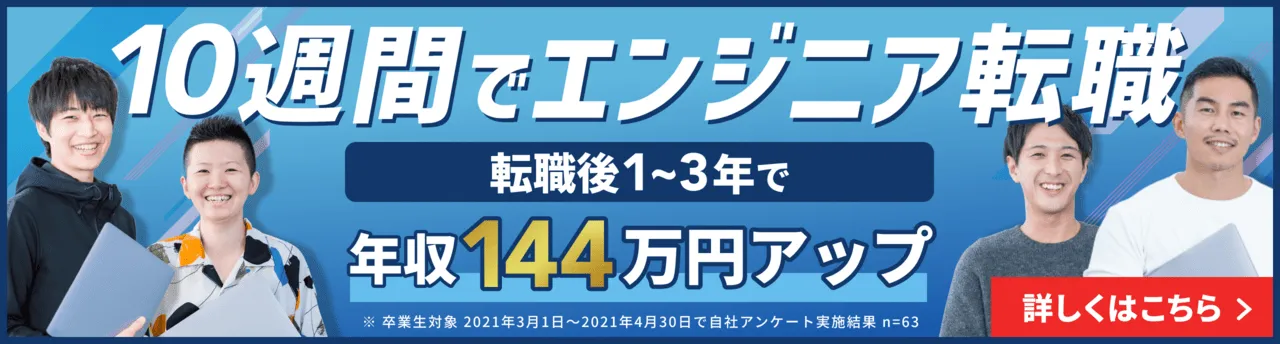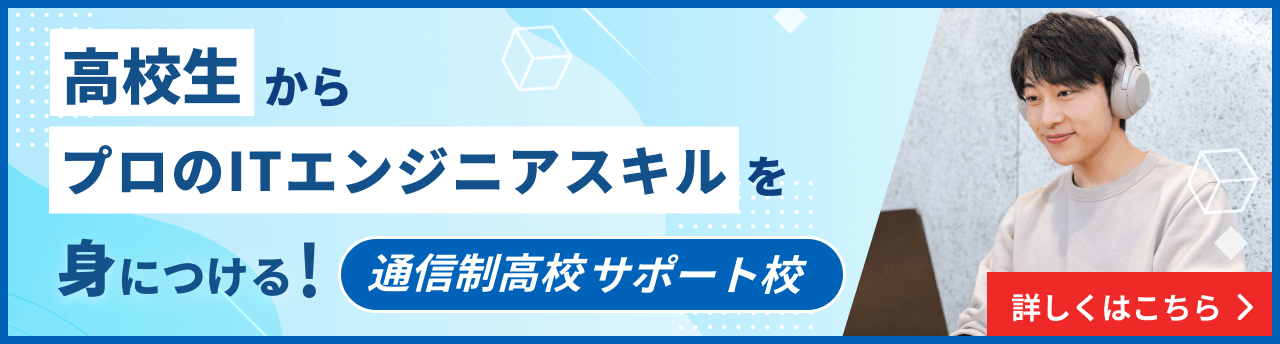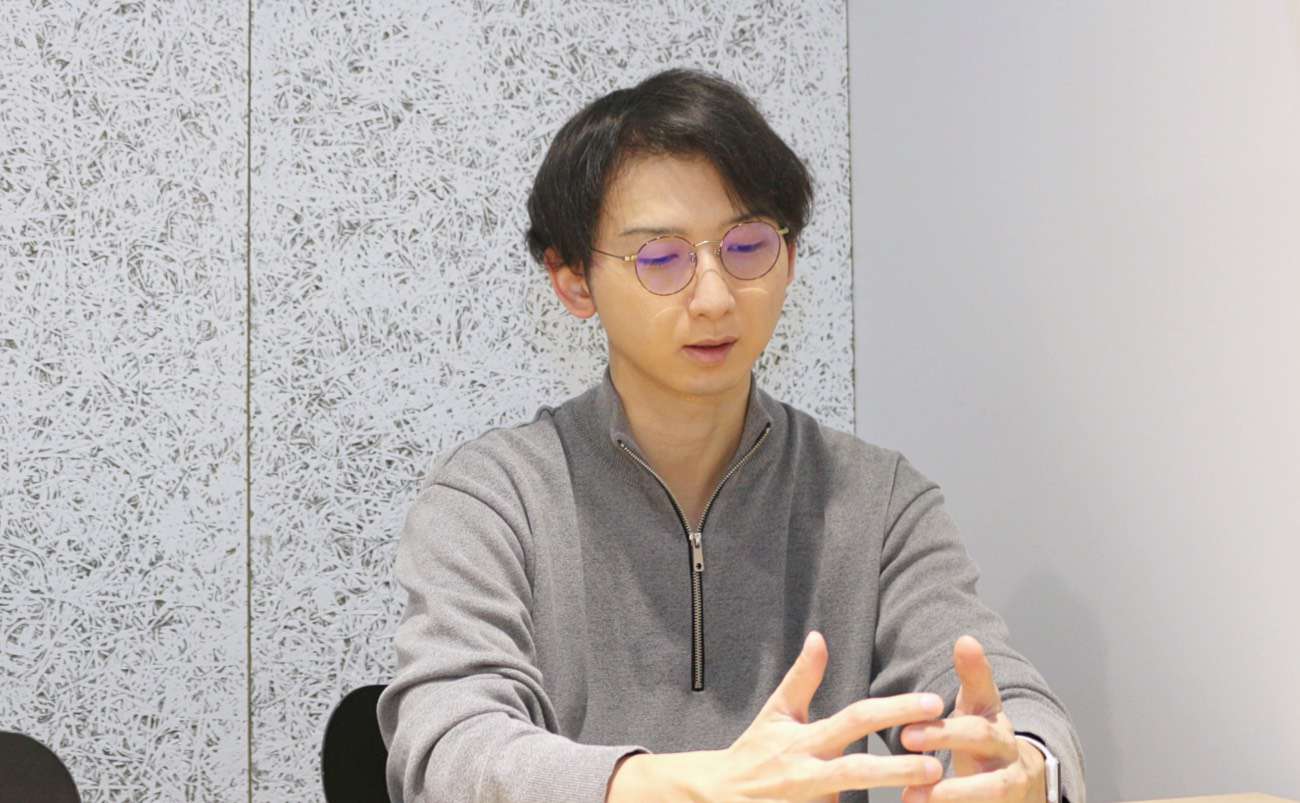私たちは、インターネットのサイトを閲覧するときも、動画を見るときも、スマホアプリを使うときも、いつもネットワークを利用しています。
私生活やビジネスで活用するスマホやパソコンは、ネットワーク無しには成り立ちません。
そして今後は、家電や自動車、仕事で使うさまざまな機器もネットワークに繋がってさらに利便性が向上していくでしょう。
そこで本記事では、そもそもネットワークとは何なのか、その基礎知識や構成要素について分かりやすく解説します。
また、ネットワークの仕組みの基礎であるTCP/IPや、OSI参照モデルについても解説。ネットワークの基礎を理解したい方は、ぜひ参考にしてください。
この記事は現役エンジニアによって監修済みです。
この記事の目次

ネットワークの基礎知識

まずは、ネットワークとは何なのか、その基礎知識から確認していきましょう。
- ネットワークとは人やモノを網のようにつなげたもの
- ITのネットワークとは複数のコンピュータを接続する技術
- ネットワークの主な用途例
ネットワークとは人やモノを網のようにつなげたもの
ネットワークとは英語で書くと「network」で、「網」を意味する単語です。
人やモノが網のようにつながっている様子をイメージすると分かりやすいでしょう。このつながりが増えていくことで、網目状にネットワークは広がっていきます。
例えば、自社の営業担当者と他社の営業担当者のつながりや、企業同士のつながりも、ビジネス上のネットワークだといえます。
また、ネットワークと聞くとイメージする人も多いインターネットは、世界中のコンピュータがWebを活用してつながったものです。
この記事もオススメ

ITのネットワークとは複数のコンピュータを接続する技術
IT業界で使われるネットワークは「コンピュータ・ネットワーク」といい、複数のコンピュータをつなげた技術を指す言葉。
例えば、自宅からスマホを使ってYouTubeなどで動画を視聴するときも、スマホとインターネットが繋がるネットワーク技術が使われているのです。
そして、YouTubeに投稿された動画は世界中の人が閲覧できるようになっています。これは世界中がネットワークという網でつながっているからです。
もし、地球上のITのネットワークが目に見えたとすれば、地球には「網」のような模様が映し出されるでしょう。
ネットワークの主な用途例
ネットワークにはさまざまな用途があります。以下は、私たちにとって身近なネットワークの用途です。
- Eメール
- Webサイト
- ECサイトでのショッピング
- SNS
- 動画視聴
- LIVE配信
- オンラインゲーム
- 各種クラウドサービス
- IP電話
- スマホ決済
このほかにも、ネットワークは官公庁・学校・病院・金融・物流など、あらゆる業界に浸透しています。ネットワークの浸透によって、私たちは生活をより便利になりました。
しかしそれと同時に、ネット依存や障害発生時の影響の大きさなど、ネットワーク社会ならではのリスクが発生しているのも現実です。
この記事もオススメ



ネットワークの仕組み


ネットワークの基礎知識が分かったら、続いてはネットワークがどのようにつながるのかを、以下の流れで見ていきましょう。
- プロトコルに従ってデータをやりとりする
- 「TCP/IP」が主流なプロトコル
- 階層ごとの通信機能を定義する「OSI参照モデル」
プロトコルに従ってデータをやりとりする
ネットワークは、コンピュータ同士が相互接続するための規則通りに通信をすることでつながります。
この相互接続するための手順を定めた規則を「プロトコル」といい、ネットワークはプロトコルを基礎として動いているのです。
プロトコルには大きく分けて、以下のような種類があります。
- TCP/IP
- IPX/SPX
- AppleTalk
これらはすべて、コンピュータ同士が通信をするための手順です。
中でも、主に使われているプロトコルが「TCP/IP」で、ネットワークを学習するならば最初に理解しておきたいプロトコルだといえるでしょう。
「TCP/IP」が主流なプロトコル
TCP/IPは、インターネットに接続する際の主流なプロトコル。
コンピュータがネットワーク接続を行うための細かなプロトコルが定められています。
例えば、ブラウザからWebサーバーに接続するための「HTTP」や、データの送信順序などをコントロールする「TCP」、データの送信先を区別するときなどに使われる「IP」などです。
このような複数のプロトコルを組み合わせることで、コンピュータはネットワークに接続され、データのやりとりを実現しています。
階層ごとの通信機能を定義する「OSI参照モデル」
ネットワークを構築するには、どのようなプロトコルを組み合わせて通信をするべきかを設計しなければなりません。
このようなプロトコルの組み合わせを設計するために、プロトコルを階層化したものを「ネットワークアーキテクチャー」といいます。
そして、ネットワークアーキテクチャーを考えるために、国際的な標準規格として用いられるのが「OSI参照モデル」。
この、OSI参照モデルに基づいた通信機能を設計することで、異なる機器でも通信が行えるのです。

OSI参照モデルの階層構造


OSI参照モデルは、プロトコルを以下の7つの階層に分けて、プロトコルの組み合わせを考えやすくしたモデルです。
また、このモデルを覚えることで、コンピュータがネットワークを通じてどのように通信をするのかが理解しやすくなります。
※階層は、第1層を一番下にして、上に積みあがるようにイメージすると分かりやすくなりますので、第7層から記載しています。
- 第7層:アプリケーション層
- 第6層:プレゼンテーション層
- 第5層:セッション層
- 第4層:トランスポート層
- 第3層:ネットワーク層
- 第2層:データリンク層
- 第1層:物理層
それでは、一つずつ見ていきましょう。
アプリケーション層
OSI参照モデルの第7層に該当する「アプリケーション層」とは、アプリケーションが通信をするときに利用するプロトコルをまとめた層です。
例えば、Webアプリケーションでは「HTTP」、メールアプリケーションでは「SMTP」、ファイルを扱うアプリケーションでは「FTP」など、それぞれに必要なプロトコルがあります。
ネットワークエンジニアだけでなく、アプリケーションを利用するユーザーにとっても最も近いプロトコルだといえるでしょう。
プレゼンテーション層
OSI参照モデルの第6層に該当する「プレゼンテーション層」は、コンピュータのデータ形式とネットワーク上で利用するデータ形式を翻訳するためのプロトコルをまとめた層です。
具体的には、コンピュータごとに異なった文字コードやデータの圧縮形式などを、共通のデータ形式に変換する役割を果たします。
プレゼンテーション層のプロトコルを利用することで、異なるコンピュータ同士が通信できるようになるのです。
セッション層
OSI参照モデルの第5層に該当する「セッション層」は、通信開始から終了までの手順のプロトコルをまとめた層です。
例えば、コンピュータAが「通信を開始します」という宣言をすると、コンピュータBが「では通信を開始しましょう」という応答をします。
このやりとりで、ネットワークの通信経路が確立されます。
また、通信の終わりには、コンピュータAが「通信を終了します」という宣言をして、コンピュータBが「了解」という応答を返したところで、通信経路が切断されるというイメージ。
このように、通信の始まりから終わりまでのやりとり方法を定めたものが、セッション層のプロトコルです。
トランスポート層
OSI参照モデルの第4層に該当する「トランスポート層」は、相手にデータを正しく伝えるためのプロトコルをまとめた層です。
例えば、コンピュータAが「あいうえお」というメッセージを送信したにもかかわらず、コンピュータBに「かきくけこ」というメッセージが届いたら困りますよね。
このようなことが起こらないように、絶対に正しいデータを相互にやり取りできるという「信頼性」を確保するのがトランスポート層の役割です。
ネットワーク層
OSI参照モデルの第3層に該当する「ネットワーク層」は、通信の送信元となるコンピュータと、送信先のコンピュータとでやりとりをするためのプロトコルをまとめた層です。
ネットワークに接続されたコンピュータには、それぞれ「IPアドレス」という住所があります。通信では基本的に、このIPアドレス宛にデータ送信をするのです。
例えば、コンピュータAからコンピュータBに通信をするときは、コンピュータAがコンピュータBのIPアドレス宛にデータを送ります。
また、コンピュータAからコンピュータBの間には、ルーターやサーバーなど、さまざまなコンピュータを経由します。
そのため、どのようなルートでコンピュータBまで辿り着けばよいか、ということも判断しなければなりません。
このように複雑な経路を経由しても、データのやりとりを可能にするルールや方法を定めたものがネットワーク層です。
データリンク層
OSI参照モデルの第2層に該当する「データリンク層」は、ネットワークに接続する経路の中で一番イメージしやすい、身近なデバイスとやりとりをするためのプロトコルをまとめた層です。
例えば、AさんのパソコンからBさんのパソコンにデータを送る場合は、以下のような手順になります。
- Aさんのパソコンはまず、一番近くにあるAさん宅のルーターと通信を行う
- 次に、Aさん宅のルーターはWANに出ていき、一番近くの通信機器に接続
- インターネット上でも近くの機器を探しながら、Bさん宅のルーターに辿り着く
- Bさん宅のルーターがBさんのパソコンを認識
このように、身近なコンピュータとやりとりするためのルールや方法を定めたものがデータリンク層です。
物理層
OSI参照モデルの第1層に該当する「物理層」は、通信に必要な物理的なものに対するプロトコルをまとめた層です。
具体的には、LANケーブルや光ファイバーケーブル、無線LAN(Wi-Fi)などの仕様に合わせて、テキストや動画といったデータを電気信号に変換します。
コンピュータネットワークに必要な機器


コンピュータネットワークはどのような機器を使って成り立っているのでしょうか。
ここでは、ネットワーク構成に最低限必要なモノを紹介します。
- パソコンなどのコンピュータ
- ルーターなどのネットワーク機器
- ケーブルや電波などの伝送媒体
パソコンなどのコンピュータ
パソコンやスマートフォンなどの「コンピュータ」を相互につなげることで、ITのネットワークは形成されます。
例えば、あなたのパソコンからWebサイトを閲覧しているとき、あなたのパソコンは別のコンピュータと通信しているのです。
会社内のパソコンから共有ファイルを開くときも、ファイルを共有するためのコンピュータ(ファイルサーバーなど)とネットワークで結ばれています。
ルーターなどのネットワーク機器
コンピュータをネットワークにつなぐためには、ハブとなるネットワーク機器が必要です。
身近なものでいえば、無線LANルーター(Wi-Fiルーター)をイメージすると分かりやすいでしょう。
自宅や会社でパソコンを使う時には、Wi-Fiルーターを介してインターネットにつながります。
あなたがパソコンからWebサイトを閲覧できるとき、あなたのパソコンはネットワークにつながっている状態なのです。
この記事もオススメ



ケーブルや電波などの伝送媒体
ネットワークにつなぐ方法には、有線と無線があります。
ケーブルを使ってネットワークに接続するのが有線接続、無線LAN(Wi-Fi)や携帯電話の電波を使って接続するのが無線接続です。
近年では、パソコンを接続する方法も無線が主流になりました。自宅に無線LANがあれば、パソコンもスマートフォンもネットワークに接続できます。
また、通信のインフラとなるケーブルや4G・5Gの電波といったフィジカルな伝送媒体もITにおけるネットワークを構成するためには必要不可欠です。
この記事もオススメ



ネットワークの種類


私たちが日常的に使用しているネットワークにも、いくつかの種類があります。
ここでは、ネットワークの種類を確認していきましょう。
- LAN(Local Area Network)
- WAN(Wide Area Network)
- インターネット
- イントラネット
LAN(Local Area Network)
LAN(ラン)は「Local Area Network」の略で、社内や自宅内などの機器をつないだネットワークのことを指します。
Local(ローカル)とは「局地的な」という意味です。「インターネット」を世界規模のネットワークとすれば、社内や自宅は「ローカルな(局地的な)」ネットワークだといえます。
WAN(Wide Area Network)
WAN(ワン)は「Wide Area Network」の略で、LANよりも広い範囲のネットワークを指します。
イメージとしては、LANと次に解説するインターネットの間にあるネットワークです。
例えば、東京本社のLANと大阪支社のLANをつなぐネットワークをWANと呼びます。
あるいは、自宅からWebサイトを閲覧する際にも、自宅のルーターからインタネットプロバイダーのネットワークにWAN接続をして、その後インターネットに接続されるという流れです。
この記事もオススメ



インターネット
インターネットは、世界のコンピュータをつないでいるネットワークで、いわゆる「ネット」ですね。
インターネット上には画像や動画などさまざまなコンテンツが存在しており、私たちはパソコンやスマートフォンでインターネットを介して、いつでもコンテンツにアクセスできます。
これは、世界中をつないでいる「インターネット」というネットワークのおかげなのです。
この記事もオススメ



イントラネット
イントラネットは、LANやWANを使った内部的なネットワークのことで、会社内やグループ企業内を限定して構築されます。
社内で利用するファイルサーバーやグループウェアなどは、イントラネットに構築することで、アクセスが許されている人だけに利用を制限するネットワークです。
近年では、イントラネットという言葉を使うことはあまりないかもしれません。しかし、ネットワークを理解するための知識として覚えておくとよいでしょう。
「ネットワーク」を含む関連用語


ここでは、ネットワークに関連した用語を紹介します。
「ネットワーク○○」という用語は多いのですが、それらはネットワークとどのような関係があるのかを同時に確認していきましょう。
- ネットワークカメラ
- ネットワークプリント
- ネットワークセキュリティキー
- ネットワークエンジニア
ネットワークカメラ
ネットワークカメラは、LANやインターネットに接続されたカメラのことで、「IPカメラ」とも呼ばれます。
一番イメージしやすいのは防犯カメラではないでしょうか。建物の内外に設置されているネットワークカメラは、ネットワークで接続された場所でその映像をみることができます。
LANなどのネットワークによってカメラとコンピュータが接続されることで、遠く離れた場所からでもカメラを通して映像を確認できるのです。
ネットワークプリント
ネットワークプリントは、パソコンやスマホからインターネットを介してコンビニなどでプリントをするサービスです。
例えば、スマートフォンで撮った写真を専用アプリでネットワークにアップロードし、その後コンビニのプリンターを使って印刷できます。
ネットワークプリントなどのサービスも、インターネットというネットワークがコンピュータ同士をつなげることで実現しているのです。
ネットワークセキュリティキー
ネットワークセキュリティキーとは、一般的には「暗号鍵」などのセキュリティ関連のキーを指しています。Wi-Fiに接続する際に入力を求められるパスワードが代表的です。
具体的には、以下のようなものがあります。
- WEP/WPA/WPA2/WPA3キー:無線LAN(Wi-Fi)ネットワークにおいて使用されるキーで、ネットワークへの不正アクセスや盗聴から通信を守るために使用される
- IPsecキー:ネットワーク層での通信をセキュアにするためのキーで、通信の機密性や完全性を確保するために使用される
- SSL/TLSキー:Webブラウジングなどで使用されるキーで、暗号鍵がセッションの確立と通信の暗号化に使用される
ネットワークエンジニア
ネットワークエンジニアは、コンピュータネットワークの設計や構築、運用管理をするエンジニアのことです。
例えば、企業内で社員のパソコンから共有サーバーを使えるようにしたり、インターネットを利用可能な状態にしたり、データセンターなどでネットワーク構築をする仕事などさまざま。
ITエンジニアの中でも、ネットワーク専門のエンジニアになりたいという人は、ネットワークエンジニアを目指しましょう。
この記事もオススメ



まとめ:ネットワークの仕組みを知ると現代IT技術の理解も深まる
ネットワークエンジニアを始めとしたコンピュータネットワークを扱う仕事にするには「なぜ、ネットワークがつながるのか」という仕組みを理解しなければなりません。
近年では、パソコンやスマートフォンの他にも、家電や自動車などをネットワークにつなげるIoTといった技術が実現しています。
これから、さらにネットワークエンジニアの需要が高まる可能性は高いでしょう。
ネットワークの基礎をしっかりと身につけて、専門性の高いクラウドも扱えるネットワークエンジニアを目指すと、さらに求められる価値の高い人材になれる可能性があります。
基礎からしっかりと学べば、コンピュータネットワークは理解できるようになるので、ITのネットワークに興味がある人はぜひ学習にチャレンジしてみてください。
この記事もオススメ



はじめての転職、何から始めればいいか分からないなら
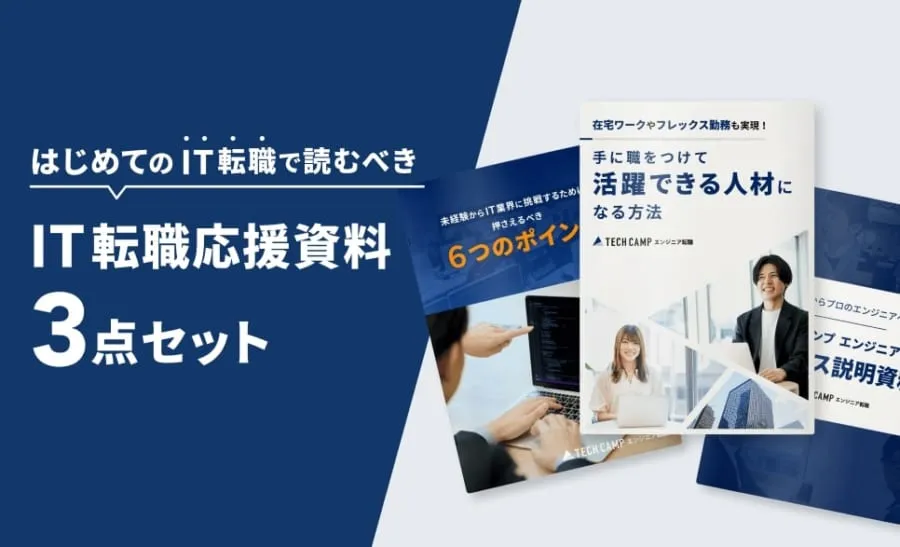
「そろそろ転職したいけれど、失敗はしたくない……」そんな方へ、テックキャンプでは読むだけでIT転職が有利になる限定資料を無料プレゼント中!
例えばこのような疑問はありませんか。
・未経験OKの求人へ応募するのは危ない?
・IT業界転職における“35歳限界説”は本当?
・手に職をつけて収入を安定させられる職種は?
資料では、転職でよくある疑問について丁寧に解説します。IT業界だけでなく、転職を考えている全ての方におすすめです。
「自分がIT業界に向いているかどうか」など、IT転職に興味がある方は無料カウンセリングにもお気軽にお申し込みください。