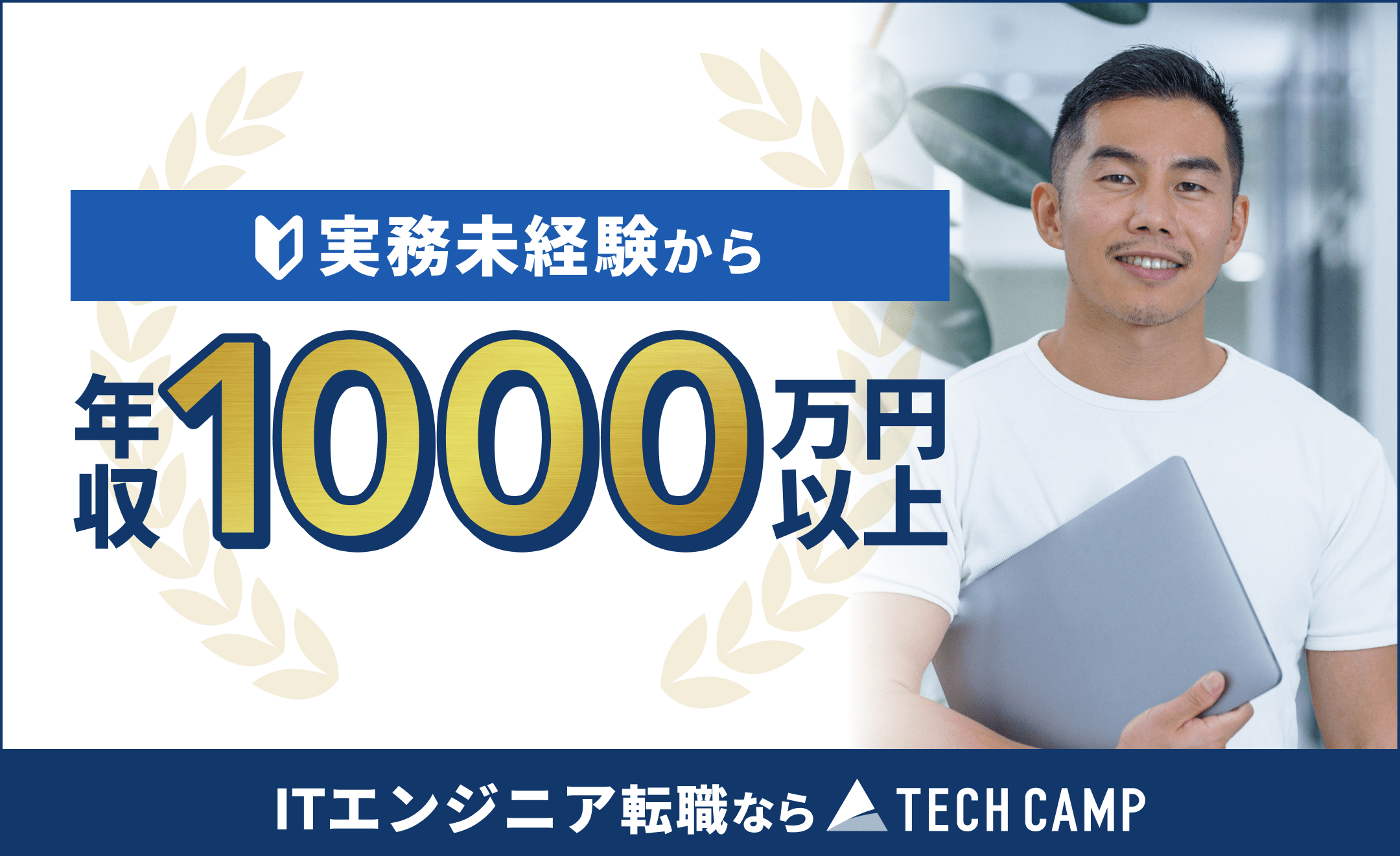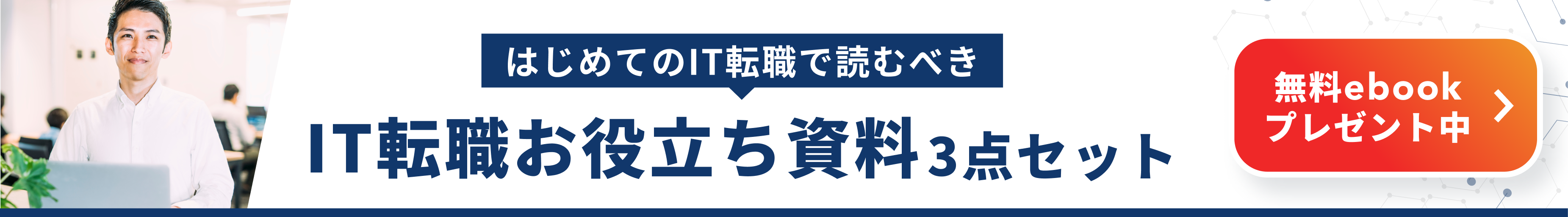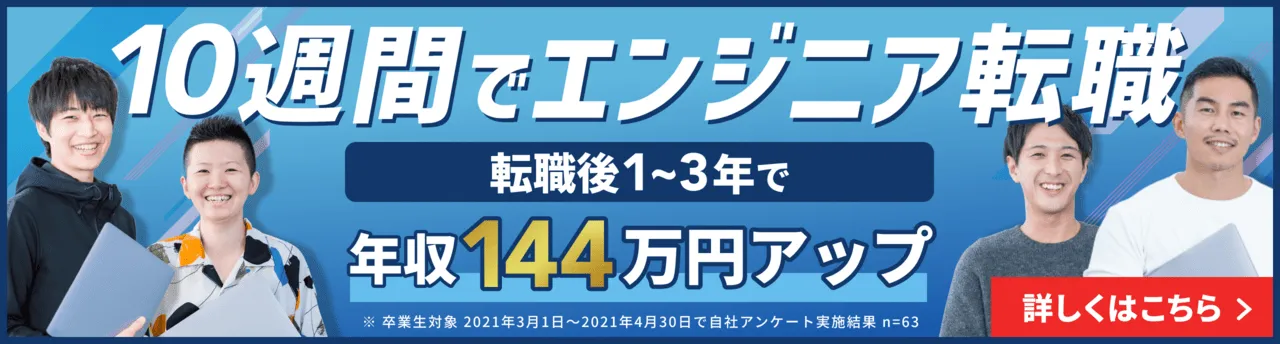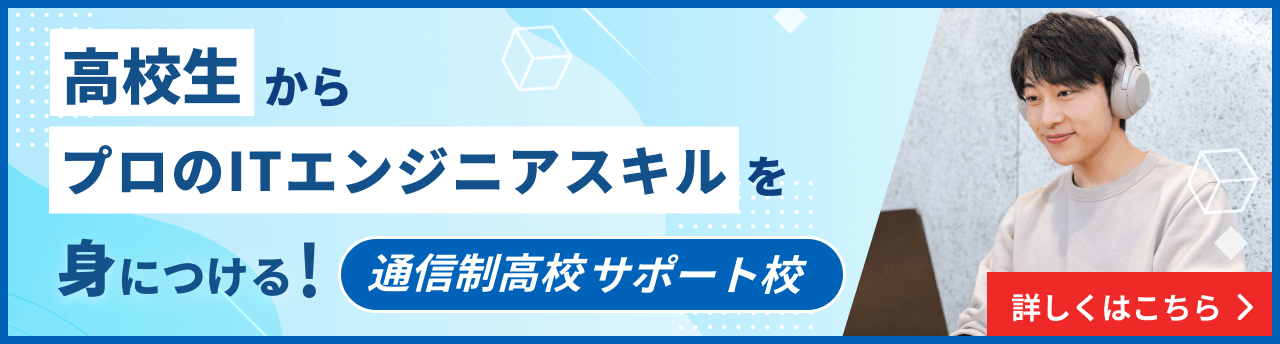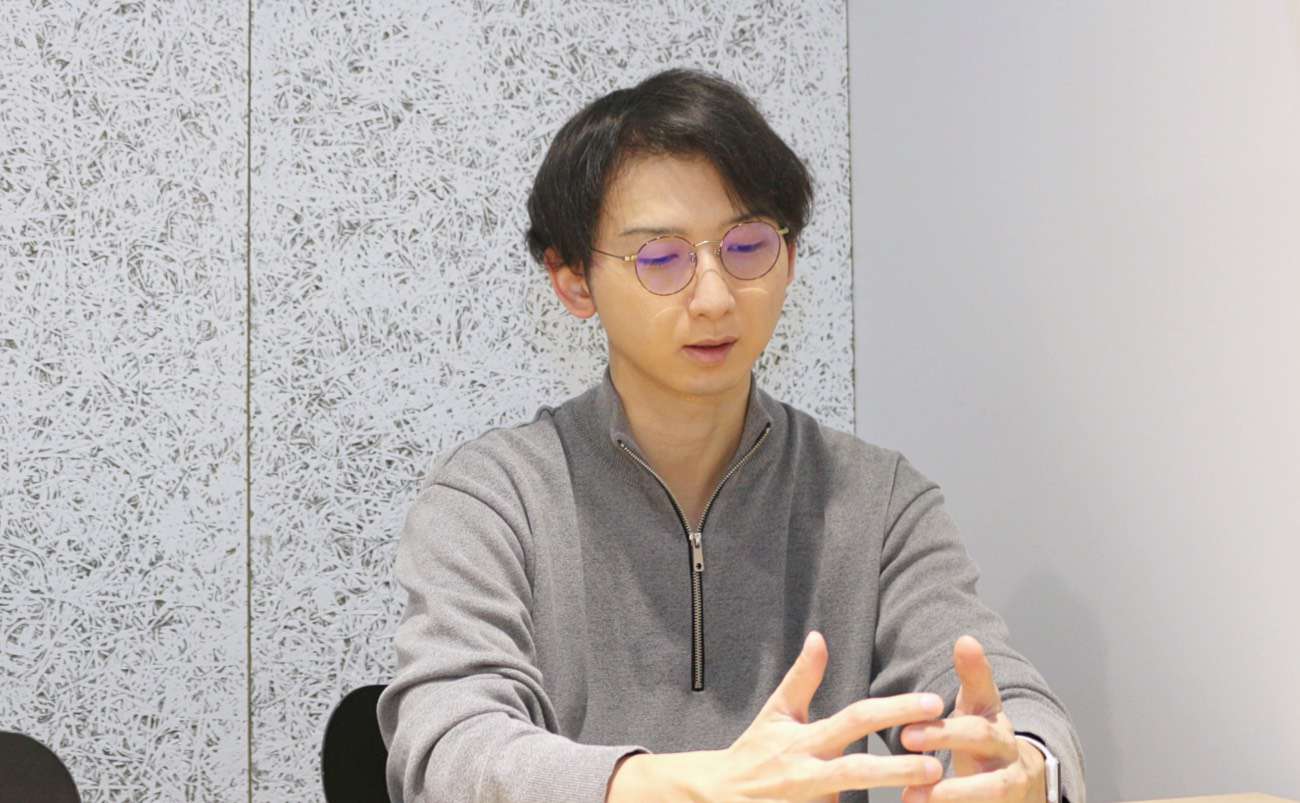「ブルーカラーという言葉を耳にするけど、どういう意味?」
「ブルーカラー・ホワイトカラー・グリーンカラーの違いは何だろう?」
「ブルーカラーとは何か詳しく知りたい!」
職業にまつわる言葉とは何となく理解しているけど、改めて「ブルーカラーとは?」と聞かれるとわからない方も多いでしょう。
そこで本記事では、ブルーカラーの意味や職種、ホワイトカラー・グリーンカラーとの違いなどを解説します。
この記事の目次

ブルーカラーとは?

ブルーカラーとは、「工場や建設現場などで働く技術者・作業員」を指す言葉。
ブルーカラーを英語で表すと「Blue-collar」であり、「カラー」は「color」ではなく「襟(collar)」である点に注目です。
これは、もともと肉体労働に従事する方々の作業服が「青い襟」だったことに由来します。
つまり、ブルーカラーとは「青色」という意味ではなく、服装に由来する呼び名なのです。
ちなみに、コトバンクによるブルーカラーの定義は、以下の通り。
企業組織に雇用されて働く賃金労働者のうち、製造業、建設業、鉱業などの生産現場で直接に生産工程や現場作業に従事する現業系の労働者をさす。ブルーカラー労働者の仕事は、直接に物の生産に携わる肉体労働であることが特徴である。
この記事もオススメ

【無料】ChatGPTの使い方をマンツーマンで教えます
・ChatGPTの基本的な使い方がわかる
・AIの仕組みがわかる
・AIをどうやって活用すれば良いかがわかる お申し込みは1日5組限定です。
今すぐお申し込みください。 ChatGPTレッスンを確認する▼
https://tech-camp.in/lps/expert/chatgpt_lesson
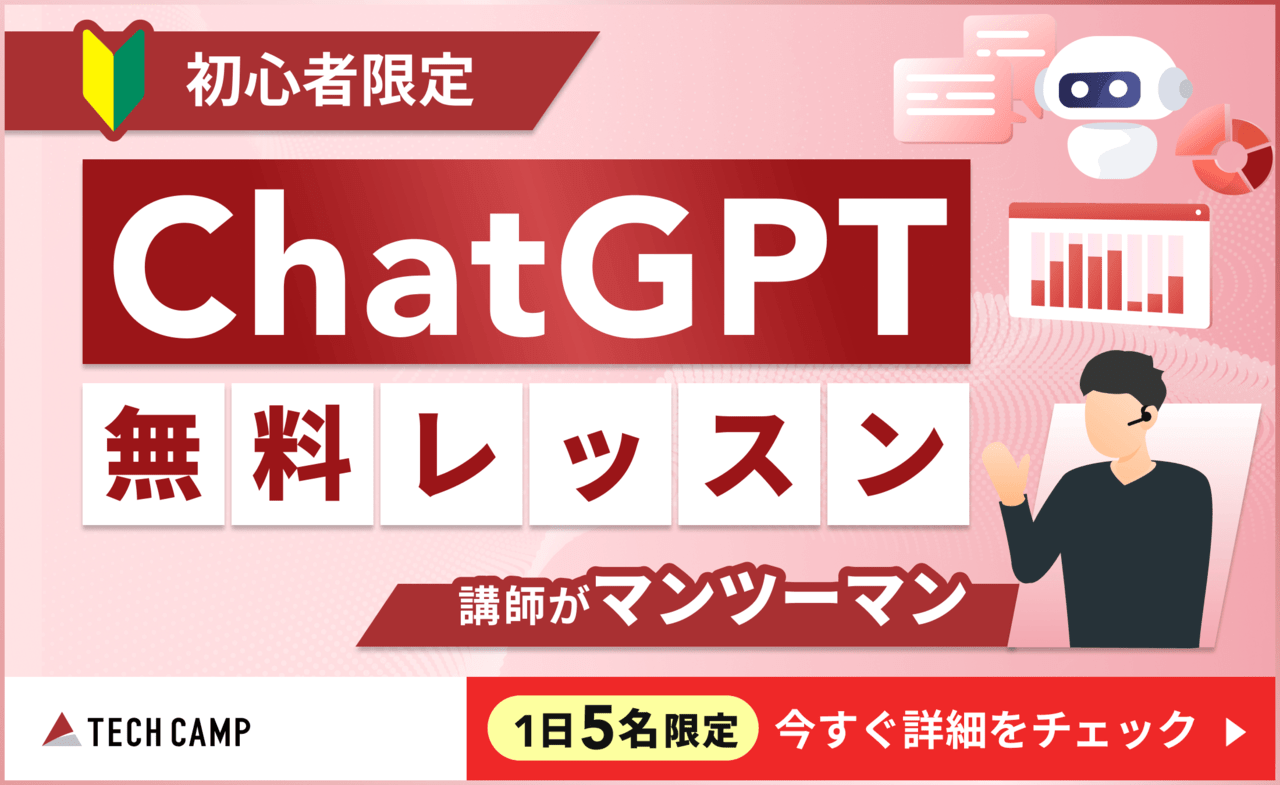
ブルーカラーの職種


ブルーカラーのおもな職種は、以下の通りです。
- 整備工
- 修理工
- 運送スタッフ
- 土木作業員
- 建設作業員
上記の職種について解説します。
整備工
整備工は、基幹産業であるインフラサービスに関わる電気、水道、ガス業、エネルギー産業、工場などで機械の整備を行うブルーカラーです。
エネルギー産業には、原子力発電、石炭や石油の火力発電所、水力発電所が含まれます。
環境(エコロジー)との関係性も強く、電気工事などの仕事も、整備工の役割です。
太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、地熱発電などがありますが、今はまだ生産量が低くコスト高な状態ですが、将来的には環境に良い自然エネルギーに代替される流れが予想されます。
これらの環境分野の技術者にも熱い視線が注がれています。
修理工


修理工は、壊れた機械の修理を行うのがおもな仕事で、関わる業界はインフラ修理から車両修理まで幅広いです。
身の回りでよく目にする機械だけでなく、産業用機械や生産現場の機械も修理する、企業の生産性を支える専門性が高い職種です。
特に、インフラ産業は故障時には修理工の迅速な対応が必要で、東日本大震災での原発作業員の活躍は大規模な修理の一例といえるでしょう。
この記事もオススメ



運送スタッフ
運送スタッフは、トラックの運転手・クレーン操作・機械のオペレーターなどの、運輸業に関わるブルーカラーです。
輸送のほかにも、旅客運転手や特殊重機による大型建造物の輸送を行う特殊作業員もいます。
さらには、国内のみならず海外でプラント建設などに従事する運送スタッフもいます。
土木作業員


土木作業員は、一般道路・高速道路・橋梁・河川敷などの建設作業で従事する職種です。
土木関連では、ロボットを用いたオートメーション化が進んでいるものの、いまだ労働者不足が問題に上がることもあるようです。
建設作業員
建設作業員は土木作業員と似た仕事で、公共施設・高層ビル・一般住宅・マンションなどの建設現場で従事するブルーカラーです。
また、インターネットがITインフラとして確立している背景から、全国にある電波基地の設置やサーバーの設置などを行う作業員もいます。

ホワイトカラー・グリーンカラーとの違い


本章では、ブルーカラーと比較されることの多い、ホワイトカラー・グリーンカラーとの違いについて解説します。
ホワイトカラーとの違い
ホワイトカラーとは、「営業職・事務職・財務・経理・マーケティング職などに従事する労働者」で、いわゆる「頭脳労働」や「サラリーマン」に該当する言葉です。
つまり、ホワイトカラーとブルーカラーの違いは、ブルーカラーが「肉体労働系の仕事」、ホワイトカラーは「頭脳労働系の仕事」という点です。
ちなみに、コトバンクによるホワイトカラーの定義は、以下の通り。
私企業や行政機構などの組織体に雇用されて働く賃金労働者である点ではブルーカラーと同じ立場にあるがホワイトカラーは、物の生産に直接にはかかわらない非現業的職種に携わる。具体的には、専門的・技術的職業、中・下級の管理的職業、事務的職業、販売的職業、対人サービス職業などが主体であり各種のシンボルや人間を対象とする知的な精神労働であることが、ホワイトカラーの仕事の特徴である。
この記事もオススメ



グリーンカラーとの違い
グリーンカラーとは、おもに「自然環境に関連する分野に従事する労働者」を指す言葉です。
自然環境に関連する分野とは、例えば風力発電・太陽光発電などの自然エネルギー関連、林業・リサイクル事業・水質調査などのエコ関連などが該当します。
つまり、自然エネルギー関連の建設現場に従事する方は、ブルーカラーでもありグリーンカラーでもあるということです。
この記事もオススメ



ブルーカラーの年収


厚生労働省の『令和2年 賃金構造基本統計調査』を参考にすると、2019年のブルーカラーに該当する職種の平均年収は、以下の通り。
| 職種 | 平均年収 |
| 自動車整備工 | 約440万円 |
| 機械修理工 | 約489万円 |
| 営業用大型貨物自動車運転者 | 約455万円 |
| 土木作業員 | 約329万円 |
| 建設機械運転工 | 約420万円 |
| 大工 | 約414万円 |
| とび工 | 約393万円 |
| 港湾荷役作業員 | 約532万円 |
| 電車運転士 | 約618万円 |
| 航空機操縦士 | 約1,694万円 |
上記の通りで、ブルーカラーという枠の中でも、年収には大きな差があります。
例えば、土木作業員やとび工は低いものの、港湾荷役作業員や電車運転士は高い傾向です。
また、ブルーカラーの中でも航空機操縦士(パイロット)は、年収1,600万円以上と高収入が約束されています。
この記事もオススメ



ブルーカラーの将来性


ブルーカラーは、近年確実に進んでいるオートメーション化の流れから、AIやロボットに業務が代替される可能性が高いです。
例えば、セレンディクス株式会社が提供するサービスでは、3Dプリンター技術を使うことで、建設費300万円の住宅が作れるそうです。
また、竹中工務店が提供する自走式墨出しロボットは、建設現場での工事の基準となる線や位置の表示をオートメーション化することで、飛躍的な業務効率化を実現します。
さらに、自動運転技術やドローン技術なども、ブルーカラーの仕事を奪うでしょう。
こうした背景から、これまで肉体労働で行ってきたブルーカラーの業務は、自動化のあおりを受けてなくなることから、将来性は低いといえるかもしれません。
一方で、自動ロボットやドローンの操作といった新たな業務が生まれたり、代替が難しい繊細な業務はなくならないことから、一定の需要は残り続けると考えられます。
この記事もオススメ



メタルカラーとは?


「メタルカラー」とは、高度な技術を持つ、創造的な工業技術者を指す言葉です。
ブルーカラーよりもさらに専門性が高く、生産性の向上に貢献する仕事で、階級が高い職人としての技能を持つ、高度な人材と言えます。
ブルーカラーと同様造語で「カラー」という言葉を使っているものの、こちらは襟の色とは関係ありません。
ノンフィクション作家の山根一眞氏による造語
メタルカラーとは、そもそもノンフィクション作家、山根一眞氏によって提唱された用語。
「週刊ポスト」で連載された「メタルカラーの時代」を語源としています。
含まれる職種としては、技術職・職人が中心です。
世界水準の技術を誇る産業に属するものが多く、鉄鋼や自動車、半導体製造業など、特に熟練を要する現業が挙げられます。
2000~2005年までNHKで放送され、社会的に反響を呼んだ番組「プロジェクトX」でスポットを当てた技術者などが該当します。
この記事もオススメ



ブルーカラー志望なら市場価値の高い人材になろう
ブルーカラーの意味や職種、ホワイトカラー・グリーンカラーとの違いなどを解説しました。
ブルーカラーは、オートメーション化・AI技術・ロボットなどに業務が代替される可能性の高いため、将来を見据えた働き方が求められるでしょう。
つまり、こうしたイノベーションとうまく共存できる仕組みの中で働ける人材になることが、未来のブルーカラーに必要となるはずです。
したがって、ブルーカラー志望の方は、業界の中で市場価値の高い人材を目指しましょう。
この記事もオススメ



はじめての転職、何から始めればいいか分からないなら
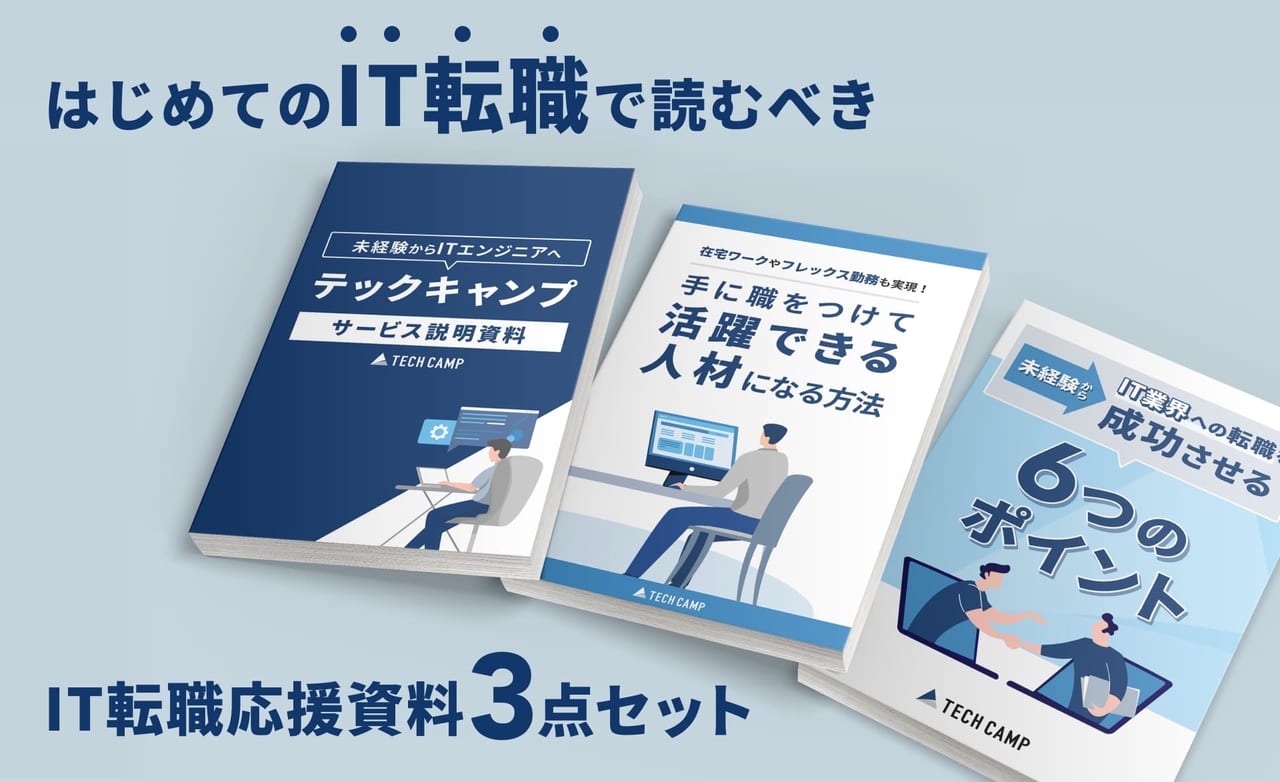
「そろそろ転職したいけれど、失敗はしたくない……」そんな方へ、テックキャンプでは読むだけでIT転職が有利になる限定資料を無料プレゼント中!
例えばこのような疑問はありませんか。
・未経験OKの求人へ応募するのは危ない?
・IT業界転職における“35歳限界説”は本当?
・手に職をつけて収入を安定させられる職種は?
資料では、転職でよくある疑問について丁寧に解説します。IT業界だけでなく、転職を考えている全ての方におすすめです。
「自分がIT業界に向いているかどうか」など、IT転職に興味がある方は無料カウンセリングにもお気軽にお申し込みください。