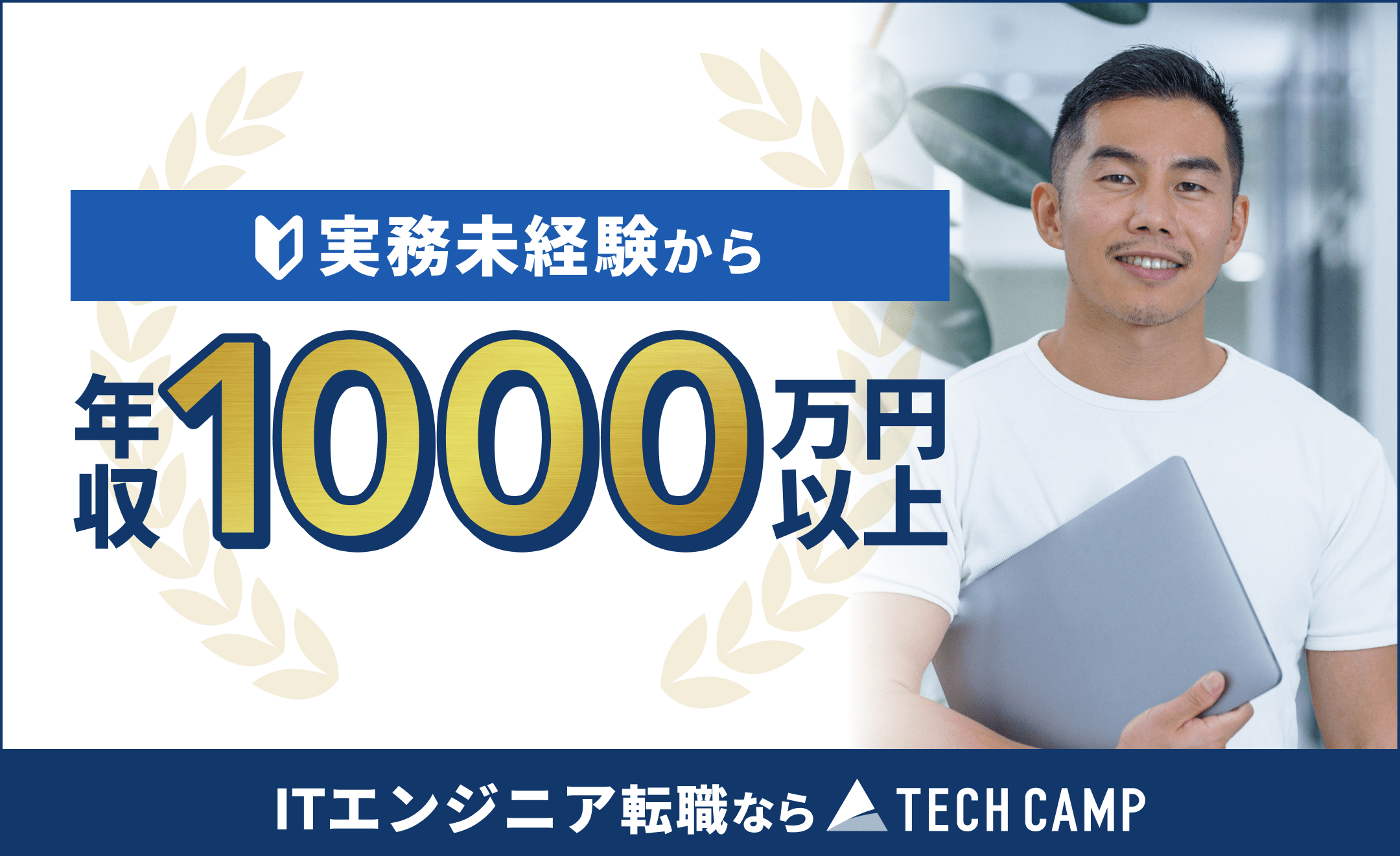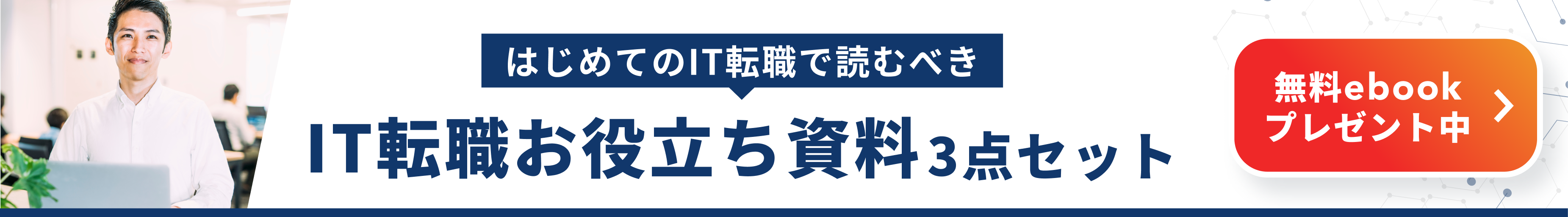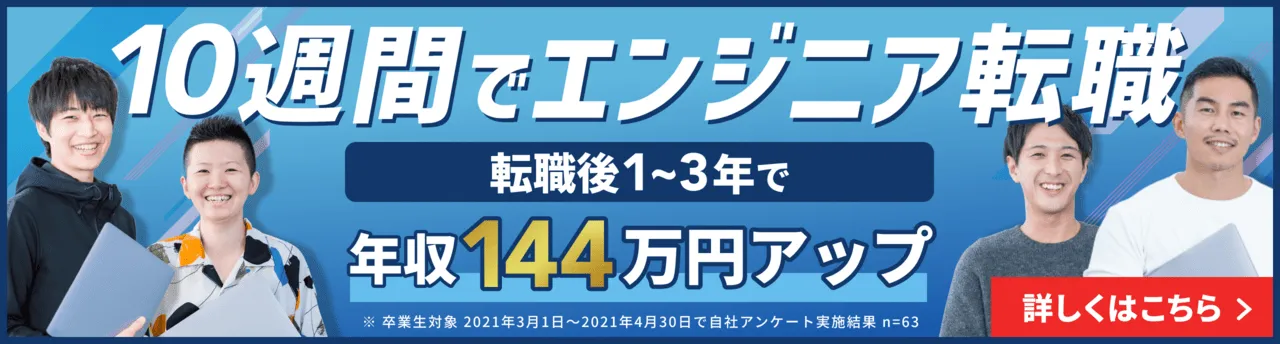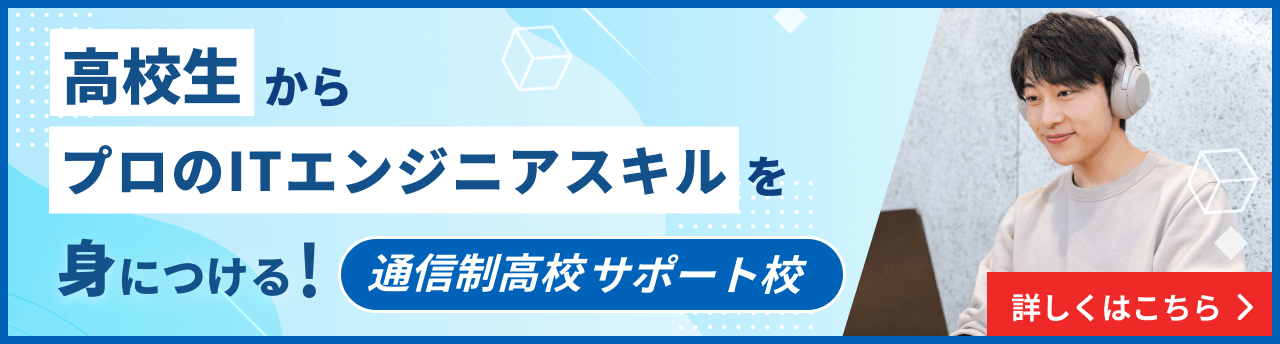「リテラシーとは?意味をわかりやすく解説してほしい」
「リテラシーがない・リテラシーが低いってどういうこと?」
「コンピテンシーやモラルとの違いは何だろう?」
ビジネスシーンやニュースなどで「今の時代はITリテラシーが必須」「メディアリテラシーを高めよう」などの声を聞くことがあります。
しかし、この「リテラシー」とは何なのかよく分からないので、何となくで聞き流しているという方も多いかもしれません。
そこで本記事ではリテラシーの意味、コンピテンシー・モラルとの違い、リテラシーのおもな種類、使い方と例文などを分かりやすく解説。
本記事を通してリテラシーを学んでみましょう。
この記事の目次

リテラシーとは

「○○リテラシーが低い」「○○リテラシーを養え」
あなたも、このような言葉を聞く機会が増えたのではないでしょうか。
リテラシーは、ビジネスがIT化されてから頻繁に使われるようになりました。ITリテラシー・ネットリテラシー・金融リテラシーなど、その種類もさまざま。
まずは、「リテラシー」という用語について、その意味と種類について以下の流れで確認していきましょう。
- 「適切に理解・解釈・活用する力」のこと
- 「リテラシーがない」「リテラシーが低い」の意味
- 英語の「literacy」から考える本来の意味
- リテラシーの類語
「適切に理解・解釈・活用する力」のこと
リテラシーには以下のような意味があります。
- 物事を適切に理解/解釈すること
- 理解/解釈したことを活用すること
- 読み書き能力/知識
ビジネスでリテラシーを使うときは、「物事を適切に理解/解釈すること」と「その能力を仕事や日常で応用し活用すること」の意味で使うことが多いです。
わかりやすくいえば、リテラシーとは理解力と応用力のことを指し、さらに簡単にいえば「使いこなす能力」を指しています。
「リテラシーがない」「リテラシーが低い」の意味
「リテラシーがない」「リテラシーが低い」とは、情報を適切に理解し活用する能力が低い、あるいはその能力が欠如しているという意味で使われます。
例えば、「メディアリテラシーが低い」とは、新聞やテレビやインターネットサイトから正確な情報を得る能力が低い、といった具合です。
また、「コンピューターリテラシーがない」とは、パソコンやモバイルなどのIT機器を使いこなせる能力がないというニュアンスで使われます。
パソコンやスマートフォンを使ってメディアの情報を取得する機会の多い現代では、リテラシーが高い人ほど正確な情報を幅広く活用できるということですね。
「リテラシーがない」「リテラシーが低い」の言い換え
おもに「情報リテラシーがない」「情報リテラシーが低い」の言い換えとして、「情報弱者」略して「情弱」という言葉が使われます。
インターネットの普及により得られる情報に格差が生まれたことから、ネット上でしばしば使われるようになりました。
英語の「literacy」から考える本来の意味
リテラシーはそもそも「literacy」という英単語です。この言葉には、本来「読み書きの能力」という意味があります。
情報源が少ない時代は、新聞・書籍などの紙媒体(アナログ)から情報を読み取り、理解したことや覚えたことをだれかに伝えるために紙に書く。
こうした一連の能力が「リテラシー」として考えられてきました。
しかし、現代はテクノロジーの発達や世界的な人口増加などに伴い、情報量だけでなく情報を得る手段も多彩になりました。
これに伴い、正しい情報の取捨選択や、情報を得るための道具であるパソコンやスマートフォンを使えるか否か、という能力も必要になったのです。
リテラシーの本来の意味は「読み書き能力」ですが、このままの意味で使われることはあまり見られません。
リテラシーという言葉は、現代では「それを正しく理解して活用できること」も含めたニュアンスで使われます。
リテラシーの類語
リテラシーの類語についても確認しておきましょう。
リテラシーは、情報の意味を正しく理解し応用する能力のことを指しますが、それらを含む用語は他にもあります。
- 判断能力
- 活用能力
- 識別能力
- 批判精神
上記の類語はすべて、リテラシーに含まれる能力です。「情報の意味を正しく理解し応用する能力」は1つの能力だけでは決まりません。
上記の能力をうまく組み合わせて、はじめて「リテラシーが高い人」になれるのです。そのため、これらの類語を包括した用語ともいえるでしょう。
リテラシーとコンピテンシー・モラルの違い

リテラシーには、いくつか意味を間違えやすい言葉があります。そこで本章では、その中でも意味を混同しがちな「コンピテンシー」と「モラル」との違いを解説。
コンピテンシーとは
コンピテンシー(Competency)とは、これまでの経験で培ってきた行動特性やコミュニケーション能力を表す用語です。
リテラシーとコンピテンシーの違いをまとめると、以下のようになります。
- リテラシー:正しい情報を取得して知識をつけ、問題を解決する能力
- コンピテンシー:経験則からくる、良好な対人関係や経験を活かした実務の行動能力
リテラシーとコンピテンシーは「ジェネリックスキル」の1つともいわれています。
ジェネリックスキルとは、ビジネスや日常で汎用的に使えるスキルのこと。ジェネリック(generic)は「一般的な」という意味です。
近い言葉としては、「ポータブルスキル」や「移転可能スキル」などがあります。企業が人材を評価する際に意識されるポイントでもあるので覚えておきましょう。
モラルとは
モラル(Moral)とは、道徳や倫理を表す言葉です。
例えば、SNSで誹謗中傷に該当する発言をする、自分に非があるのに謝罪をしない、公共施設での迷惑行為(図書館で騒ぐなど)を平気で行うことなど。
こうした社会常識と外れた行為を取る人・非常識的な行動をする人に対して、「〇〇はモラルがない人」といった使い方をします。

リテラシーのおもな種類7つ

「リテラシー」は、それだけでも意味が通じる言葉。しかし近年では、それぞれの分野ごとに細かく分けられている印象です。
「〇〇を使いこなせる能力」という意味合いで「○○リテラシー」という表現を用います。
そこで本章では、数ある〇〇リテラシーの中でも、特に日常やビジネスでよく使ったり聞くことがあるリテラシーの種類を7つ紹介します。
- ITリテラシー
- メディアリテラシー
- ネットリテラシー
- コンピュータリテラシー
- 情報セキュリティリテラシー
- 金融リテラシー
- 文化リテラシー
ITリテラシー
ITリテラシーとは、インターネット上に存在する情報を正しく理解し活用できる能力のことです。「情報リテラシー」とも呼ばれます。
具体的には、インターネットから情報を収集し、その情報に対して事実確認(ファクトチェック)をして正誤判定まで下せる能力です。
事実確認においては、複数の情報を比較調査したり、企業や国の統計情報などで実施。必要な場合は、その情報源(ソース)を取得します。
また、後述する「コンピューターリテラシー」は、ITリテラシーに含まれる能力であり、ITリテラシーはIT全般に対するリテラシーのことです。
インターネットと常時接続できる現代にあって、情報を正しく理解し活用できるITリテラシーは、現代人に必須の能力といえるでしょう。
この記事もオススメ

メディアリテラシー
メディアリテラシーとは、新聞・テレビ・インターネット・SNSなどのメディアから得られる情報の中から、正しい情報を選び出し、活用できる能力のことです。
情報過多により、フェイクニュースや情報源が不明なデータがあふれ正しいニュースが埋もれてしまうことも多い現代。
こうした中で、信頼できる情報を取捨選択できる能力が求められています。
SNSなどで流れてくる情報を鵜呑みにしないことや、自身で情報の正しさを探り理解することもメディアリテラシーに含まれます。
フェイクニュースを鵜呑みにして拡散してしまうなどの失敗をすると、「メディアリテラシーの低い人」だと評価されるかもしれません。
この記事もオススメ



ネットリテラシー
ネットリテラシーとは、インターネットを正しく使える能力のことです。
メディアリテラシーに近い意味であり、世の中にあふれるデマやフェイクニュースといった嘘の情報を見抜き、拡散されている噂を鵜呑みにしないこと。
そして、ネットを正しく理解できる能力という意味合いがあります。
また、インターネット上で他人を傷つける情報や、肖像権や著作権などのプライバシーを侵害するような情報を発信しないよう意識することも、ネットリテラシーに該当。
近年はSNSで不特定多数の人とつながる機会が急激に増えました。こうした背景からも、正しい情報を見抜くためのネットリテラシーは重要な能力。
この記事もオススメ



コンピュータリテラシー
コンピュータリテラシーとは、パソコン・スマホ・タブレット・ウェアラブルデバイスなどのIT機器を使って正しい情報を取得する能力のこと。
例えば、パソコンを使って情報を得るためのキーボードやマウスの操作、アプリケーションの使い方を知っているということもコンピュータリテラシーです。
また、情報を見つけるための検索方法(ワードのチョイス)や、よく利用するWebサービスやアプリがどのような仕組みや意図で成立しているかを理解することも含まれます。
情報を調べるときに、機器を使った調査手段をすぐに思いつき、正しい情報にたどり着ける人は「コンピュータリテラシーの高い人」だと評価されるでしょう。
この記事もオススメ



情報セキュリティリテラシー
情報セキュリティリテラシーとは、パソコン・スマホ・WebなどのITツールを利用する際にセキュリティリスクを考えた行動が取れる能力を指します。
仕事における問題が発生することを未然に防ぐ上で、非常に重要な能力です。
情報セキュリティへの意識は、個人だけでなく企業レベルでも至上命題として重要なこと。情報セキュリティリテラシーの基礎は社会人としてぜひ身につけておきたいです。
以下、情報セキュリティの一例を挙げます。
- 漏洩しづらいパスワードを設定して管理を徹底する
- 信頼性の低いネットワークに接続しない
- メールの誤送信や機密ファイルの流出に留意する
- フィッシング詐欺などのリスクを理解して、不審なメールやWebページを開かない
- 安全性の低いソフトウェアをインストールしない
この記事もオススメ



金融リテラシー
金融リテラシーとは、お金に関する知識や、お金を動かすときの判断能力を指す用語。
この能力は日本国内だけに限らず、世界経済の情勢まで把握することで成り立ちます。個人レベルでは、家計における支出と収入の管理、貯金や投資の知識も金融リテラシーです。
また、クレジットカード・オンラインバンキング・保険商品への理解、将来や老後に向けた資産形成についても、金融リテラシーが高い人は抜け目なく考えています。
文化リテラシー
文化リテラシーとは、過去から現在に至るまでの文化を正しく理解して、文化における慣習やルールに対して順応・活用できる能力を指します。
文化リテラシーが身に付くと、国や地域の文化の違いを理解でき、互いの文化を認め合うことができるのです。国際交流においては欠かせないスキルでしょう。
今や、日本国内にも多くの外国人が住み、一緒に働いているという環境は珍しくありません。
こうした中で、それぞれの国の習慣や文化を理解し尊重し合うことは、グローバル化した現代社会では必須の能力。文化リテラシーは社会人として身につけておきたい能力なのです。
まだまだある〇〇リテラシー
上記に挙げた以外にも、「〇〇リテラシー」という言葉はさまざま。さらに色々なリテラシーの一例を以下に挙げてみました。
- データリテラシー
- ゲームリテラシー
- 環境リテラシー
- 統計リテラシー
- 科学リテラシー
- 法律リテラシー
- マルチメディアリテラシー
- ヘルスリテラシー
時代が進むに連れて、新たな「〇〇リテラシー」が生まれ、多様化が進むでしょう。
このように、あらゆる分野にリテラシーという言葉が存在します。それだけ、リテラシーは現代人にとって非常に重要な能力なのです。
ビジネスシーンでのリテラシーの使い方と例文


リテラシーの意味を把握できたところで、ここではビジネスシーンでの使い方と例文をチェックしておきましょう。
リテラシーの言葉としての使い方
リテラシーという言葉は以下のような使い方をします。
- リテラシーが高い
- リテラシーが低い
- リテラシーがある
- リテラシーがない
- リテラシーを身に付ける
- リテラシーを持っている
- リテラシーを高める
リテラシーはこれまでの説明の通り、「ある分野に関する知識やスキルを実際に使いこなせる能力」を指す言葉と認識しておくのがよいでしょう。
リテラシーの意味をしっかり把握しておくと、使い方について理解しやすいです。
一方で、共通認識を持つことが難しいマイナーなものも。そのため、リテラシーという言葉を使う時は、相手がしっかり理解できるか判断する必要があります。
「リテラシー」を使った例文
リテラシーを使った例文をいくつか紹介します。
- 仕事をするならばコンピューターリテラシーは必須だ
- メディアリテラシーを高めて正確な情報を取得しよう
- あの人は金融リテラシーが低いから投資には不向きだ
- グローバルな社会を実現するには国民1人1人の文化リテラシーの向上が不可欠だ
身近で使う機会があるのは、ITリテラシーやメディアリテラシーなどが多いと思います。前述の「リテラシーの言葉としての使い方」と合わせて確認してみてください。
リテラシーの意味をしっかりと理解すれば、仕事でも私生活でも自然にリテラシーという言葉を使えるはずです。
ITリテラシーを高めるにはどうすればいい?


今や日常生活に欠かせないものになっているインターネット。
もはやインフラの1つである一方で、SNSでの誹謗中傷やフェイクニュースなど、ネガティブな側面もしばしば語られます。
こうした中で、インターネットを正しく活用していく上でITリテラシーは必須です。
そこでITリテラシーをどうすれば高められるのか、具体的な方法としては以下があります。
- IT系の情報を発信しているメディアを定期的にチェックする
- IT系の国家資格・民間資格の取得に挑戦する
- IT知識を学べるセミナーを受講する
1つ目の「IT系メディアをチェックする」では、具体的には「IT media」や「NewsPicks」などがおすすめです。最新のIT情報を収集できます。
2つ目の「IT系の国家資格・民間資格の取得」では、国家試験の「ITパスポート」や「基本情報技術者試験」の取得がおすすめです。勉強しながらIT知識が身に付きます。
3つ目の「セミナーの受講」では、「TECH PLAY」で検索が可能。そのほか、オンライン動画教材の「Udemy」で受講するのもおすすめです。
ITリテラシーを高める方法は、「ITリテラシーを高める6つのメリットと4つの方法を解説!」でも解説しています。
リテラシーの意味を正しく理解して使いこなそう
リテラシーの意味、コンピテンシー・モラルとの違い、リテラシーのおもな種類、使い方と例文などを一挙に紹介しました。
かつてのリテラシーの意味と現代で使われているリテラシーは若干違います。
しかし、今の時代に即したツールを正しく理解し使いこなすという意味では、本質的な意味としては同じといっても過言ではありません。
リテラシーの意味や種類を正しく理解すれば、ビジネスでは同僚や取引先から信頼を得られる1つの要素になるはずです。
もちろん、日常生活でもリテラシーは自分の身を守る能力となるでしょう。
遅すぎることはありません。この機会に、ITひいてはメディアやネットを使いこなすためのリテラシー学習を始めてみてください。
はじめての転職、何から始めればいいか分からないなら
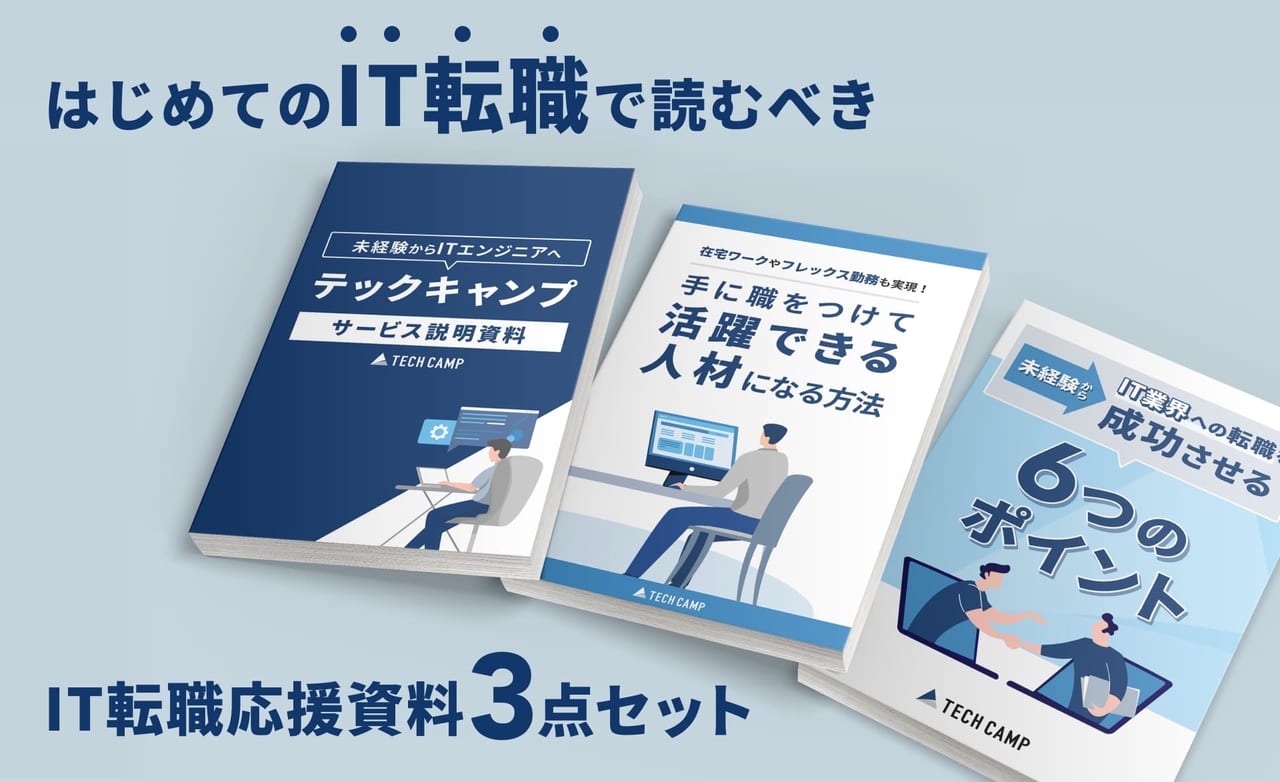
「そろそろ転職したいけれど、失敗はしたくない……」そんな方へ、テックキャンプでは読むだけでIT転職が有利になる限定資料を無料プレゼント中!
例えばこのような疑問はありませんか。
・未経験OKの求人へ応募するのは危ない?
・IT業界転職における“35歳限界説”は本当?
・手に職をつけて収入を安定させられる職種は?
資料では、転職でよくある疑問について丁寧に解説します。IT業界だけでなく、転職を考えている全ての方におすすめです。
「自分がIT業界に向いているかどうか」など、IT転職に興味がある方は無料カウンセリングにもお気軽にお申し込みください。