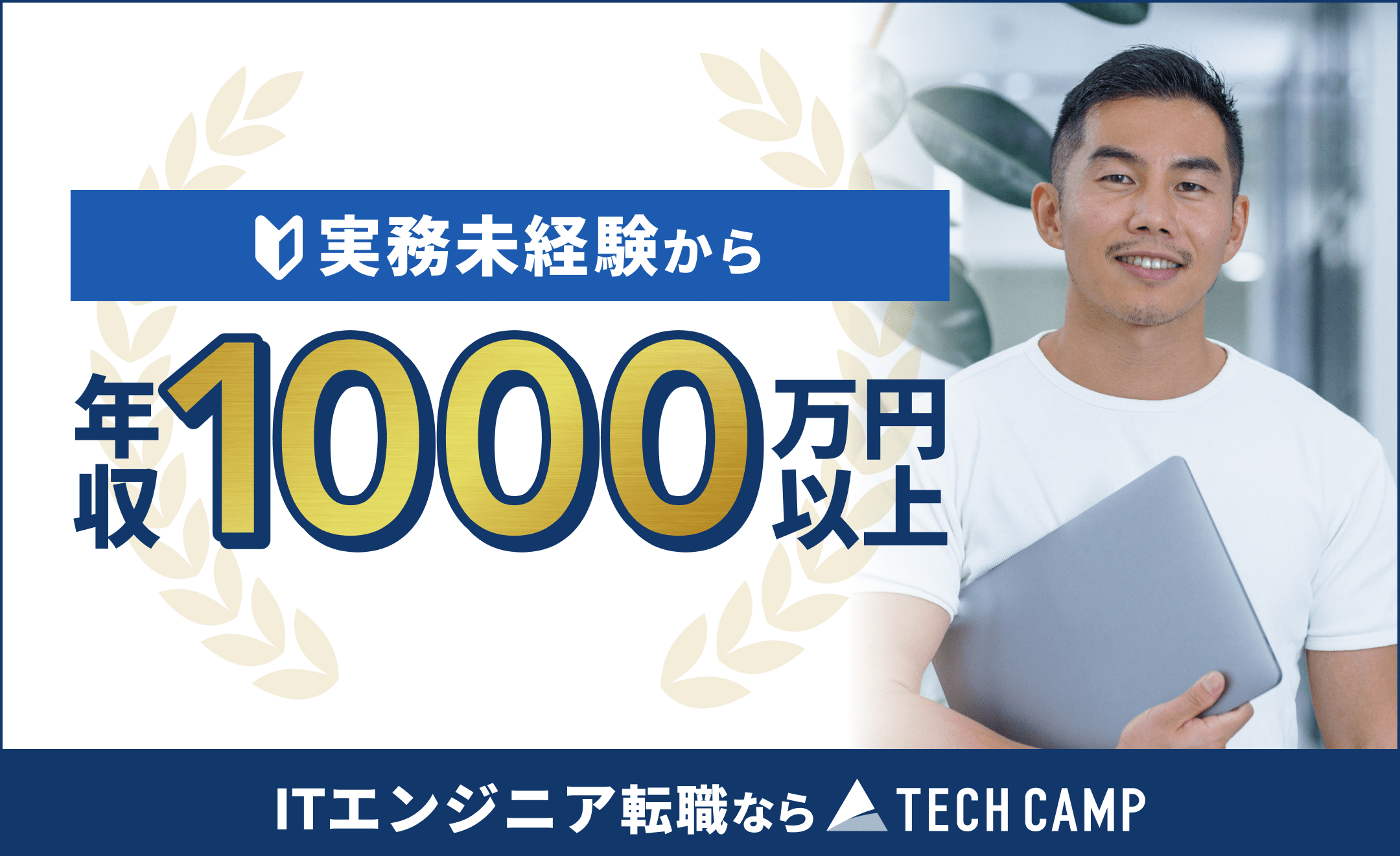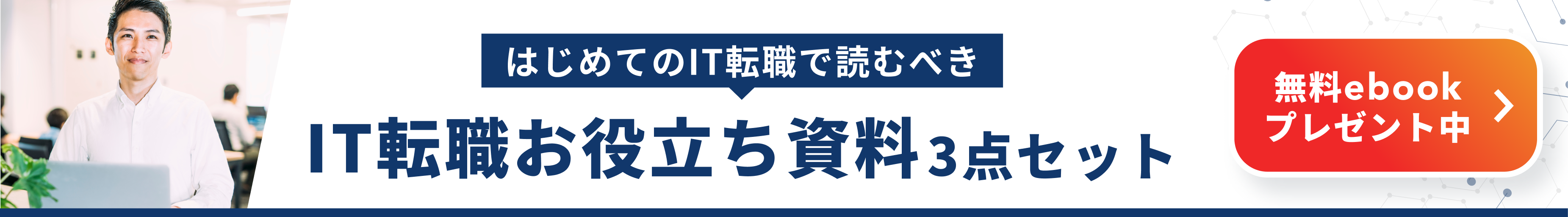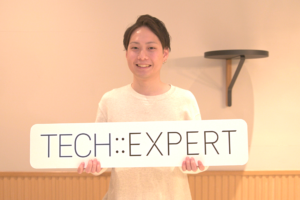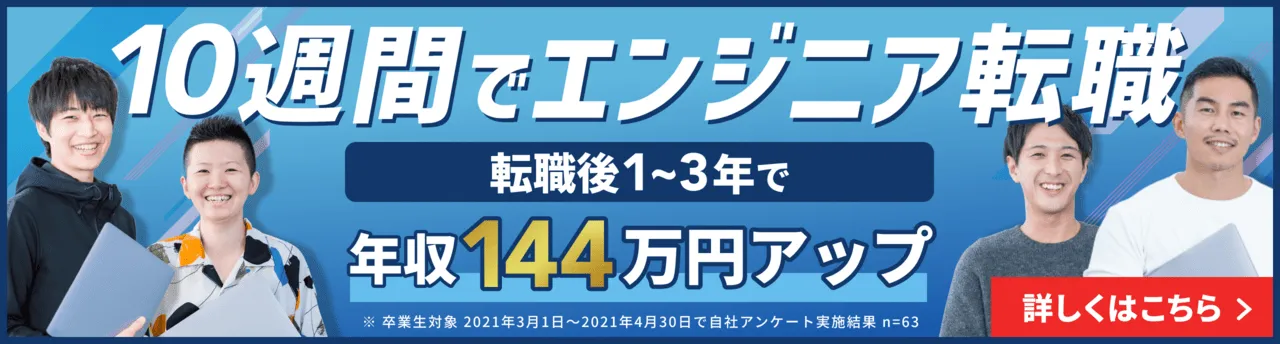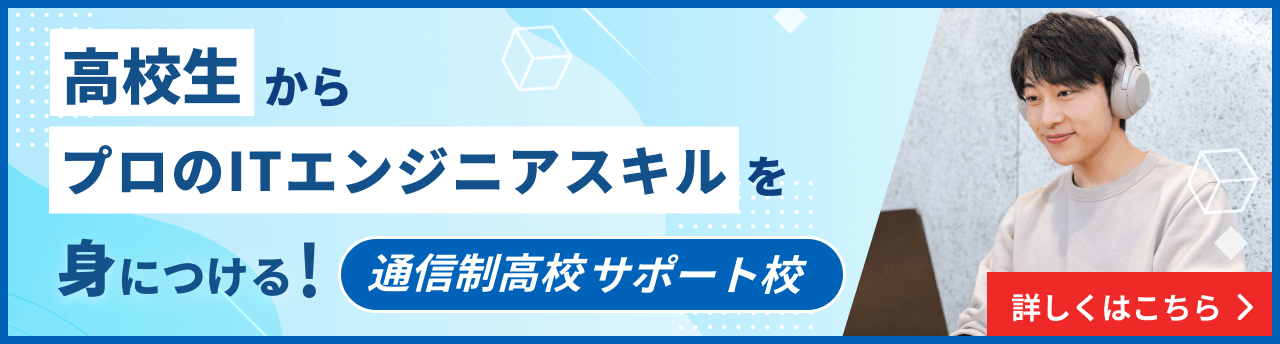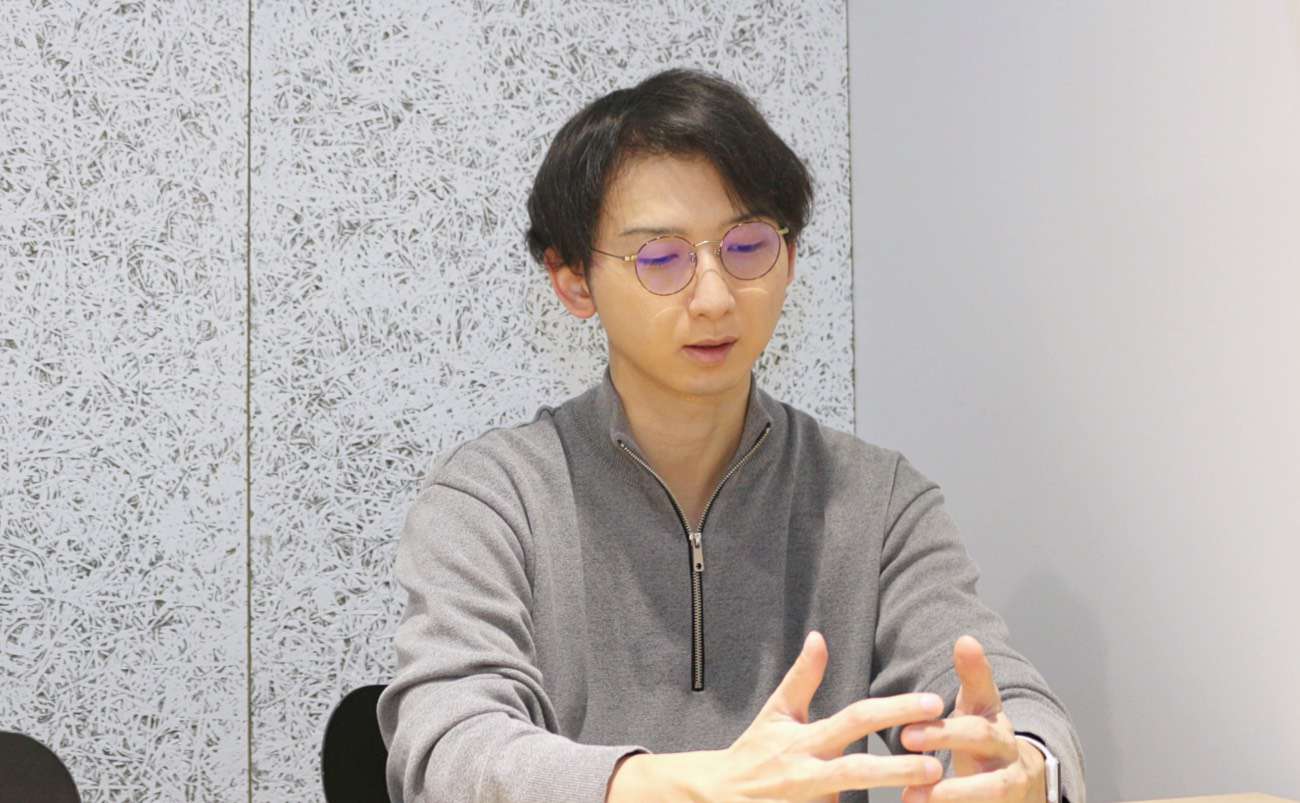- 身内(子供・孫):30,000~50,000円
- 兄弟・姉妹:20,000~30,000円
- 甥・姪:10,000~20,000円
- 上記以外の親戚:5,000~10,000円
- 友人・先輩・後輩・恋人など:5,000円~10,000円
「内定が出た先輩に就職祝いを渡したい」
「後輩が就職が決まったらしいが何を渡そう」
現在あなたはこう考えていませんか。
身近な人が就職活動を頑張っていたのを知っていた分、内定が出たときの喜びは大きいでしょう。しかし就職祝いを渡すのには適切な時期や金額の目安があります。
この記事で基本的な就職祝いのマナーを知り、相手に喜ばれる品を選びましょう。

就職祝いを渡す適切なタイミングは?

就職祝いを選ぶ前に、就職祝いを渡すタイミングを知っておきましょう。
実は内定が出たからといって、すぐにお祝いを渡すのはNG。ここでは2つのポイントで解説します。
就職祝いは3月を待って渡すのが妥当
就職祝いを渡すタイミングは、早くても卒業する3月を待ってからです。「内々定をもらった」「内定が出た」と聞いても、そこからすぐにお祝いを渡すのは避けましょう。
なぜなら最悪内定取り消しになったり、卒業できなかったりする可能性があるからです。
この記事もオススメ

就職の知らせを受けた場合は入社式1ヶ月以内に
一方、「就職した」と報告を受けた場合は、できるだけ早い時期に就職祝いを贈りましょう。
目安としては、遅くても入社式後1ヶ月以内です。その場合、新生活に少しずつ慣れてきたときに使えるものを選ぶと喜ばれるでしょう。
就職祝いの相場


次に気になるのが就職祝いの相場です。これは立場によって異なるため一概には言えませんが、目安となる金額はあります。
以下に示しましたので参考にしてください。
上記を参考にその金額相当のプレゼントを選ぶほか、「就職祝い金」として現金を送ったり、商品券を贈ったりしてもよいでしょう。
新生活準備には出費がかさむため、モノよりも現金が喜ばれるケースもあります。
のしをつける場合は「就職御祝」など
就職祝いのプレゼントや現金にのしをつける場合、以下のような表書きにしましょう。
- 就職御祝
- 祝御就職
- 賀社会人(読み方:しゃかいじんをがす・意味:就職おめでとう)
- 就職おめでとう
- 御服地料(読み方:おんふくじりょう・意味:これでスーツを作ってください)
いずれも水引の色は紅白で蝶結びにしましょう。
のしをつけずお祝いの言葉を添えるのもOK
先輩や後輩、友達へ就職祝いを渡す場合、「のしをつけるのはなんだか堅苦しい」と感じることもあるでしょう。
そのような場合は就職を祝う言葉をカードなどに書いてプレゼントと共に渡しても問題ないです。後ほど就職祝いのメッセージ例文を紹介しますので参考にしてください。

就職祝いのプレゼント選びのポイント


就職祝いにプレゼントを贈る場合、どのようなものが喜ばれるのでしょうか。
ここではプレゼントを選ぶ際の5つのポイントを解説します。
相手の好みに沿ったものを選ぶ
就職祝いに限りませんが、プレゼントは相手の好みに合ったものを選ぶのが大前提。明らかに使わないようなものや、転居を予定しているのに大型のものを選ぶのは避けましょう。
親しい間柄であれば、相手の好みもおおよそは検討がつくでしょう。その好みに合った品を選ぶか、場合によっては一緒に選びに行くのもおすすめです。
新社会人生活で役立つものを選ぶ
例えば、万年筆や財布などは就職祝いの定番の品でしょう。しかしそのようなものを明らかに使わない職に就いていたり、すでに愛用品があったりするのであれば、避けるのが無難。
新社会人としてこれから生活をする上で、あると役立つものを選ぶと喜ばれます。
もし後輩に就職祝いを贈るのであれば、自分が新生活当初に役立ったものや必需品だったものを思い出すとよいでしょう。
後輩から先輩に贈るのであれば、すでに社会人経験がある人に「新生活でもらって嬉しかったものは何ですか」と尋ねてみるのもおすすめです。
相場からかけ離れた高級なものは避ける
就職祝いに選ぶものは、前述した相場を目安にしましょう。相場からかけ離れた高級品を贈ると、「何かお返しをしなければ」と気を遣わせてしまう可能性があります。
新生活のエールを送るためのお祝いですから、相手が素直に喜べるような、相場感を持ったプレゼントにしましょう。
仕事だけでなくプライベートで使えるもの
スーツやネクタイ、ベルトなど、仕事で使うものはすでに自分で買い揃えていたり、他の人からもらっていたりする可能性があります。
とくに後輩や先輩、友人などフランクな関係であれば、仕事だけでなくプライベートでも使えるものを選ぶとよいでしょう。
悪目立ちするものを避ける
仕事で使えるワイシャツやハンカチ、ネクタイなどを贈るなら、無難なカラーやデザインのものを選びましょう。
例えばワイシャツであれば白地に薄いストライプ、ハンカチやネクタイであれば紺色など、オールマイティに使えるものなら重宝します。
一方で奇抜なデザインやカラーのものは悪目立ちしますし、限られたシーンでしか使えない可能性も。
特別な日に使うものは自分自身で選びたい人も多いでしょうから、就職祝いで選ぶものはシーンを選ばず使えるものにしましょう。
場合によってはタブーとなるものも
就職祝いの贈り物としてタブーとされるものもあります。以下にいくつか例を挙げますので参考にしてください。
・白のハンカチ:「手巾(てぎれ)」=「手切れ」を連想されるためお祝い事には向かないといわれています。色柄ものは問題ありません。
・お茶:弔事のイメージがあるためお祝い事としては向かないと言われることも。近年はお祝い用のお茶ギフトもあり、贈る相手がお茶好きなら問題ないでしょう。
・櫛(くし):「苦」「死」を連想させるといわれています。
年上にはタブーと言われるもの
年上にお祝いを贈る際、以下のような意味を持つため失礼にあたる場合があります。
- 靴・靴下:「踏みつけるもの」
- 時計・カバン:「より勤勉に」
- ペン・万年筆:「もっと精進しろ」
- ベルト:「腹をくくれ」
- 印鑑:「自立を促す」
- 現金:見下しているイメージを持たれることがある
しかしいずれの場合も、本人が希望していれば贈っても構いません。大事なのは贈る相手のことを想ってお祝いを選ぶことです。
何かしらメッセージをつけよう
就職祝いを渡すときは、物だけでなく、何かしらのメッセージを添えましょう。
もらった人の新生活を後押しできるような言葉なら素敵ですね。実際に自分がかけられて嬉しかった言葉をメッセージに添えるのもよいでしょう。
就職のお祝いの言葉を例文で紹介
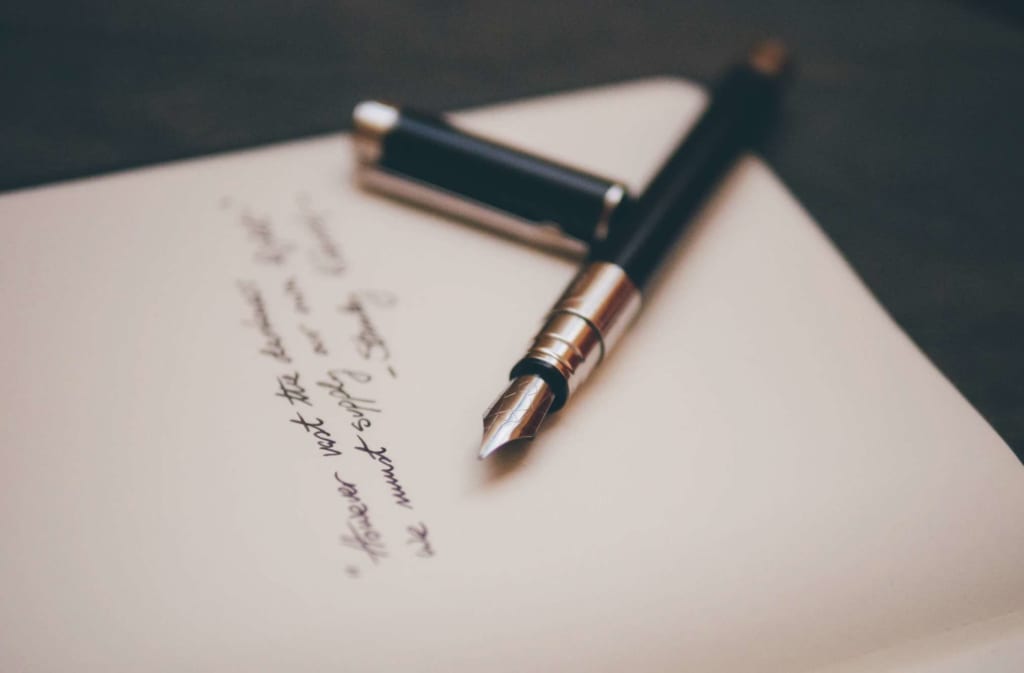
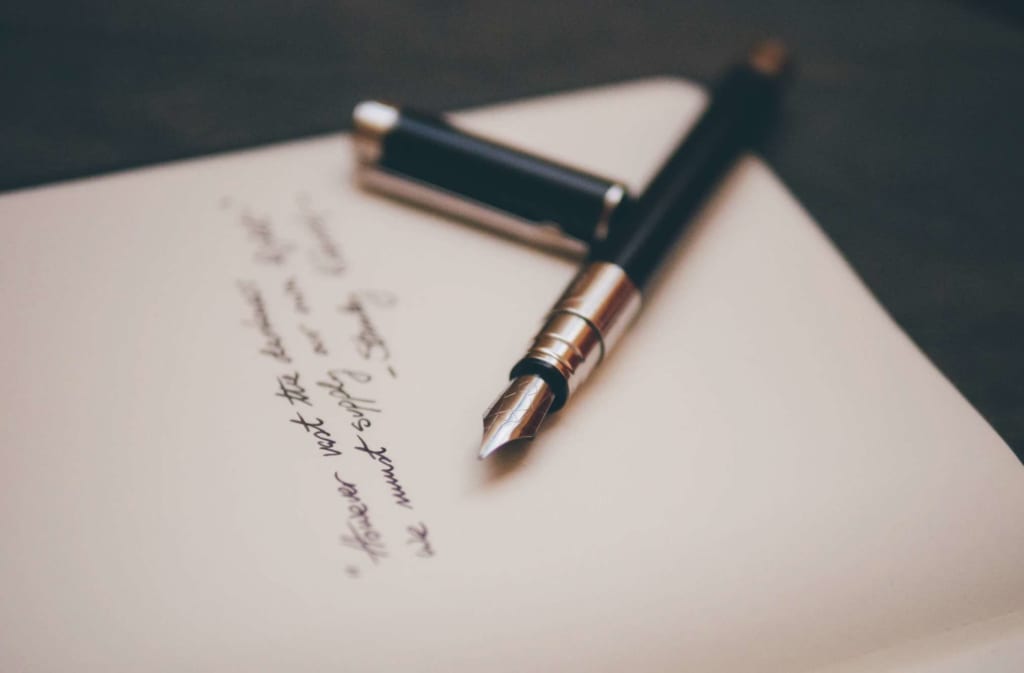
就職祝いに添えるメッセージを立場別に紹介します。
【先輩→後輩】就職祝いの言葉
就職おめでとう!
報告してくれたとき本当に嬉しかったよ。
春から新しい職場、楽しみだな!
〇〇ならきっと活躍できるよ。
何か困ったことがあったら、またいつでも連絡してください。
落ち着いたらご飯でも行こう!
〇〇、就職おめでとう!
報告を受けたときは自分が就職決まった時のことを思い出してしまったよ……
本当に頑張ったね。
でも、ここからが本当のスタート。
まあ、〇〇ならきっとどんなことでも乗り越えていけると思うけれど
何かあったらまたいつでも相談してね。
これからも応援しています!
【後輩→先輩】就職祝いの言葉
〇〇さん、ご就職おめでとうございます!
ずっと目指されていた業界に決まったとのこと……
先輩が頑張っているのをずっと見ていたので、自分のことのようにうれしいです。
わたしも先輩のように自分の目指す道を進めるよう頑張ります。
春からの新生活、応援しています!
ご就職おめでとうございます。
いつもサークルを引っ張ってくれる〇〇さんなので、新しい職場でもご活躍される姿が目に浮かびます。
落ち着いたら、また社会人生活についていろいろお話聞かせてください。
これからも応援しています!
【親戚→甥・姪】就職祝いの言葉
〇〇くん、ご就職おめでとうございます。
あんなに小さかった〇〇くんがもう社会人なんて…時の流れを感じます。
新生活、初めは慣れないこともあるかもしれないけれど、くれぐれも体には気をつけて。
〇〇くんらしく元気いっぱい、頑張ってください。
また帰省したときはお話聞かせてくださいね。
就職おめでとうございます。
〇〇ちゃん、よく頑張りましたね。
お父さん、お母さんもきっと喜ばれていることと思います。
春からの新生活、くれぐれも体には気をつけてくださいね。
また帰省したときは顔を見せてください。
応援しています。
忌み言葉に気をつけよう
お祝いの言葉を考える際に気をつけたいのが「忌み言葉」です。新生活の門出を祝う際に適さない、以下のような言葉は避けるようにしましょう。
- 会社の倒産・経営悪化を連想させる言葉:「崩れる」「傾く」「倒れる」「失敗」
- 会社との関係がなくなることを連想させる言葉:「すべる」「取り消す」「中止」「切る」
はじめての転職、何から始めればいいか分からないなら
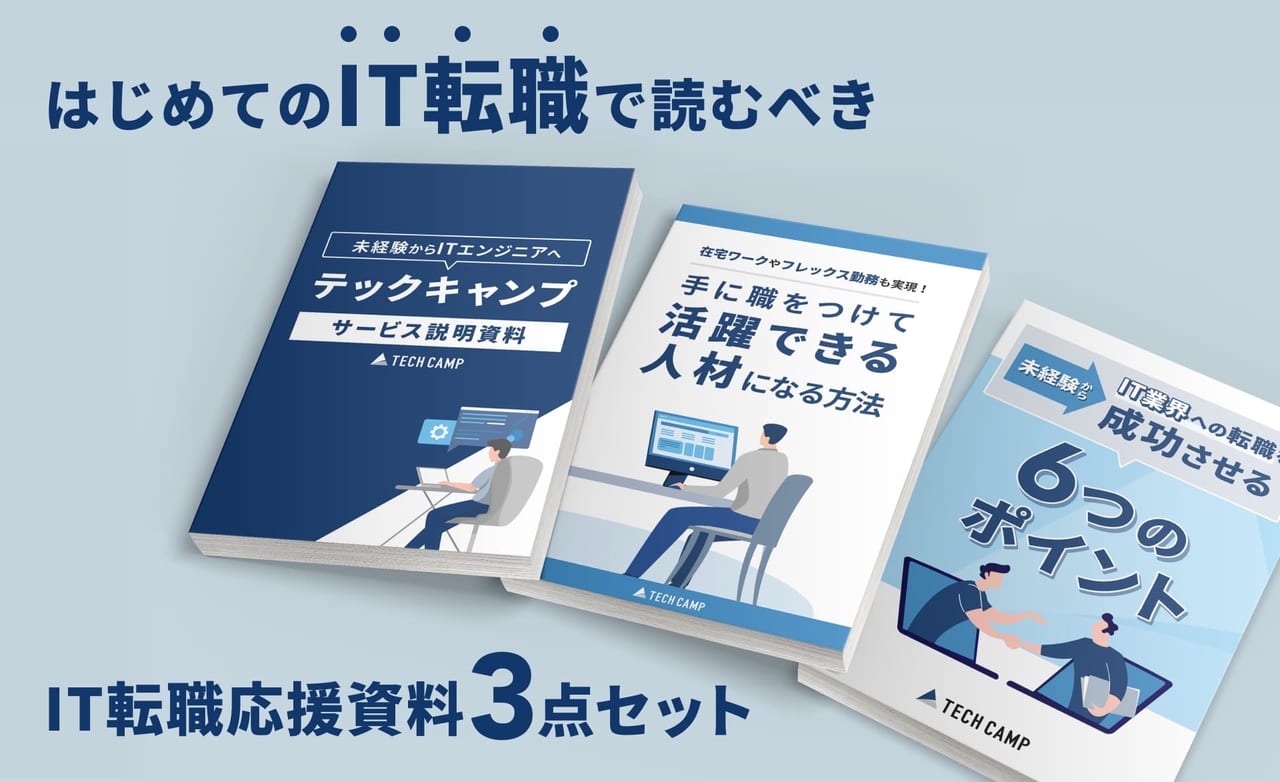
「そろそろ転職したいけれど、失敗はしたくない……」そんな方へ、テックキャンプでは読むだけでIT転職が有利になる限定資料を無料プレゼント中!
例えばこのような疑問はありませんか。
・未経験OKの求人へ応募するのは危ない?
・IT業界転職における“35歳限界説”は本当?
・手に職をつけて収入を安定させられる職種は?
資料では、転職でよくある疑問について丁寧に解説します。IT業界だけでなく、転職を考えている全ての方におすすめです。
「自分がIT業界に向いているかどうか」など、IT転職に興味がある方は無料カウンセリングにもお気軽にお申し込みください。