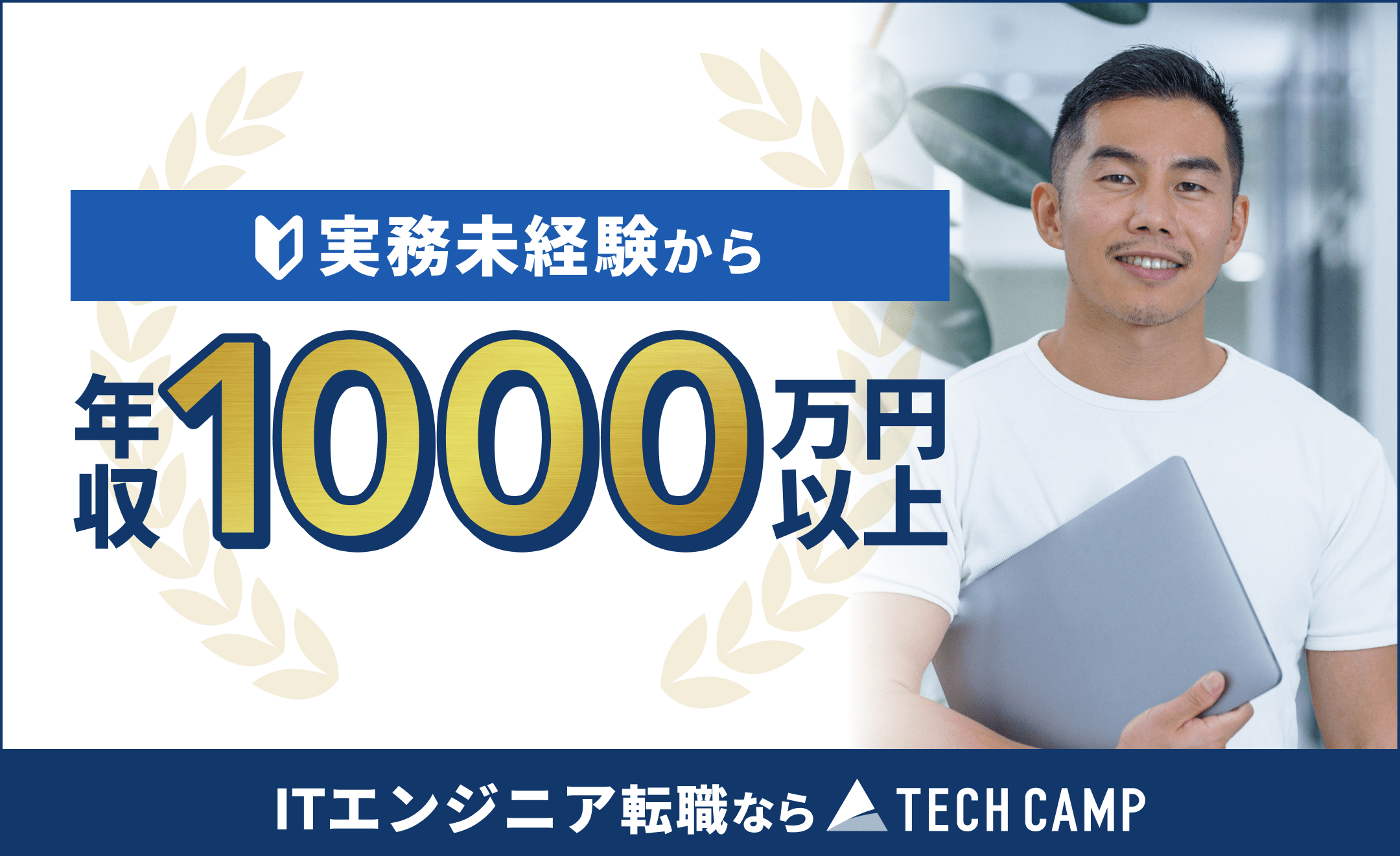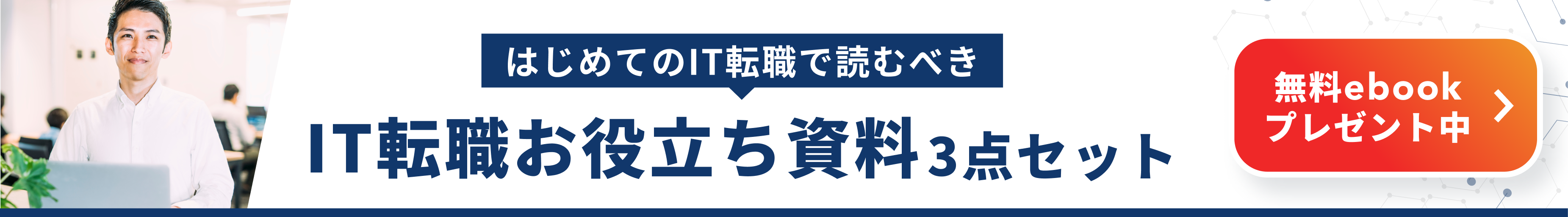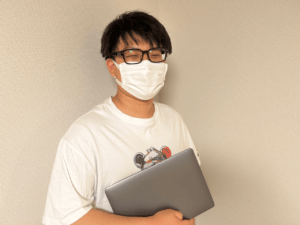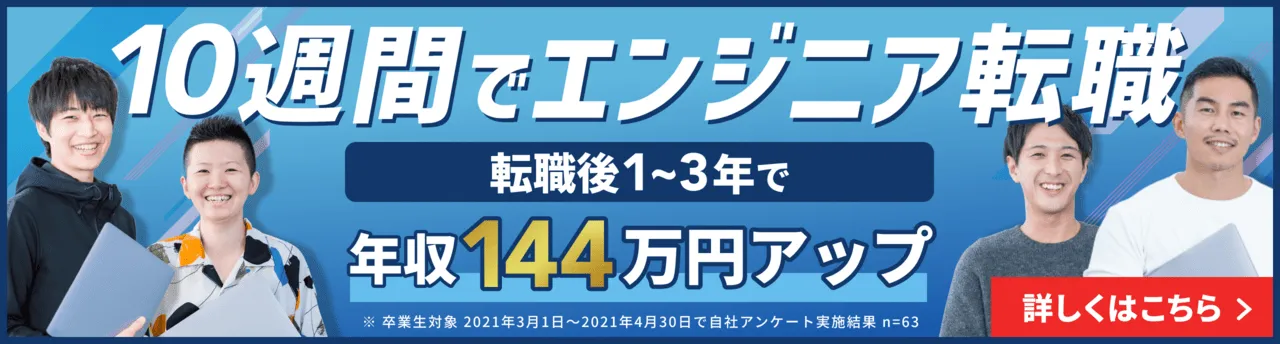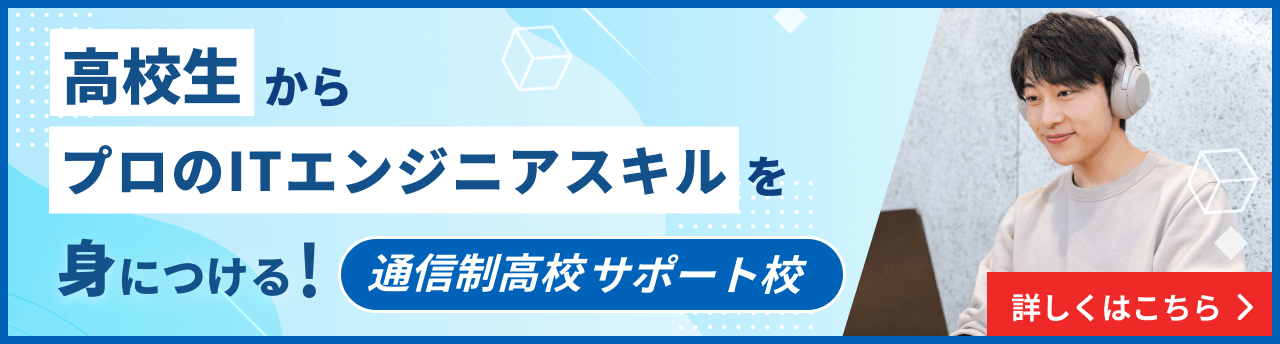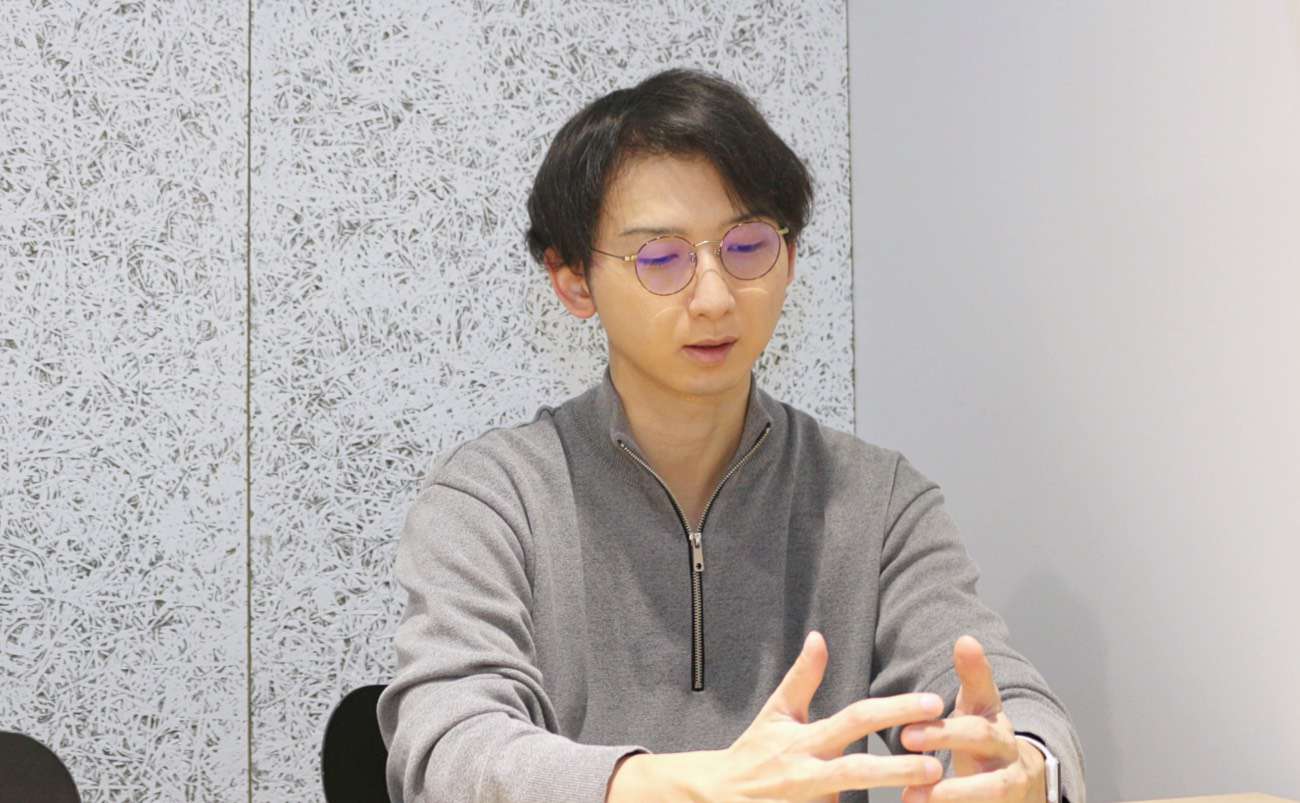本記事では、代休を取得する際の基本的なルールや振替休日との違い、企業が代休を取得させないことは違法なのかなどについてまとめました。
社会人経験が少なく代休のシステムがよく分からない方や、代休が取得できず違法ではないかと気になっている方は、ぜひ参考にしてください。
この記事もオススメ


代休とは?


まず代休の概念について説明します。代休とは、休日出勤をした後、別の勤務日に休みを取得することです。本来休みだった日に勤務した分の代わりの休みが代休に当たります。
代休は時間単位で取得することも可能です。例えば、「日曜日に4時間勤務したため、翌日の月曜日に4時間の代休を取得する」など。
代休の取得は労働基準法で定められた義務ではなく、取得期日などのルールも企業によって異なります。代休を取得する際に不明なことがあれば、人事・労務担当者に確認するようにしましょう。
代休と振替休日の違い
代休とにている言葉に「振替休日」があります。「どちらも同じではないの?」と、区別なく使っている方も多いのではないでしょうか。実は代休と振替休日には違いがあります。
- 代休:休日出勤をした後に決めた代わりの休日
- 振替休日:休日出勤する前にあらかじめ決めていた休日
また賃金の面でも違いがあります。
代休の場合、休日出勤した日は割増賃金の対象となり、法定休日(「毎週1日」または「4週間で4日以上」与えられる最低限の休み)なら35%以上の割増賃金、法定外休日(法定休日以外の休日)なら25%以上の割増賃金になります。
法定休日と法定外休日の定義は会社によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
一方、振替休日の場合は事前に休日と別の勤務日を交換しただけのため、割増賃金の対象にはなりません。ただし、週の法定労働時間(40時間)を超えて働く場合や、労働時間が深夜まで及んだ場合は、割増賃金の対象になることがあります。
代休を取得させないのは違法なのか?
企業が従業員に代休を取得させないのは違法になるのでしょうか。
違法となるかどうかは、休日の日数によります。労働基準法では、「毎週1日の休み」または「4週間で4日以上の休み」を従業員に与えることを規定しています。代休を取得させないことでこの規定の休日日数を下回る場合、違法となる可能性があります。

休日出勤が当たり前の会社で働くべきか?


本記事を読んでいる方の中には、「休日出勤が当たり前になっているが、代休や振替休日が取れなくて困っている」という方もいると思われます。
休日出勤が当たり前になってしまうと、プライベートのスケジュールが組みにくくなり、生活に支障が出ることもあるでしょう。さらに、代休・振替休日が取れないような制度や風潮がある企業で働き続けると、心身に悪い影響が出てしまう可能性もゼロではありません。
何らかの目的や理想があってその企業に勤めていたり、今の仕事が好きで働いていたりするのであれば、休日出勤が多くても続けられるかもしれません。しかしそうでないのであれば、改めて働き方を見直し、自分に合った企業を探した方がよいでしょう。
休日をしっかり定めている企業や、代休・振替休日の取得を必須にしている企業はたくさんあります。現状の働き方に不満があるのならば、転職も解決方法の1つです。
この記事もオススメ



休日出勤と代休・振替休日の仕組みを理解しよう
会社勤めをしている方は、休日出勤になる機会が少なからずあると思われます。その際は代休または振替休日を取得するのが基本であることを知っておきましょう。
代休・振替休日の詳細なルールは企業ごとに決まっているため、分からない点があれば担当部署に確認を取ることをおすすめします。
この記事もオススメ



はじめての転職、何から始めればいいか分からないなら
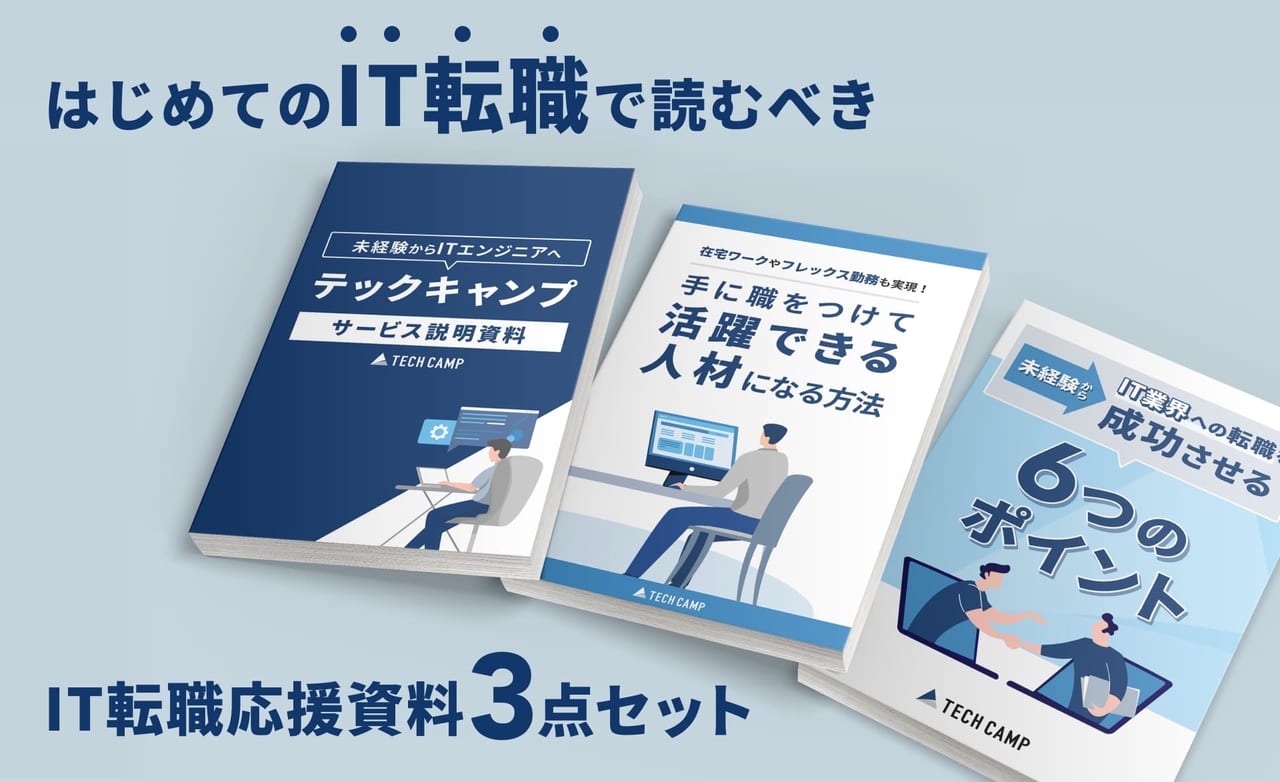
「そろそろ転職したいけれど、失敗はしたくない……」そんな方へ、テックキャンプでは読むだけでIT転職が有利になる限定資料を無料プレゼント中!
例えばこのような疑問はありませんか。
・未経験OKの求人へ応募するのは危ない?
・IT業界転職における“35歳限界説”は本当?
・手に職をつけて収入を安定させられる職種は?
資料では、転職でよくある疑問について丁寧に解説します。IT業界だけでなく、転職を考えている全ての方におすすめです。
「自分がIT業界に向いているかどうか」など、IT転職に興味がある方は無料カウンセリングにもお気軽にお申し込みください。