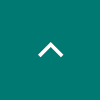導入事例
「テックキャンプ研修でバックオフィスの業務改善に成功」
ウーブン・バイ・トヨタが挑むDX人材育成とは

ウーブン・バイ・トヨタ株式会社は、トヨタ自動車株式会社のモビリティ技術を開発する子会社であり、「安全でスマートな人に寄り添うモビリティをすべての人に届ける」ことをミッションとしています。主にソフトウェアプラットフォーム「Arene(アリーン)」、自動運転技術、Woven Cityプロジェクトを推進しています。
既に本研修を導入済みのトヨタ自動車から紹介を受けて、2022年度〜2023年度と2年連続でテックキャンプ 法人研修サービスのDX人材育成コース(https://tech-camp.in/training)を実施しました。今回、テックキャンプの研修を通して得られた成果や、今後のDX人材育成の展望について、神山さん(責任者)と池内さん(1期受講生 兼 1期・2期運営事務局担当)にお話をお伺いしました。

●神山和晃
1990年トヨタ自動車株式会社に入社。自動車の法規認証業務や本社技術開発拠点の総務部門を担当。2020年からWoven by ToyotaにてAD/ADAS開発部門のProductivity Promotion OfficeのHeadとして、部門内間接業務の効率化やDX化を推進中。

●池内亜香里
2017年トヨタ自動車株式会社に入社。レクサスインターナショナルにてレクサスブランドの国内マーケティング施策及びレクサス販売店での販促グッズ制作等を担当。2021年からWoven by ToyotaにてAD/ADAS開発部門のProductivity Promotion Officeメンバーとして部門内間接業務の効率化やDX化を推進中。
本研修では、運営事務局メンバーでありながら1年目には自身も受講生として参加している。
エンジニアリング分野ではDX化が進んでいたものの、バックオフィス分野では課題を抱えていた

ーー2年連続で研修をご利用いただいていますが、研修実施前の2022年頃の御社のDX化に向けた取り組みや課題感について教えていただけますでしょうか。
弊社は、最新のソフトウェアやサーバー、デバイスを導入するなど、エンジニアリング分野でのDX化は進んでいました。
一方で、人事や経理などのバックオフィス分野に関しては課題がありました。各部署が独自のシステムを導入していましたが、これらのシステムの互換性が十分ではなかったんです。予算の紐付けや管理を人手で行う必要があり、当時はアシスタントがその役割を担っていました。
この現状を解消するために、バックオフィスのDX化が必要でした。
また、私自身がトヨタ自動車から出向してきた背景もあります。2018年から2019年にかけて、トヨタ自動車ではRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)のソフトが導入され始め、私もその展開を部内で担当していました。
そのため、出向してからもバックオフィスのDX化を常に意識していましたが、なかなか上手くいかず、壁にぶつかっていました。例えば、Excelを使って自動化を試みましたが、うまくいかない部分が多かったのです。
トヨタ自動車で導入された研修が、業務の標準化とDX化に役立つと感じた
ーーどのような過程でテックキャンプ法人研修サービスの導入に至ったのでしょうか?
神山さん:
バックオフィスのDX化に課題を感じていたちょうどその頃、トヨタ自動車のカウンターパートと「自工程完結活動」※注釈1と呼ばれるプロセス改善活動を進めていました。
その活動の中で、テックキャンプ法人研修サービスの紹介を受けたんです。
テックキャンプの研修では、業務プロセスを分解し、ITを活用して自動化の実装まで行っていくと聞きました。この一連の流れを経て整流化の考え方を社内に広めることは、トヨタ自動車からの受託業務を主とする弊社にとって、非常に親和性の高い取り組みだと感じました。
※注釈1 自工程完結:トヨタ自動車の製造現場から生まれた「自らの工程を完璧に遂行し、次の工程に不適合品を流さない」という考え方。製造分野だけでなくあらゆる業務においてこの考え方が浸透しており、ビジネス職でも「目的、目標の的確な設定、作業の見える化を行い、タスクごとに徹底的に品質を高める」という改善活動を継続的に行っている。
ーー研修を受講された方々の部署や仕事内容はどのようなものですか?
池内さん:
受講したのは主にバックオフィスチームやエンジニアリングチームに所属しているアシスタントのメンバーです。バックオフィスチームは社内の契約やファイナンス関係の取りまとめを行っており、エンジニアリングチームをサポートする部門と言えます。また、データ処理や予算管理も行い、バックオフィスの中心的な業務を担っています。
特にアシスタントを対象とすることで、研修を通じて自動化スキルやTPS※注釈2の考え方を身に付けてもらい、業務の標準化を進め、バックオフィスのDX化を推進する人材を育成したいという意図がありました。
※注釈2 TPS(トヨタ生産方式):世界中で知られているトヨタ自動車のモノのつくり方。ムダを徹底的に排除し、良いものを安く、タイムリーに届けることを目的としている
トレーナーとの定期面談や質問サポートが、理解を深め、モチベーションを高めてくれた

ーープログラミングを扱う研修を実施するにあたって不安はありましたか?
池内さん:
正直ありました。プログラミングの経験が全くない受講生がほとんどで、特にスプレッドシートの関数に対して苦手意識を持っている方が多かったです。そのため、本当に自動化スキルが身に付くのか不安がありました。
ーー実際に研修が始まってからの受講生の反応について教えてください。特に、トレーナーのサポート体制はどうでしたか?
担当トレーナーさんとの定期面談は毎週行われており、次の面談までに進捗を上げるというプレッシャーがモチベーションとして働きました。また、質問対応は初心者にもわかりやすく説明していただいたおかげで、理解が深まりました。
チャット質問に関しても、迅速に対応いただきコミュニケーションが取りやすかったです。質問をする際のフォーマットに則って要点をまとめる作業は、自分の考えを整理するのに大変役立ちました。
ーー企業担当者としての池内さんの視点から、週次報告や定例ミーティングについての感想を教えてください。
池内さん: 週次報告で学習の進捗が見える化されていたので、必要なサポートをすぐに受講生に提供できました。進捗が停滞している受講生には、職場サポーター※注釈3と連携して解決策を見つけることができたと感じています。
※注釈3 職場サポーター:研修受講生の先輩や上長にあたる方。受講生が自業務の改善を進める上で相談にのったり、進め方のアドバイスを行ったりしている。社内のシステムや所属部署の業務に直結するテーマを取り扱うため、divのトレーナーでは把握しきれない部分もあることから、職場サポーターがトレーナーとともに受講生をサポートしている。
研修で業務自動化に成功、今後もDX化を進めていきたい

ーー研修の具体的な成果についてもお伺いしたいです。特に印象的だった自動化の事例はありますか?
神山さん:
はい。研修では様々な業務自動化に取り組みましたが、中でも予算管理や購買発注の承認プロセス自動化が印象的でした。研修終了後にはこれらを統合して、より効率的なプロセスを構築しました。また、Slackを使った承認フローの自動化なども行い、業務の効率化が大きく進みました。
ーー今後取り組んでいきたいことや目標について教えてください。
神山さん:
引き続きDX化を進めていきたいと考えています。
当社は継続的に人材の出入りがあるため、経験者が減ってしまうおそれのある現状を踏まえて、新しい受講者を募り、育成することが重要だと考えています。
また、業務自動化のノウハウを持続・発展させるため、研修を受けた方には社内に広める役割も担ってもらいたいと思っています。
ーー今後のテックキャンプ研修に期待することや改善点についてお聞かせください。
生成AIなどの新しい技術を取り入れた研修プログラムがあれば、より応用力が広がると思います。新技術にも対応したプログラムが登場することを期待しています。
ーー最後に、本研修はどのような企業に向いていると思いますか?DX化に困っている企業への一言メッセージをお願いします。
手作業で行っている業務が多い企業や、パソコンを単なる入力装置として使っている企業には、DX化に取り組んでいただきたいですね。
私自身、正直に言って最初は本当にできるのかと思ったこともあったんです。でも、この研修を受けると皆さんしっかり実力をつけてご自身で色々なことができるようになるんですよね。そのため、私からの最後のメッセージとしては、「できますよ。信じてやればちゃんと報われますよ。」ということをお伝えできればと思います。
最新のサービス内容に関しては、下部資料ダウンロードもしくはお問い合わせから、お気軽にご相談ください。
組織課題に合わせた人材育成・研修を提供します。
まずはご相談ください。
お問い合わせください
こちらから