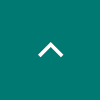導入事例
「文系でも大丈夫」インフォマートの新卒社員が語る、不安を払拭してくれたテックキャンプのエンジニア研修の魅力とは

株式会社インフォマートはBtoB(企業間電子商取引)プラットフォームを運営する東証プライム上場企業。2025年時点の導入企業数は120万社を突破し、BtoBプラットフォームの分野において日本トップのシェアを誇ります。
同社では、文系出身者やプログラミング経験の浅い社員を含めた新卒エンジニアの育成を目指しています。この重要な目標を達成するため、テックキャンプの法人研修サービスを導入しました。
本インタビューでは、実際に研修を受講した(写真左から)小谷さんと山口さん、嬉野さんにお話を聞きました。テックキャンプ法人研修サービスを受講して、エンジニアとしての基礎スキルをどのように習得したのかを紹介します。また、研修を進める中で変化した理想のエンジニア像についても伺いました。
「技術を実務に活かす面白さ」に気づき、エンジニアの道へ

―― まずは、学生時代について教えてください。
小谷さん:文系出身ですが、大学1年次にエンジニアの市場価値に関する動画を見たことがきっかけで徐々にプログラミングに興味を持ちました。それから、PythonやRの学習、Webアプリケーションの開発を独学で経験しました。
山口さん:私は情報科学部だったので、C言語の基礎を学んだり、研究室でKotlinでスマホアプリを作ったりしてました。そのデータを分析するためにPythonを使ったこともあります。
嬉野さん:私も情報学科だったのでJavaやRuby、HTML、CSSを学びました。ゼミでは3Dモデリングについても学習し、プログラミングとは違う楽しさを感じていました。
―― エンジニアを目指そうと思ったのは、どんな経験が影響していますか。
小谷さん:高校の頃から数学や物理が好きで、論理的な思考が得意でした。大学時代にExcelの関数を駆使してデータ処理を行った際、命令通りに正確に動作することに楽しさを感じました。また、サークルで会計係を務め「Excelの技術を実務に活かすことの面白さ」に気づいたんです。その経験がエンジニアを目指すようになったきっかけです。
山口さん:大学で情報系に進んだこともあり、そこで学んだ知識を仕事に活かしたいと考えたため、エンジニアを志すようになりました。
嬉野さん:私も情報学科だったので、IT業界を志す学生が多く、周囲の影響もあり自然とエンジニアを目指すようになりました。
―― みなさん、大学での経験がエンジニアを目指すきっかけになったんですね。
丁寧なカリキュラムと、初めてのチーム開発

―― 大学時代にプログラミングの経験があったとはいえ、それを仕事にするとなると不安もあったのではないでしょうか。
嬉野さん:大学でプログラミングの基礎は学んでいましたが、スキルに対する自信は正直なく、不安もありました。一方でインフォマートは「研修制度が充実している」と聞いていたので、その点は安心材料でしたね。
小谷さん:私は文系出身でしたので、IT業界でやっていけるのかという不安が大きかったです。しかし、4ヶ月間にわたるテックキャンプの研修は、未経験者でも理解できるように非常に丁寧に構成されていました。内容も分かりやすく、安心して学習をスタートできました。
―― 実際にテックキャンプの研修を受けてみて、いかがでしたか。
小谷さん:研修はJavaなどの言語学習から入り、そこから徐々に難しい内容へ進んでいく流れだったので、非常に取り組みやすかったです。振り返ると最初に制作したアプリはシンプルでしたが、当時の私にとっては十分な難易度でした。その後も課題の難易度が常に適切に設定されており、刺激を受けながらスキルアップできたと実感しています。
山口さん:大学で学んだ知識の復習に加え、学生時代に触れられなかった分野を体系的に吸収できたことが大きな収穫でした。特に、Webアプリケーション開発に不可欠なバックエンド技術や、先進的なフロントエンドフレームワークのスキルを習得できたことは印象的です。
―― 特に大変だったと感じた場面があれば教えてください。
嬉野さん:学生時代はペア開発までしか経験がなく、3人以上で取り組むチーム開発は初めてでした。特に、コミュニケーションの取り方については不慣れな部分もあり最初は戸惑う場面もありました。しかし、その分コミュニケーションの大切さを学べました。メンバー間で知識や技術を共有できる環境はとても良かったと思います。お互いに学んだ知識をアウトプットすることで、頭の中を整理できました。
小谷さん:私も、チーム開発の経験がなかったので不安もありました。大規模ではない課題は、一人で進めた方が効率的だと感じる場面もありました。しかし、あえて小規模な課題にチームで取り組むことで、協力して進める難しさを実感できました。実務では大規模な開発をチームで行う必要も出てくるため、この経験が今後に活かせると感じています。
山口さん:エラーが発生したときですかね。環境構築やDockerといった未経験の領域でエラーが出た際は、原因を特定するのに苦労したのを覚えています。
「AIの回答とは違う」エラーや不安を"対話"で解消してくれたメンターの存在

―― 環境構築はどのようにして解決しましたか。
山口さん:未経験の領域でエラーが発生すると、原因の特定が難しく手が止まることが多かったんです。しかし、テックキャンプの研修では、受講生一人ひとりに担当メンターがついていました。そのため一人で抱え込まず、積極的にメンターへ質問することで、スムーズに学習を進めることができました。
嬉野さん:私も環境構築で手こずった際に何度もメンターに相談し、アドバイスをもらっていました。
―― 技術面以外にメンターとはどんなやり取りをしていましたか。
小谷さん:私は復習方法について悩んでいた際に、メンターに相談していました。そのとき、メンターから「それで大丈夫」と後押ししてもらえたことで、安心して復習に取り組むことができました。
嬉野さん:私も復習についてはメンターのおかげでやり方を確立できたと思っています。また、苦手なTypeScriptの参考サイトなど、経験のあるメンターだからこそ知っている情報を教えてもらえたのはありがたかったです。
山口さん:毎週、事前にフォームへ困りごとを記入し、その内容を面談で振り返る仕組みでした。立ち止まって考えるきっかけになり、テキストに書き出すことで思考を整理できたのが非常に有益でしたね。
―― 3人とも振り返りについての話がありましたね。
小谷さん:実際にコードを書いてみると意外なところで行き詰まることもあって、カリキュラムを読むだけでは、自分が理解できていない部分に気づかないんだな、と。復習はそうした課題を洗い出すために大切だと感じました。
山口さん:カリキュラムを読んだ直後は覚えているので問題も解けるのですが、少し時間が経つとできなくなっていることが多くて。だからこそ、繰り返し復習して定着させることが大事だと実感しました。
―― その他にメンターとのやり取りで印象に残っていることはありますか。
山口さん:カリキュラムでつまずいたときはAIにも聞いていました。一方で、メンターとのやり取りはAIの無機質な回答と違い、対話を通して楽しく解決できたのが良かったです。また、雑談の中で趣味の話もできて、息抜きになりました。
嬉野さん:私もメンターと共通の話題で盛り上がりました。最後に『寂しい』と思うくらい良い関係を築けたと思っています。
幅広く対応できるエンジニアになりたい
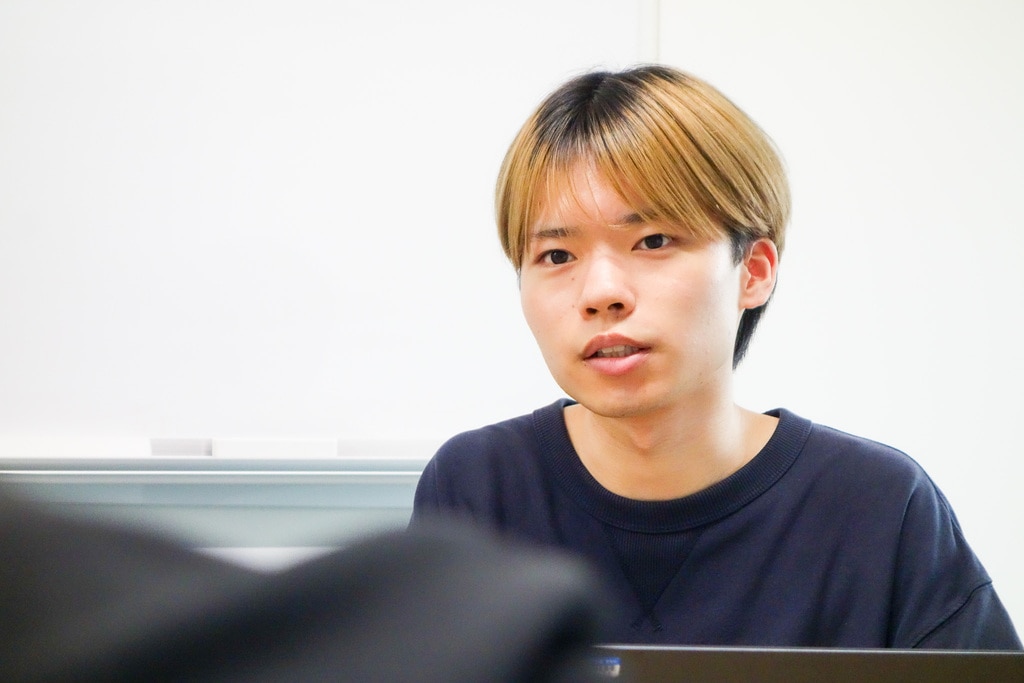
―― 今後、どんなエンジニアになりたいと考えていますか。
小谷さん:チームを引っ張る力やスケジュール管理なども含め、フルスタックに動ける人材を目指しています。
そう思ったきっかけは研修のチーム開発課題です。チームで一つのプロジェクトを推進する中で、メンバー間の連携や認識合わせの難しさを痛感したんです。この経験から、大規模なシステム開発には円滑なチーム連携が不可欠であることを再認識しました。
山口さん:幅広い知識を持ち、他の人とコミュニケーションを取りながら円滑に仕事を進められるエンジニアを目指しています。その上で、自分の強みを発揮できる分野を見つけたいと思います。
入社前は一つの技術を深く追求することが重要だと思っていました。しかし、研修で経験したチーム開発を通して、全体を理解するためにはチーム間の連携が欠かせないと実感しました。
嬉野さん:フロントエンドもバックエンドもこなせるフルスタックエンジニアを目指しています。
会社の方針でフルスタックエンジニアになることが目標としてあるのももちろんですが、私もフロントとバック、どちらの領域も理解することでスムーズに仕事を進められると思い、必要性を感じています。
テックキャンプの研修を通じて力が身につく

―― 最後に、これからテックキャンプの研修を受ける人に、どんな言葉を伝えたいですか。
小谷さん:私自身、文系出身のため研修についていけるか心配でした。しかし、いざ取り組んでみると順を追って進めれば理解できるよう丁寧に作られていました。そのため未経験でも安心して臨んでほしいです。
嬉野さん:テックキャンプの研修を通じて力が身につくと伝えたいです。中でもチーム開発は難しく感じる部分もありましたが、それ以上に充実感が得られました。知らなかった知識をコミュニケーションを通して吸収できたのは一番の収穫です。
山口さん:カリキュラム通りに進めれば基本的にはスムーズに進みます。もしカリキュラムにないエラーが出たり、環境構築でつまずいたりしても、メンターが親身になって教えてくれるので心配いりません。「分からない部分が出てきても、サポートしてもらえるから大丈夫だよ」と伝えたいです。
―― みなさん、本日はありがとうございました。
最新のサービス内容に関しては、下部資料ダウンロードもしくはお問い合わせから、お気軽にご相談ください。
組織課題に合わせた人材育成・研修を提供します。
まずはご相談ください。
お問い合わせください
こちらから