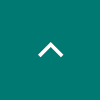導入事例
「AI時代だからこそ基礎力を」デジタルガレージがテックキャンプのエンジニア研修を選ぶ理由

株式会社デジタルガレージは国内最大級の決済プラットフォーム事業を軸に、マーケティング、スタートアップ投資事業、最先端テクノロジーを活用した新規事業を展開するIT企業です。
同社は組織の継続的な成長には新卒採用の強化が欠かせないと考えています。その上で、採用した新卒エンジニアの早期戦力化が重要な課題となっており、その解決策としてテックキャンプ法人研修サービスを導入しました。
本インタビューでは、同社が新卒エンジニア研修にテックキャンプを選んだ理由や教育に力を入れる背景、今後のエンジニアに求められる役割について、DG Technology本部 DGTエンジニアリング部 部長の髙橋さんにお話を聞きました。
生成AIの普及でエンジニアの役割が変わってきている

―― まず、研修を導入しようと考えたきっかけを教えてください。
新卒エンジニアをOJTだけで育成することに限界を感じていました。というのも、共通して身につけてほしい基礎を定着させるのが難しい状況だったんです。
具体的には、配属先や指導者、プロダクトによって進め方やルールが異なり、学ぶ内容や深さにばらつきが生じていました。
そこで、新卒エンジニア全員が体系的に基礎スキルを学べるように、外部研修の導入を決めた、という経緯です。
―― 研修では特に基礎力の定着を重視していると伺いました。どのような背景やねらいがあるのでしょうか。
背景には、生成AIの発展という大きな要因があります。
生成AIの活用が急速に進むことで業務の自動化が加速し、特にコーディングはAIで代替可能な領域となりました。その結果、エンジニアの役割は「コードを書くこと」から「作るものを定義し、設計を行い、品質やセキュリティを担保し、成果物を責任をもって説明すること」へと移りつつあります。
こうした環境変化の中では、特定の言語に依存したスキルよりも、言語を問わず活用できる普遍的な基礎力こそが重要だと考えています。
カリキュラムを一緒に設計できたことがテックキャンプの研修を選んだ決め手です

―― テックキャンプを選んだ決め手について教えてください。
私たちがテックキャンプを選んだ大きな理由は、自社の方針に合わせてカリキュラムを柔軟に設計できる点です。
私は昨年ジョインしたため初回導入の経緯は把握していませんが、導入後の研修を実際に見て、受講者が十分に成長していると感じていました。そうした実績を踏まえて2025年も検討を進める中で、カリキュラムを目的に合わせて設計できる点が最終的な決め手となり、今年も引き続き導入することを決定しました。
私たちは、生成AIの発展を踏まえて「AIの活用を前提として開発できるエンジニア」を育成する方針を掲げています。いわゆる「AIネイティブなエンジニア」です。そのためには、特定の言語やフレームワークに依存せず、要件定義・設計・品質・セキュリティといった基礎力を体系的に身に付ける必要があります。繰り返しになりますが、この方針に沿ったカリキュラムを共に作り上げられる点が、テックキャンプ導入の決め手になりました。
―― 生成AIの広がりを踏まえて、エンジニアにはどのような能力が必要だと考えていますか。
生成AIがコードを自動生成できるようになった今、エンジニアの役割は確実に上流工程へシフトしています。正しいコードを生成するためには、仕様や要件を正確に定義し、設計・品質・セキュリティの観点まで含めて考えられる力が求められます。
実際、エンジニアチームの中でも生成AIを効果的に使いこなしている人は、前提知識や基礎スキルを備えている人の方が多い傾向にあります。だからこそ、全員が共通して基礎力を身につけることが今まで以上に重要だと考えています。
チーム開発を通じて実務に直結するスキルを習得

―― テックキャンプの研修を受けた社員の感想はいかがでしたか。
学生時代から開発経験がある社員もいましたが、「モダンな技術に触れられた」「開発のインターンやアルバイトでは経験しなかった領域にも取り組めた」といった感想を聞いています。
経験がある新入社員も、個人開発が中心だったため、今回の研修で経験したチーム開発を通じて、チーム内での役割分担やコミュニケーションの取り方、タスクの割り振りなどを実践的に学べたことは、特に大きな収穫となったようです。
―― メンター伴走についてはどのような声がありましたか。
受講者からは技術的なサポートだけでなくマインド面でも支えになったと聞いています。表面的なやり取りではなく、受講者の様子や発言をもとに、悩みや不安を深掘りしてくれた点が助かったそうです。
また、週に一度の面談では、研修の目的や意味づけをしてくれることで、新入社員のモチベーション維持にもつながっていました。
スキル面については、研修で得た気づきや学びを実務にどう活かすかといった視点でアドバイスがあり、メンターの経験を踏まえたフィードバックがより実践的に感じられたようです。
どういうエンジニアになってほしいかを伝えることが大事

―― 最後に、新入社員研修を検討している企業の担当者に向けてメッセージをお願いします。
最終的に学ぶのは新入社員です。だからこそ、いかにして本人の納得感を引き出し、主体的に学べる状態を作るかが重要だと考えています。どれだけ充実したカリキュラムでも、学ぶ意義を実感できなければ知識は定着しません。
そのためには、研修を始める前に「どのようなエンジニアに育ってほしいのか」を明確に伝えることが大切です。会社の状況や業界の変化を背景に示すことで、新入社員が「自分は何のために学ぶのか」を考えるきっかけとなり、主体的に学ぶ姿勢につながります。
テックキャンプの魅力は、こうした企業の育成方針や背景をカリキュラムに反映できる点です。「こういう人材を育てたい」「こういう価値観を伝えたい」といった要望を丁寧にくみ取ってもらえるため、同じような課題を持つ企業にとっては心強いパートナーになるはずです。
最新のサービス内容に関しては、下部資料ダウンロードもしくはお問い合わせから、お気軽にご相談ください。
組織課題に合わせた人材育成・研修を提供します。
まずはご相談ください。
お問い合わせください
こちらから